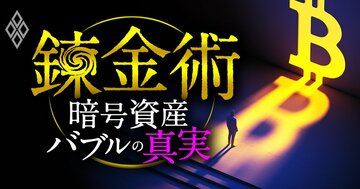過度な金融緩和で投機的な需要増加
物価上昇率高まれば名目金利引き上げ必要
なぜなら、現状では金融が過度に緩和的になっているからだ。その結果、株式や不動産に対する投機的な需要が増えている。
この点をもう少し詳しく説明するために、次のような単純化された経済を考えよう。
世の中にはさまざまな実物資産があり、その価格上昇率を「インフレ率」と呼ぶことにする。そして、現在から将来の時点までのインフレ率の予想値を「期待インフレ率」と呼ぶ。ここで「実質金利」とは、次式(「フィッシャー方程式」と呼ばれる)で定義されるものだ。
実質金利=名目金利-期待インフレ率 (1)
いま日本経済では、直近、消費者物価上昇率は3%前後、政策金利は0.5%なので、期待インフレ率として現実の消費者上昇率を取れば、実質金利はマイナスの状況といえる。
実質金利がマイナスになっていると、何が発生するか?
仮に名目金利が1%であり、期待インフレ率は3%である場合を考えてみよう。
1億円を名目金利1%で借り入れ、これを実物資産に投資したとする。すると1年後に1.03億円になると期待できる。他方、借入金の返済額は1.01億円だ。したがって、0.2億円の利益を期待することができる。
ただし、購入した実物資産の価格が必ず期待インフレ率通りに上昇するとは限らない。つまり、この投資にはリスクがある。したがって、この投資が正当化されるには、利益である「期待インフレ率-名目金利」が一定値以上であることが必要だ。これを「リスクプレミアム」と呼ぶ。
すると、前記の投資が正当化されるための条件は、次式で表されることになる。
期待インフレ率-名目金利>リスクプレミアム (2)
期待インフレ率が高まったとき、それに応じて名目金利を引き上げなければ、(2)式の左辺は大きくなるので、(2)式が成立する投資対象が増える。
したがって、社会的に見て不必要な投資も正当化されることになる。
これは、金融が過度に緩和的になっていることを意味する。これを防ぐために、名目金利を引き上げる必要がある。
個々の具体的場合に具体的数字がどうなっているかは、投資によって異なる。特に問題なのは、期待インフレ率がどうなっているかだ。
期待インフレ率は、現実のデータとしては観測できないので、推計することになる。大まかに言えば、期待インフレ率として、現実の物価上昇率を取ることができるだろう。
そうだとすれば、現実の物価上昇率が高まる状況では期待インフレ率も高まるので、それに合わせて名目金利を引き上げなければ、(2)式の左辺が大きくなってしまう。
つまり、それまで投資が行われなかった場合でも、投資や投機が行われるようになる。だから、現実の物価上昇率が高まれば、それに合わせて名目金利を引き上げていく必要があるのだ。
10月決定会合で公表された「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)では、「不動産価格や株価といった資産価格の動向には留意が必要」としているが、「全体としてみれば、資産市場(中略)には過熱感はみられていない」としている。
しかし、この判断は、日本経済の現状に照らして、再検討の余地があるだろう。