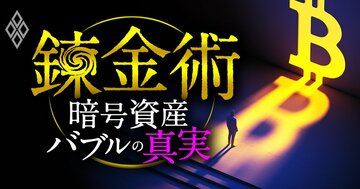過度の円安を防ぐためにも
政策金利引き上げが必要
過度に緩和的な状況が投機的な需要を増やすという問題は、為替レートについても適用できる。
以下では、円で借りてドル資産に投資し、一定期間後に円に戻す取引を考えよう(このような取引は「円キャリー取引」と呼ばれる)。
この場合には、(2)式における「名目金利」を「円金利」とし、「期待インフレ率」を「ドル金利+売却益率」で置き換えればよい。
すると、円キャリー取引が正当化される条件は、(2)式から次のようになる。
(ドル金利+売却益率)-円金利>リスクプレミアム (3)
だがドル資産に投資してから円資産に戻すまでの間に円高が進むこともある。その場合には売却益がマイナスになる場合もあるので、この取引はリスクが非常に大きい。つまり、リスクプレミアムの値が大きい。
なお、円キャリー取引は、円を売ってドルを買う取引なので、それが増えれば、円安をもたらすことになる。
ベッセント財務長官が
日銀の独立性の重要さを指摘
自民党総裁選の前に1ドル=147円だった円相場は、10月30日には153円まで下落した。
こうした状況の下で、ベッセント米財務長官は、10月29日にXに投稿し、高市政権が日銀の政策の自由度を認めることが重要だと、日銀の利上げを後押しするかのような姿勢を示した。この投稿は、円安によるアメリカの対日貿易収支赤字拡大を抑えるとの意図からされたものだろう。
さらに、同長官はアベノミクス導入から12年が経過し、いまやデフレ脱却が課題だった当時とは逆に、高インフレ続伸が懸念されるなど状況は大きく変化していると指摘した。
これに先立ち、8月にブルームバーグのインタビューで、「日銀が後手に回っている」と指摘し、「彼らはインフレを制御する必要がある」と述べている。
ベッセント財務長官のこうした指摘は全く正しいと思う。ただし、日銀の独立性の重要さが、日本国内からの声でなく、外国から指摘されるのは、残念なことだ。