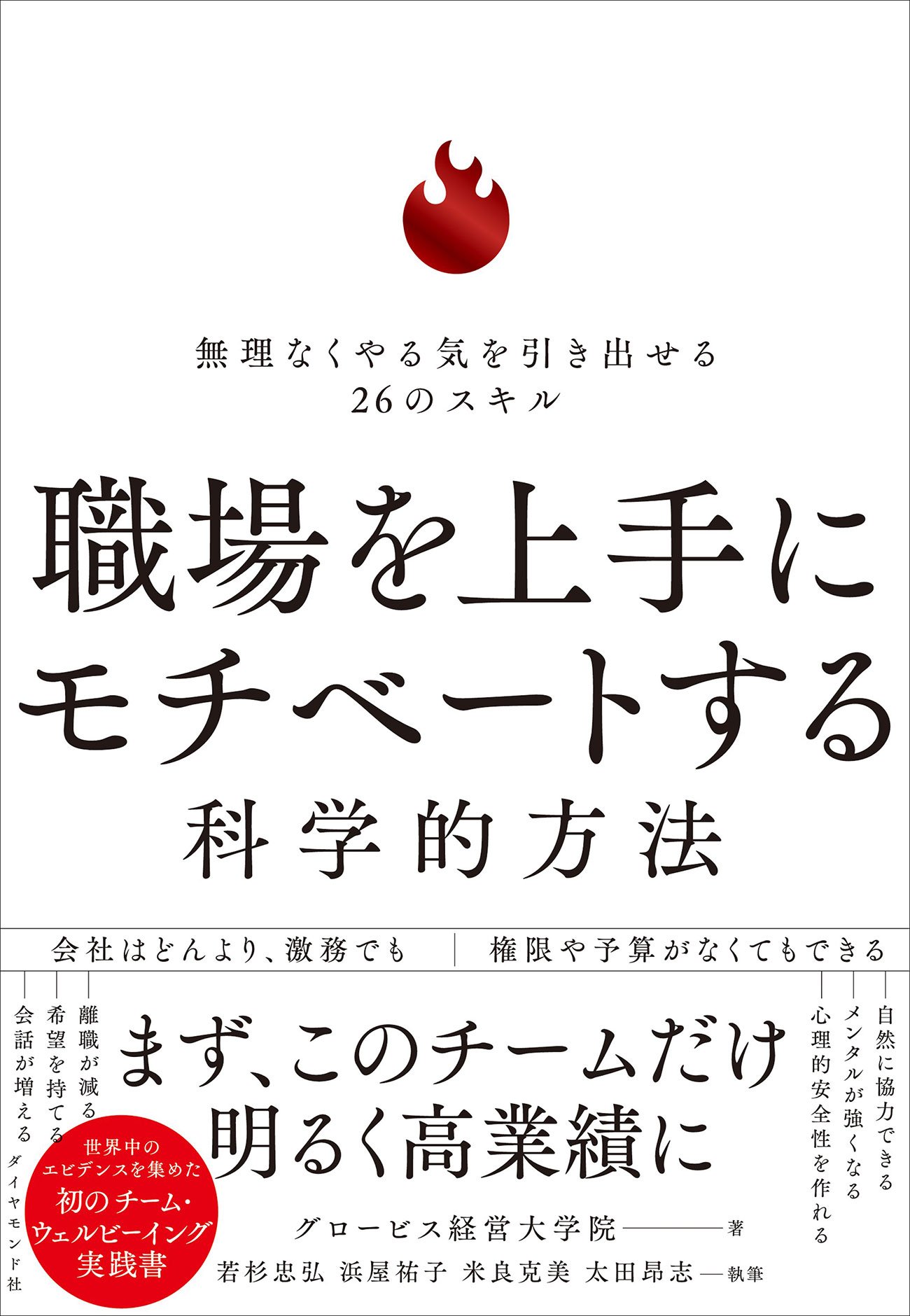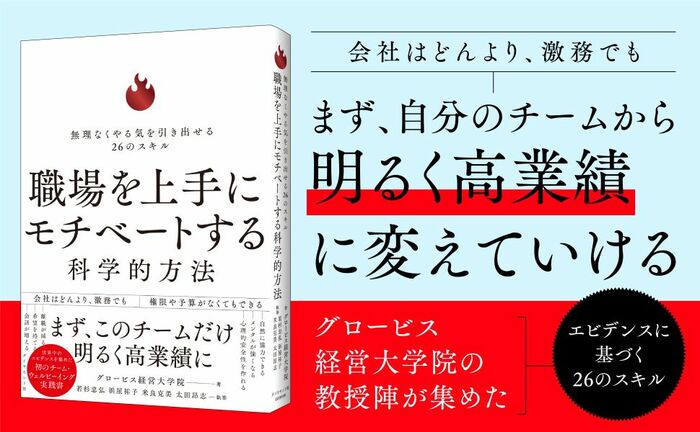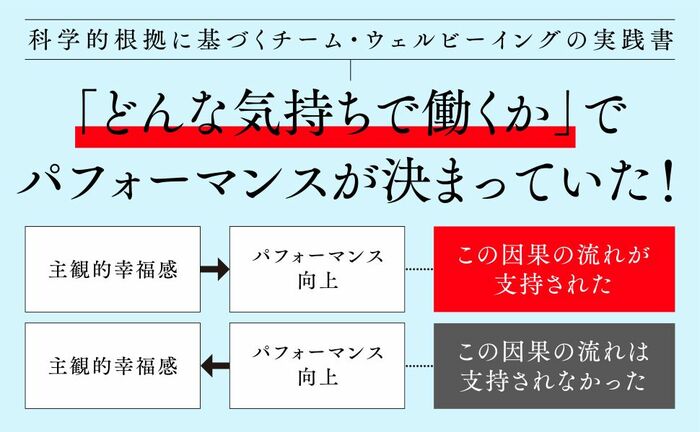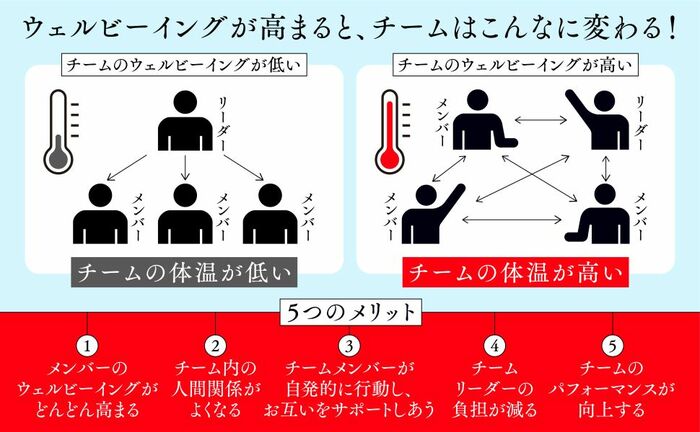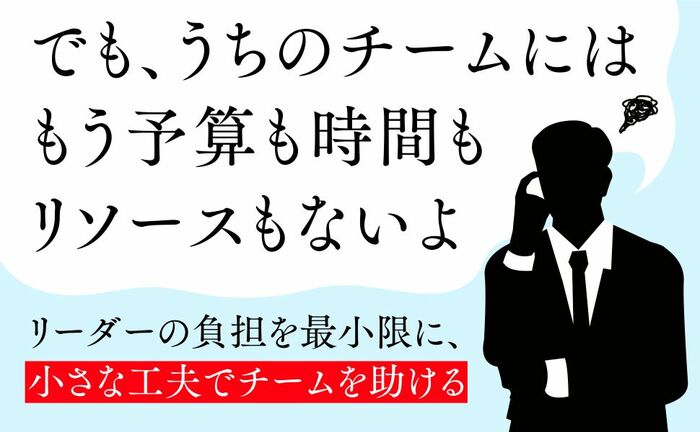休暇をめぐる多元的無知を解消する
「本当は休みたいけれど、休むと周りから仕事熱心でないと見られるのではないかと気になり、休暇を取ることをためらってしまう」という経験はありませんか。
実際には、休暇を取ることに対して誰も否定的な感情をもっていないにもかかわらず、こうした「後ろめたさ」を感じてしまうとしたら、米国の心理学者F.H.オルポートが提唱した「多元的無知」の状況にあるのかもしれません。
少し専門的になりますが、これは「集団の多くのメンバーが、自分は『この集団ではこうすべきだ』という規範を受け入れていないにもかかわらず、ほかのメンバーのほとんどがその規範を受け入れていると信じている状況」を指します。
つまり、休むのはよいことだとみんなが考えているにもかかわらず、誰もが「自分だけがそう考えていてほかの人は違う」と思い込むことで、「休むのはよくないことだ」というムードがチーム内に広まってしまうのです。
リーダーは自身の休暇取得を機に、部下に仕事を任せられる仕組みづくりを
休みを取得することに対する「多元的無知」の状態、根拠のない後ろめたさを感じている状態を打破するためには、まずは、リーダーであるあなた自身が率先して休暇を取ることです。
そして、休暇を取得するにあたっては、チームミーティングの運営や会議への出席など、普段なら自分が行うことをすべてメンバーに代行してもらえるようにお願いしましょう。休暇の前後に振り分けて自分で処理しようと考えてはいけません。
リーダーが休暇を取ることは、チーム内に「休んでかまわないのだ」というメッセージを発するとともに、メンバーに自分の仕事を任せる絶好の機会になるからです。
リーダーの仕事の一部をスムーズに任せるためには、日頃から、メンバー各人の担当業務の概要・進捗状況・相談事項などをチームミーティングの前に記録することをルーティン化しておくと役に立ちます。
また、定例のチームミーティングの目的と進行手順についても、明文化してメンバー間で共通理解をつくっておくとよいでしょう。
仕事との適度な距離感がある休暇がウェルビーイングを高める
休暇中の過ごし方について、参考にしたい知見を紹介しましょう。調査によれば、休暇中に仕事への心理的距離が遠い(仕事からしっかり離れている)ほど、メンタルヘルスが良好であるとされます。
一方、ワーク・エンゲージメントは、仕事への心理的距離が中程度(仕事から完全には離れていない)のときにもっとも良好であることがわかりました。
メンタルヘルスとワーク・エンゲージメントはともにウェルビーイングに影響を与える要素ですから、両者と仕事への心理的距離の関係を踏まえて言うと、休暇中もずっと仕事のことを気にかけるのではなく、とはいえ無理にすべてを遮断するのでもなく、「仕事とほどよく離れている」という距離感を保つことが望ましい休み方になります[4]。
休暇中に仕事に関してどうしても気になることが出てきたら、それをメモすることで「不安の外在化(いったん自分の外側に切り離す)」を行いましょう[5]。
そうすることで、頭の中で同じことを何度も考えるのを防ぎ、リラックスできるようになります。また、どうしても必要ならば「この日時にメールを確認する」と決めて休暇前に周囲に伝えておくようにします。これで休暇中も安心して過ごせます。
休暇後の同僚への感謝と共有が休暇文化を育てる
休暇を終えて出社したら、休暇中に仕事を一部肩代わりしてくれたメンバーたちに、忘れずに感謝を伝えましょう。
そのうえで、何か気づいたことがあったか尋ねてみましょう。一時的な代理であっても、進行役としてチームミーティングを運営することで仕事を見る目線が変わることも多いものです。
また、リーダーであるあなた自身が休暇中に体験したことや、それを通して得た発見、感じたことなどは、直接的に仕事に関係していなくても、あなた自身が心地よく感じられる範囲でチームメンバーに話して共有しましょう。
休暇をオープンに語るチームリーダーの行動が、休暇に対するメンバーの意識を「後ろめたさを感じつつ取得するもの」から「お互いのリフレッシュや視野の広がりにつながるもの」へと変え、休暇文化をアップデートすることにつながります。
なお、休暇にポジティブな意味づけをし、お互いに仕事を委ね合うよう推奨しても、そもそも仕事量が多すぎたり、任せられる人が誰もいないような状況では、休暇前後の期間にしわ寄せがきて、メンバーのウェルビーイングを逆に損ないかねません。
日頃から、チームメンバーの業務量を把握して調整することを忘れないようにしたいものです。
*この記事は、『職場を上手にモチベートする科学的方法――無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社刊)を再編集したものです。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/24/dl/gaikyou.pdf
[2] 島津明人(2022).『新版ワーク・エンゲイジメント』労働調査会.
[3] 塚本尚子, 野村明美(2007).「組織風土が看護師のストレッサー, バーンアウト, 離職意図に与える影響の分析」日本看護研究学会雑誌, 30(2), 2_55-2_64.
[4] 2に同じ。
[5] 2に同じ。