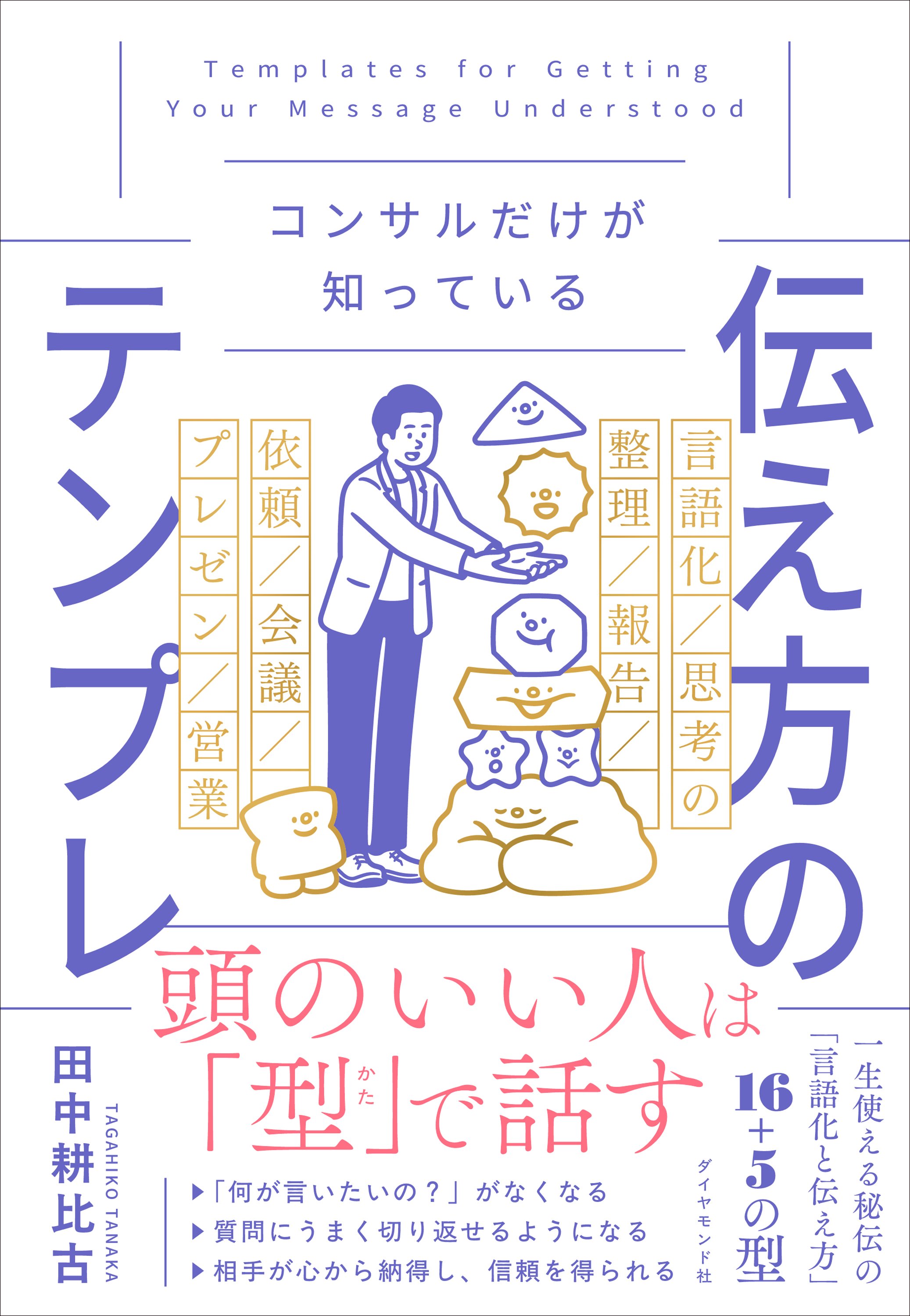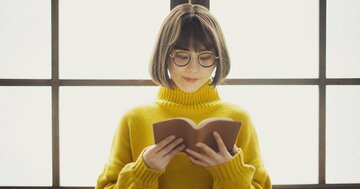ポイントを押さえて
判断してもらえる報告を目指す
それでは、どのような報告が理想的なのでしょうか。まずは具体例を見てみましょう。
A案件についてご報告します。現在、予定通り開発フェーズに入っており、進捗上の問題はありません。
現状の進捗率は60%で、想定とのズレは基本的にありません。
唯一、X工程に置いて、テストの遅れが出ていますが、リカバリ可能な範囲です。
一点、今後のリスクとして、クライアントの追加要望が入ってくる可能性があります。現時点で想定される影響範囲は軽微なのですが、ご要望の内容次第では、納期の後ろ倒しや追加費用が発生する可能性があります。
納期や費用に影響する可能性があることは、すでに先方にはお伝え済みです。
いずれにしても、早々に仕様を確定する必要がありますので、今週中に先方からのご連絡がない場合は、こちらから確認のアクションを取ります。
来週の定例打合せで、この点を議題に追加させていただく予定です。
この対応方針で問題ないか、ご意見をいただければと思います。
現状の進捗率は60%で、想定とのズレは基本的にありません。
唯一、X工程に置いて、テストの遅れが出ていますが、リカバリ可能な範囲です。
一点、今後のリスクとして、クライアントの追加要望が入ってくる可能性があります。現時点で想定される影響範囲は軽微なのですが、ご要望の内容次第では、納期の後ろ倒しや追加費用が発生する可能性があります。
納期や費用に影響する可能性があることは、すでに先方にはお伝え済みです。
いずれにしても、早々に仕様を確定する必要がありますので、今週中に先方からのご連絡がない場合は、こちらから確認のアクションを取ります。
来週の定例打合せで、この点を議題に追加させていただく予定です。
この対応方針で問題ないか、ご意見をいただければと思います。
出典『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』(ダイヤモンド社)
ポイントとしては
● 最初に「問題はない」と伝えて、安心して聞いてもらえる状況を作っている
● 60%などの定量的な情報を入れて、理解を手助けしている
● どんなリスクがあるのか、それはどれくらい重大なのか、などをわかりやすく整理し、今後の報告タイミングについて言及している
● 最後に、相手に「判断してほしいこと」を明確に伝えることで、聞き手が何をすればよいのかを明らかにしている
● 「○○システムとの接続部分」などの詳細な話を省き、まずは「現時点で伝えるべきこと」を絞り込んでいる(情報量を減らしている)
といった点を挙げることができます。
材料をただ並べるだけではダメ
「相手が食べやすい状態」にするのが大事
報告のゴールを、相手が判断できることだと捉えると、事実を全て伝えるだけでは不十分であるということは、若手社員にも理解できると思います。
ただ、もしピンとこないという若手がいた場合には、私は、料理を例に出して説明します。
事実、つまり話の材料をテーブルに並べることは報告の準備段階では、非常に重要なことです。一方、報告の場で誰かに話す際には、それをうまく料理して、お皿に盛りつける必要があります。
また、食材があるからといって、全て使えばよいというものではありません。おいしい組み合わせもあれば、あまり推奨されない組み合わせもあります。
食材のまま皿に乗せて提供する料理人はいません。同様に、報告する際には、事実を雑多に並べてもダメなのです。
しっかりと「相手が食べやすい状態」に調理し、盛り付けするように心がけるようにしましょう。