 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第105回は、入試問題を自作することの有用性について考える。
「活躍した」の定義は、どこにあるの?
東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒は、夏休みを終えて2学期の勉強をスタートさせた。東大合格請負人・桜木建二は、2人に東大の入試問題を作ってみるように提案する。
何かを勉強する時に、解答者の視点だけではなく作問者の視点になって考えることはとても有効だ。自分で問題を作成することで、単に勉強している分野の理解が深まるだけでなく、「問題として成立させるには何が必要か」という見方ができるようになるからだ。
問題として成立させるために必要な条件、その1つが「答えが1つに定まること」だ。例えば、次のような問題を考えてみよう。「16世紀に活躍した尾張国の戦国武将は誰か?」おそらく、多くの人が「織田信長」と答えるだろう。
ただ、この情報だけだと「豊臣秀吉」を×にすることができない。では、次のように問題文を変えてみよう。「16世紀に活躍した尾張国の戦国武将で、1582年に本能寺の変で亡くなったのは誰か?」
これだと、豊臣秀吉は明確に×だ。ただ、織田信長の息子の織田信忠はどうだろうか。彼は信長と共に本能寺の変で亡くなっている。
こうなってくると、問題文をより深く考えなくてはいけない。15世紀と16世紀の両方を生きた人物は正解なのか? 「活躍した」の定義はなんだろうか?「尾張国の」とあるけど、生まれと育ちが違う場合はどうするの?「戦国武将」と「戦国大名」の違いは?
とても短い問題文だが、たくさんのポイントがある。
作問トレーニングは日常にも役立つ
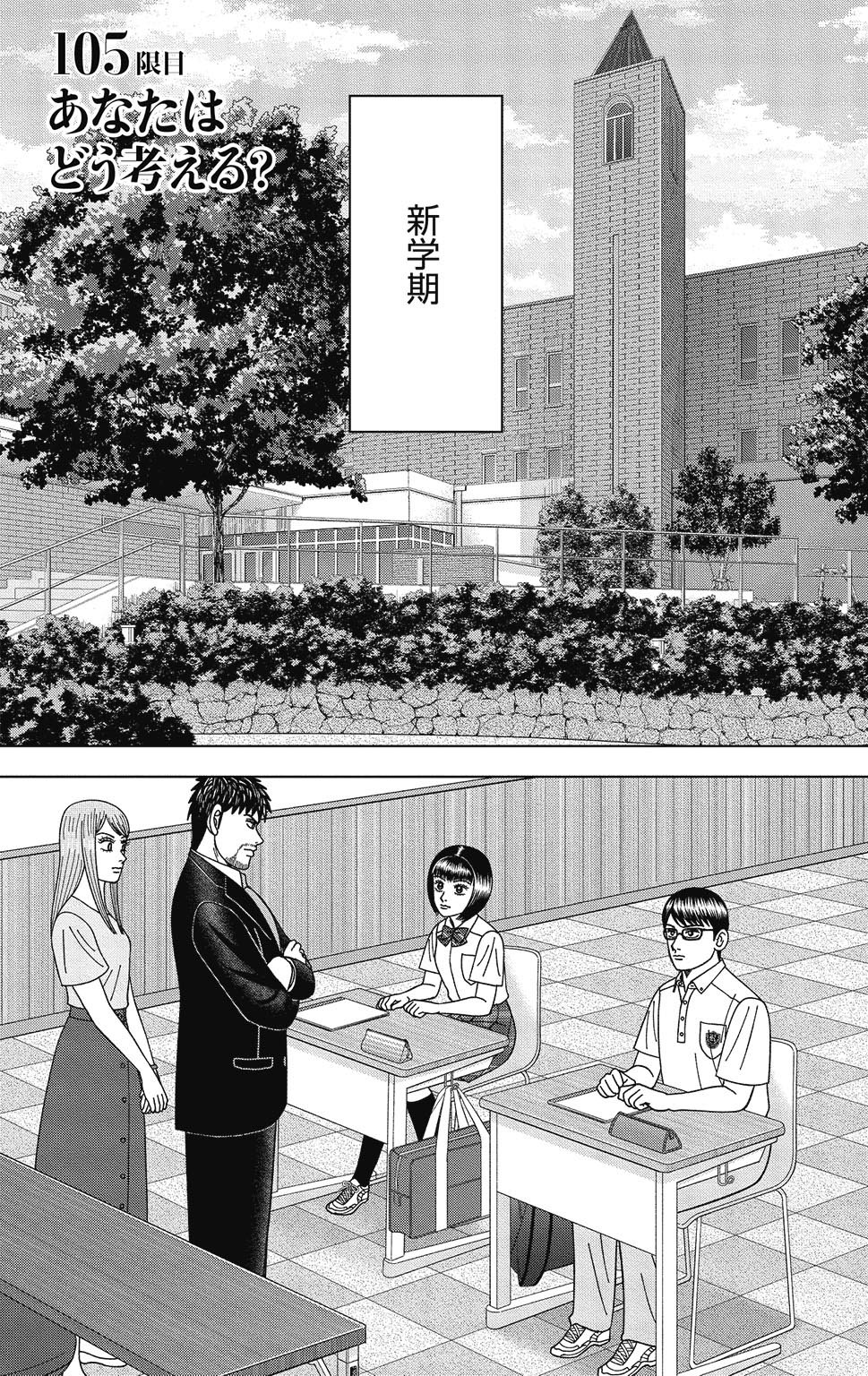 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
自分で問題を作ることで、考えるポイントに気づきやすくなる。「あえてこの言葉を使っているということは、AではなくBと答えてほしいのだろう」「○○という用語と××という用語にはこのような厳密な違いがあるのか」といった思考ができるようになる。
特に数学の問題では、答えが1つに定まる条件が論理的に定まっている。作問者の視点を取り入れることで、どこまでが前提条件で何を求めればいいのかが理解しやすくなる。
さらに数学では、1つの問題に複数の小問がつくことがある。その際に、(1)の答えや考え方が(2)のヒントになっている、いわゆる「誘導」と呼ばれる形式をとることが多い。
蛇足に見える小問があることで、次の問題が解きやすくなっていることがある。誘導を含む問題を作ることで、1つ1つの小問にとらわれない立体的な見方ができるようになる。
とはいえ、1つの問題から導かれる答えは1つだが、1つの答えを導く問題は無数にある。「何が正解なの?」と悩んでしまい、1人では取り組みづらいと思われるかもしれない。
だが、例えば「問題出してみてよ」と声をかけたり、友達同士で自分で作った質問を出し合ったりするだけでも有効だ。私の母校では、テストの前に予想問題を作る取り組みがあった。
問題を作ることは、テストや受験の対策に役立つだけではない。「どこまでが分かっていて、どこからが分からないのか」「ある事象を構成する要素は何なのか」という抽象的な思考のトレーニングにもなる。これらの思考が、日常生活に役立つことは言うまでもないだろう。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







