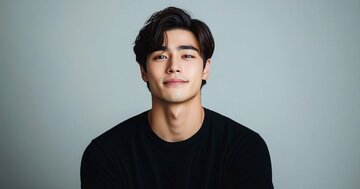AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。
そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか!」「値段の100倍の価値はある!」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って“アイデアのヒント”を得る「聞き方」
AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。
ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問(プロンプト)が適切でないことがほとんどなのです。
たとえば、アイデアを考えるヒントを得たいときにおすすめなのが、技法その51「重要な要素」です。
こちらが、そのプロンプトです。
以下のようなターゲットユーザーが求めるもっとも重要な要素(あるいは機能)は何ですか?
〈顧客の属性や特性などを記入〉
商品やサービスを改善・改良する方法を考える際、「人」の価値観や深層心理を探り、それを起点にすることも多いですが、その際に気をつけるべきことがあります。
「既存の魅力」を損ねてしまうことです。
ですが残念ながら、私たちは他人に100%なりきることはできません。生活を共にしている家族であっても、わかり合えないことだらけです。他人が重要視している価値観は想像するしかありません。
そこで、人の心の奥底に迫る作業を、AIで「エイヤッ」とやってしまうのが技法「重要な要素」です。ユーザーの属性などは見えていて、彼らの本音に迫りたいときはもちろん、自分がよく知らない物事やユーザーに関するアイデアを考えるときにも有効な技法です。
「コインランドリー」のユーザーにとって重要なポイントを探ってみよう
では、実践してみましょう。
普段は無意識に接している価値は、なくなって初めてその大切さに気づいたりします。よって、コモディティ化した商品やサービスの価値がどこにあるのかを可視化したい場合にも、むしろ、そういった場合こそ、この技法は役立ちます。
以下のようなターゲットユーザーが求めるもっとも重要な要素(あるいは機能)は何ですか?
〈コインランドリーのユーザー〉
「コインランドリーの価値なんて、考えるまでもないでしょ」と思うなかれ。私にもある程度のイメージがありますが、先入観はさて置いて、改めてAIに言語化してもらいましょう。ちなみに私の肌感では、最近は無人のコインランドリーが全国で増えつつあるように思います。その理由などもわかるかもしれません。