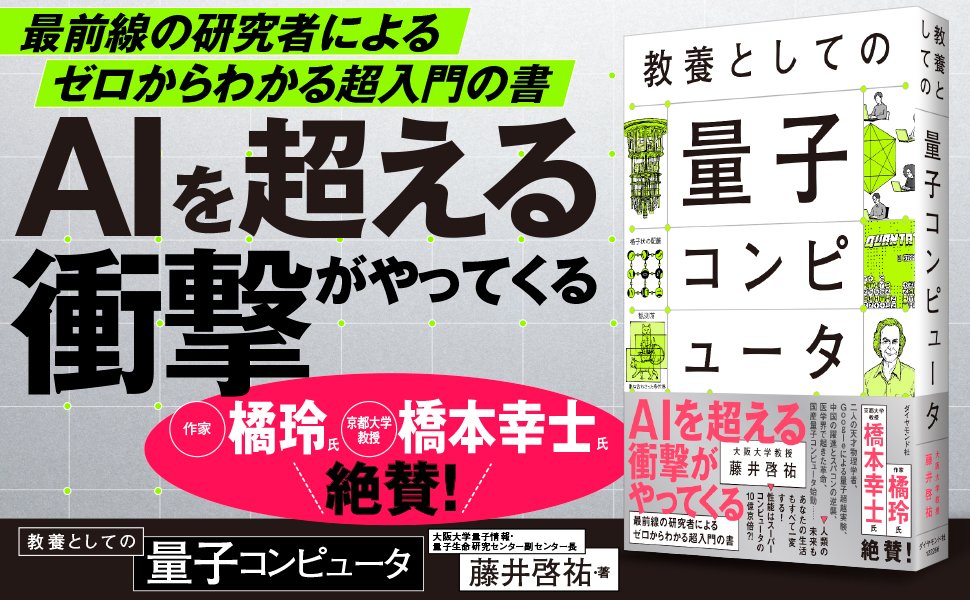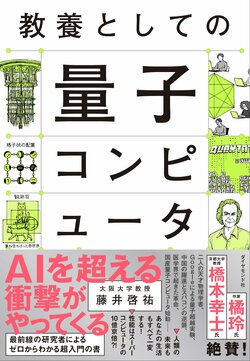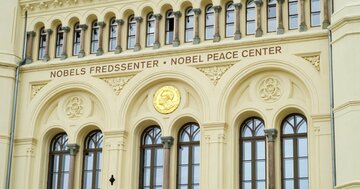量子コンピュータが私たちの未来を変える日は実はすぐそこまで来ている。
そんな今だからこそ、量子コンピュータについて知ることには大きな意味がある。単なる専門技術ではなく、これからの世界を理解し、自らの立場でどう関わるかを考えるための「新しい教養」だ。
『教養としての量子コンピュータ』では、最前線で研究を牽引する大阪大学教授の藤井啓祐氏が、物理学、情報科学、ビジネスの視点から、量子コンピュータをわかりやすく、かつ面白く伝えている。今回は量子コンピュータのはじまりについて抜粋してお届けする。
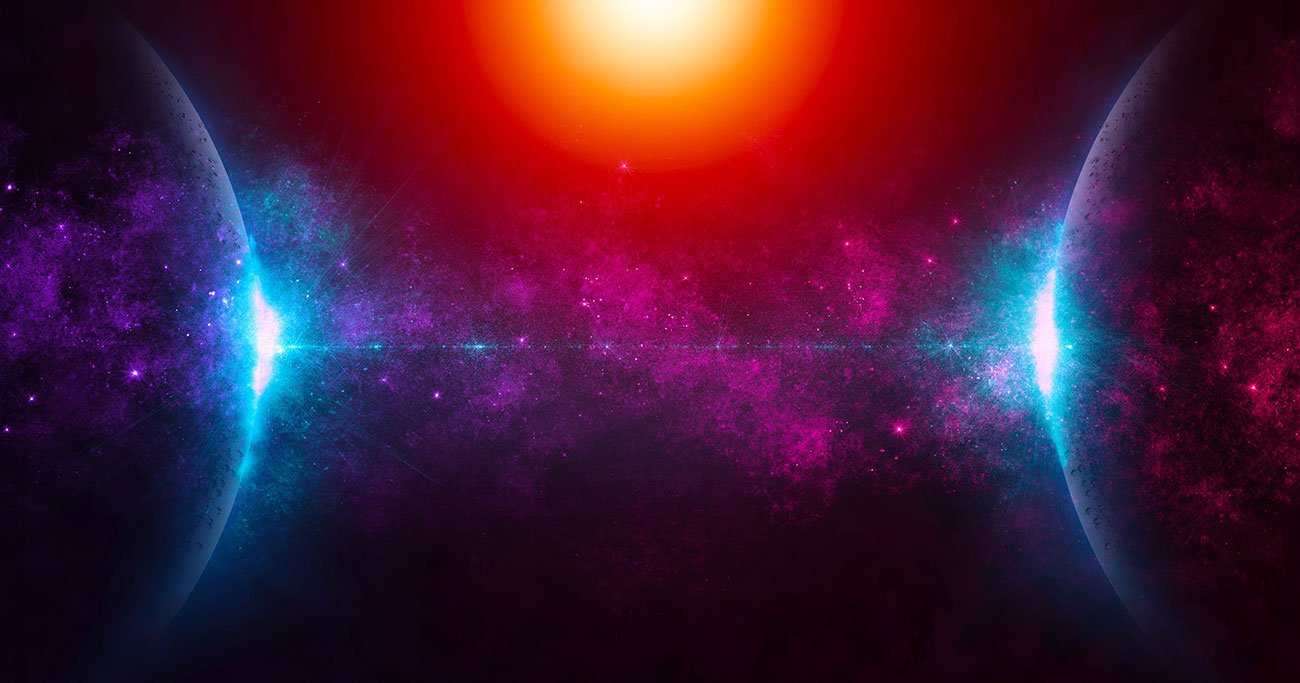 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
情報を保存できるコンピュータ
ベネットは、コンピュータが情報を処理する際、なぜエネルギーを使って熱が発生するのか、それが物理法則でどう決まっているのかを研究していた。
ベネットの同僚であったロルフ・ランダウアは1960年代、情報を消去する際には必ずエネルギーを消費するという「情報消去の原理」を提唱していた。
つまり、エネルギー消費をせず情報処理ができるコンピュータを作りたければ、情報を消去せず、いつでも元に戻せる状態で処理をするコンピュータを作ればいいということになる。
このような研究を皮切りに、「情報は物理である」という哲学が徐々に広まっていった。
情報も物理である以上、情報処理の究極的な限界を知るためには、それが従う物理法則を知る必要がある。
伝説の「計算の物理学」
このような流れに乗る形で開催されたのが1981年にマサチューセッツ工科大学で開催された「計算の物理学」という会議だ。
現在では伝説的な会議として語り継がれるこの集まりには、いまの量子コンピュータの礎を築いた面々が参加した。
その一人である素粒子物理学でノーベル物理学賞を受賞したリチャード・ファインマンは、「自然界は古典力学では動いていない。したがって、自然界を効率よくシミュレーションしたければ、コンピュータも古典力学ではなく、量子力学の原理で作らないといけない」と指摘し、量子コンピュータの概念を提唱した。
また、ポール・ベニオフはコンピュータにおける発熱の問題を回避するために、一九七〇年代に量子力学に基づくコンピュータの概念をいち早く考案していた。
寒い日のコーヒーは冷めるだけ
私たちの日常スケールの世界では、一度時間がたつと元には戻せない、不可逆な現象がある。
寒い日に熱いコーヒーを置いておくと、冷めることはあっても、逆に温まることは決して起きない。
このため、コーヒーを元どおりに温めるためにはエネルギーが必要になる。
これを説明するのが熱力学だ。
一方で、ミクロな世界を支配する量子力学は、状態を元どおりに戻すことが常に可能である。
この量子力学の可逆性を使えば、計算の途中で情報を消去せずに、つまりエネルギーを消費しない、可逆コンピュータが作れるとベニオフは考えたのだ。
しかし当時は、量子コンピュータが新たな原理に基づく革新的なコンピュータになるとは考えられておらず、古典コンピュータで解けない問題を解けるとも思われていなかった。
物理は情報から生まれる「計算の物理学」には他にも、世界初、プログラム内蔵型のコンピュータを第二次世界大戦中のドイツで開発したコンラート・ツーゼや、いまもインターネットで使われている暗号方式「RSA暗号」を考案した一人であるレオナルド・エーデルマンなど、物理とコンピュータ科学にまたがった錚々たるメンバーが参加していたことになる。
パラレルワールド理論
そのなかに「世界は情報からできている(It from bit)」という考え方を提唱したアメリカの物理学者ジョン・ホイーラーもいた。
「情報は物理である」とは真逆で、物理学の根底には情報理論があるという考え方だ。
最近では、「世界は量子情報からできている(It from Qubit)」という考え方へと進化している。
この考えによると、私たちが住んでいる世界の時空や物質はすべて量子情報からできていることになる。
この頃、ホイーラーと交流があった学生のデイヴィッド・ドイッチュが、一九八五年に量子コンピュータの原型、量子チューリングマシンを提唱した。
ドイッチュは、ベニオフの量子力学に基づく可逆コンピュータの理論に触れて、量子力学の性質を使えば、古典コンピュータを超えたもっとすごい計算ができると考えたのだ。
同じくホイーラーの元で学んだヒュー・エヴェレット三世は、量子力学における観測問題をパラレルワールド(並行宇宙)によって説明する多世界解釈を提唱した。
この考え方も、量子コンピュータ研究の進展に影響を与えることとなった。
(本稿は『教養としての量子コンピュータ』から一部抜粋・編集したものです。)