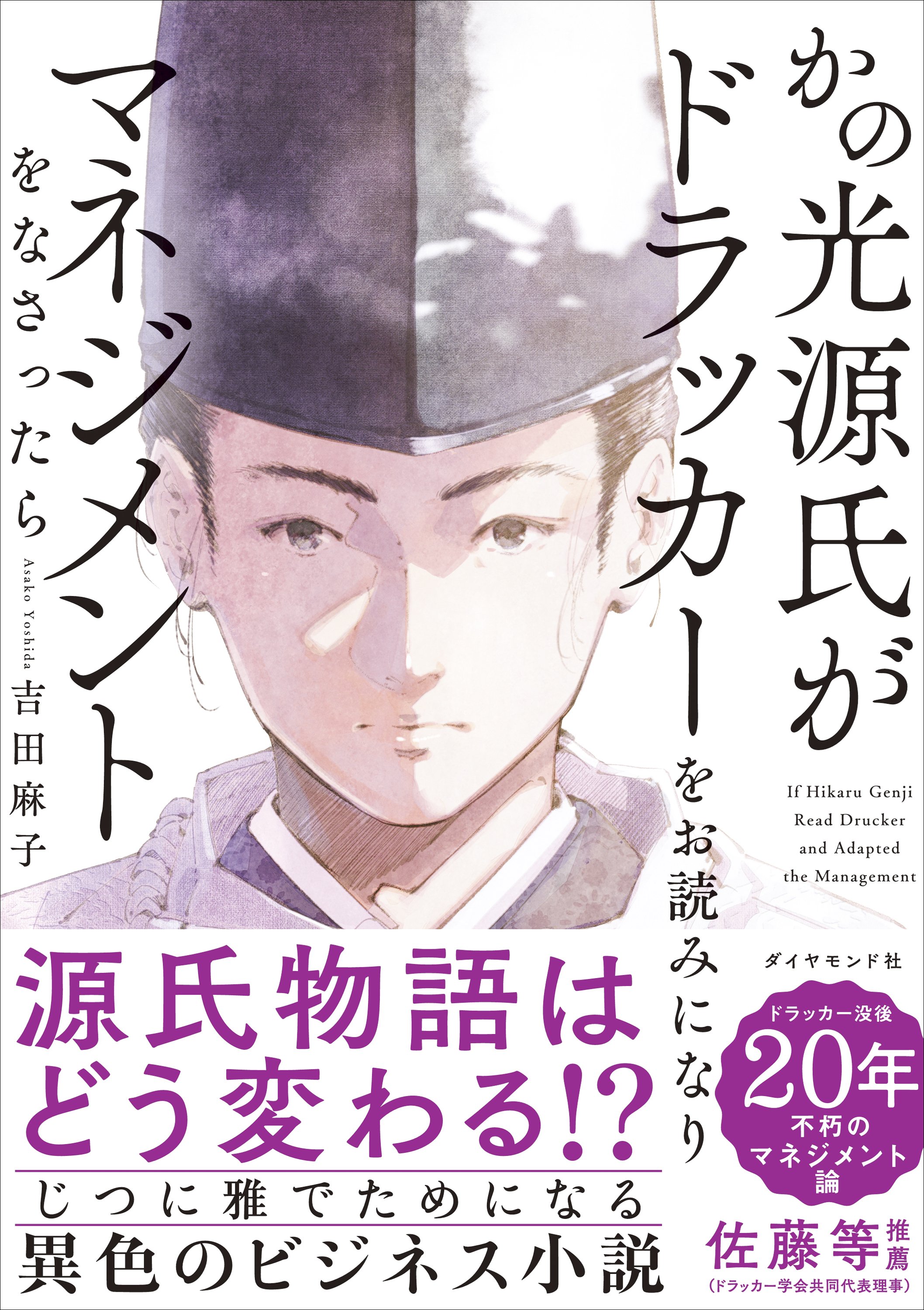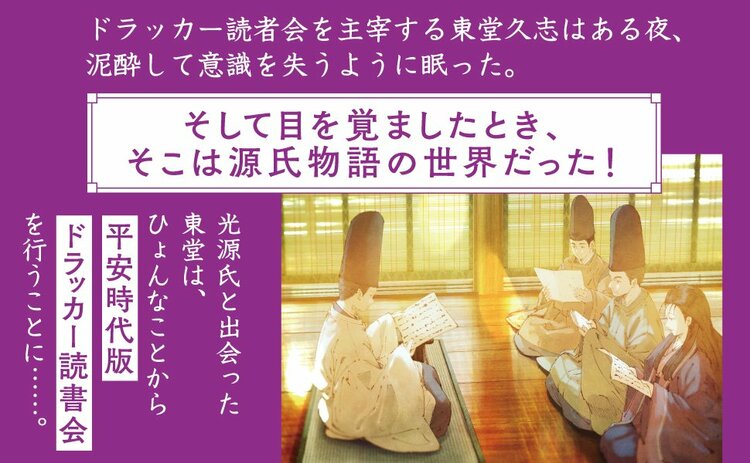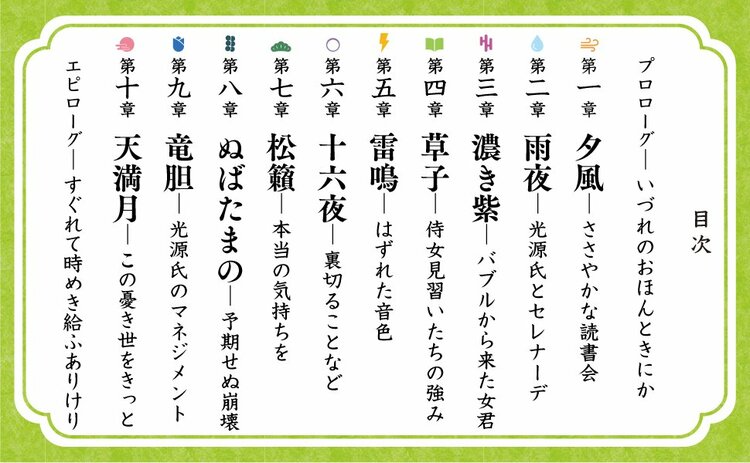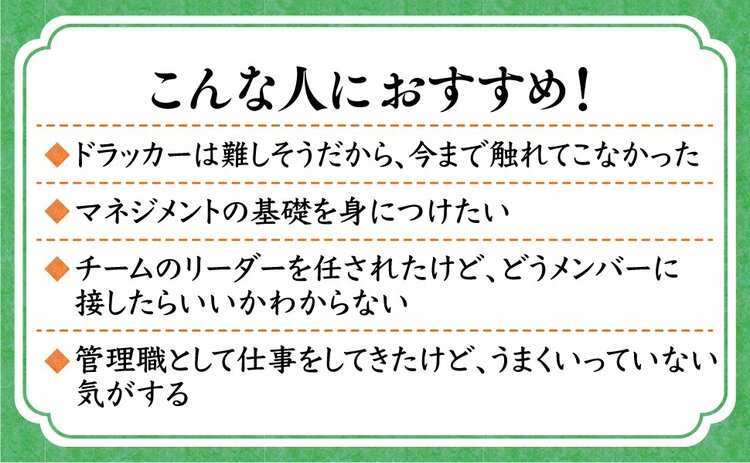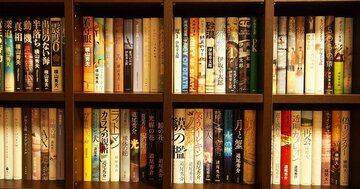「経営学の父」と呼ばれるのは誰か、あなたは即答できますか?
その名は――ピーター・ドラッカー。
彼が残した言葉は、時代を越えて世界中の経営者やビジネスパーソンの指針となっています。なぜ没後20年近く経った今も、ドラッカーは読み継がれ続けるのか。
『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』の著者である吉田麻子氏に、現代にこそ響くドラッカーのメッセージを伺いました。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
リーダーが「絶対に」やるべきこと
――リーダーになる人が「絶対にやるべきこと」はありますか?
吉田麻子(以下、吉田):ドラッカーは著作『マネジメント』でこういっています。
前回の記事(「人が去っていくリーダー」の特徴・ワースト1)で解説したように、リーダーに必要なのはカリスマ性や煽動ではないのです。
では具体的に、ドラッカーはリーダーシップとはどのような仕事であるとしているのでしょうか。
『マネジメント』ではこう続きます。
成果中心の精神とは
吉田:この文章は『マネジメント』第36章「成果中心の精神」の中でリーダーシップについて書かれている部分からの引用です。
この章でドラッカーは、「成果中心の精神とは、投入した以上のものを生み出すことである。それはエネルギーを創造することである。そのようなことは機械では起こらない。エネルギーは、保存はできても創造はできない。投入した以上のものを得られるのは、精神の世界においてだけである」といっています。
リーダーが日々確認すべき三つの原則
吉田:組織の焦点を成果に合わせ、その成果の基準を高くもち、一人ひとりの強みを引き出し、他の者の助けとする――といった“精神”に基づき、
① 行動と責任についての厳格な原則
② 成果についての高度の基準
③ 個としての人と仕事に対する敬意
この3つを日々のリーダーとしての仕事の中で確認していくことが重要です。
つまり、リーダーがやったほうがよいことは
・ 自分はリーダーとしての行動に責任をもち、一貫性があるか
・ 組織のよりよい成果を求めているか
・ 一人ひとりのメンバーに対する敬意、仕事に対する敬意をもっているか
と自らに日々問うところから始まるのではないでしょうか。
そして何より、リーダー自身がその問いにまっすぐ向き合おうとするとき、変化が生まれはじめるのだと思います。
真摯さとは、声高ではなく、日々の一つひとつの行動に宿る、もっとも静かで揺るがないリーダーシップといえます。