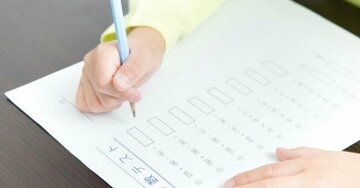そこで気になる学校の資料をもらい、話をしてみて「この学校は合わないな」と思ったら、その瞬間に切ってしまって問題ありません。
そのときに「現地に行ったほうがいいかな」って思う学校もあるでしょうし、その逆で1回で「バイバイ!」っていう学校もあって当然だと思うんですよ。
だって、行った瞬間に「合わない」と思う学校がその後、併願校になる確率はほぼないですからね。 行った瞬間「ダメな学校」と「キープ校」…つまり、あんまりすごいとは思わないけど「まあ、ここでもいいかな」という学校、そして「絶対行きたい!」の○△✕の3段階ぐらいで評価してみてください。
○の学校ばかりがたくさん残っているのであれば、もうキープ校もバイバイ!でいいと思うんですよね。 ただ、○があまりに少なかったら、キープも含めてもう1回行ってみればいいと思いますよ。
説明会での印象は良かったのに、実際に行事に参加してみるとつまらなかった。逆に説明会がいま一つで良くも悪くもないって学校でも、いざ行事に行ってみると子どもたちが元気で楽しそうだったとか、印象ひとつで見方が変わりますからね。
いずれにせよ、親がまずきちんと計画的に行動することがとても大事です。
6年生になったら、モチベーションアップの意味で行く志望順位の高い学校の運動会や文化祭、あるいは直前期の入試問題体験会など以外は子どもが学校見学に出向くのは時間的にほぼ不可能。となると、ある程度、親の中で優先順位をつけていき、子どもにどこを見せるかっていうのを計画的にやっていったほうがいいと思います。
子どもをこの学校に通わせたいと思ったら、低学年のうちからその学校にアクセスする機会、しかも、なるべく学校の良さが伝わりやすい、楽しげな行事にアクセスする機会を増やしていくというのがすごく大事なのかな、というふうに思います。クラブ活動体験会や文化祭に行くと、やっぱり、子どもは楽しい。「ここに行きたい!」という強い気持ちがなければ中学受験は頑張れないものなのです。
――憧れの学校を持つことが大事ってことでしょうか?