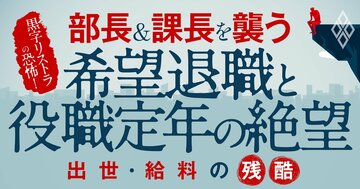料理人の世界は、学歴も経験も関係ない。上司に「やれ」と言われたとき、その場できっちり「やれる」ことを示せれば、この世界では認められ、さらに重要な仕事を任せてもらえるようになる。
僕は寝る間も惜しんで励み、急速に腕を上げ、入社3年目には、ホテルのメインダイニングのワゴンサービスという花形ポジションにまで上り詰めていた。
上り詰めれば、次はもっと別の景色が見たくなる。
調子に乗っていい気になっていた部分はもちろんあるのだが、そこで終わるつもりは最初からなかったようにも思う。僕は次の場所を強く求めていた。
そんなとき、“料理の神様”の話を耳にした。その人は、東京の帝国ホテルの村上信夫総料理長。日本中の料理人の頂点に立つ“神様”だという。その話を聞いたとたん、僕は村上総料理長に会いたくてたまらなくなった。
よし、決めた!僕は神様の弟子になる。
それからは熱にうかされたようにそのことばかりを思い続け、周囲に思いの丈をぶちまけた。「相手にされるはずがない」「いい気になるな」「あきらめろ」――いさめる言葉、引き留める言葉を山ほど浴びたが、気持ちは強まるばかりだ。
あるとき、僕をパートから社員に引き上げてくれた恩人である青木靖男料理課長に呼ばれ、当時の札幌グランドホテル総料理長・斉藤慶一シェフのところへ連れて行かれた。
「三國、どうしても行くのか」
「どうしても行きたいです」
「わかった。これを持っていきなさい」
村上総料理長と旧知の仲だった斉藤総料理長は紹介状を書いてくださったのだった。
20歳の誕生日に味わった
人生初の挫折
紹介状を握りしめて単身上京し、帝国ホテルの前に立ったとき、僕は希望にあふれる18歳だった。帝国ホテルには500人を超える料理人がいて、その指揮を執るのが“料理の神様”村上総料理長である。僕はその人のもとで働くのだ。
だが、現実はそんなに甘くなかった。折からのオイルショックのあおりで、社員の採用枠はなく、洗い場のパートタイマーしか空きがなかったのである。
札幌グランドホテルでワゴンサービスを担当するところまで上り詰めたのに、鍋洗いに逆戻りだ。