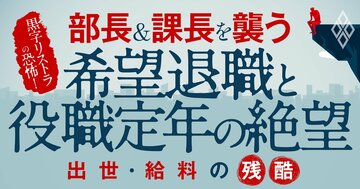それでも1年目は、いつか社員にしてもらえる日を夢見て、頑張ることができた。誰よりも速く、誰よりもたくさん、誰よりもきれいに鍋を洗い続けた。村上シェフは、NHKの料理番組「きょうの料理」に出ておられたので、収録があるときには、食材の準備や仕込みの手伝いも買って出た。
“神様”の周りをうろちょろする僕が目障りだったのだろう。「洗い場の若造のくせに」「三國は生意気だ」そんな声が聞こえてきたが、誰になんと言われたってかまわない。僕は村上シェフだけを追いかけていた。
しかし、2年目に入るとさすがに精神的にきつくなってくる。
憧れの場所・帝国ホテルにはいるものの、僕は洗い場の雑用係、まだコックですらないのだ。あのまま札幌にいればよかったのか。判断を誤ってしまったのではないか。頑張れば道は拓けると思ってやってきたけれど、世の中には自分の力ではどうにもならないこともある、ということをじわじわと思い知らされる毎日だった。
増毛に帰ろう――8月、20歳の誕生日を洗い場で迎えた僕はそう決めた。今さら札幌には戻れない。厳冬の増毛の海の光景や子ども時代のひもじさが蘇る。だが、出口が見えないままここにいるのはもう限界だ。戻れる場所は故郷しかなかった。
今思えば、あれが人生で初めての挫折だった。
洗い場の僕を
ずっと見ていてくれた“神様”
そんなとき、突然村上シェフから呼び出しがかかった。いよいよ解雇通告かと腹をくくった僕は、総料理長室へと向かう。これまでのお礼をしっかり述べて、きちんと辞めよう。部屋に入り、シェフの前に立つ。
「三國君、君をスイスの日本大使館の料理人に推薦しました。年明けからジュネーブへ行きなさい」
青天の霹靂とはこのことである。大使専属の料理人になることが、どれだけすごいことなのか、どんな仕事をするのか、この時点で僕にはまったくわかっていなかった。だが、「君に決めました」「行きなさい」という村上シェフの断固とした言葉には、疑問を差し挟む余地もなく「わかりました」と答えるのが精一杯。
しかし、なんで僕なんだ?