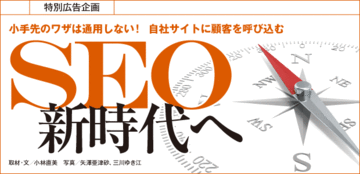広告企画
「アベノミクス」による円安や株高を受け、輸出、消費が伸びるなど、景気に明るさが見えてきている。これまでは、コスト削減で後回しにされてきた企業の設備投資が、本格回復へ向かう期待も高まっている。しかし、オフィス環境への投資は、なおざりにされている場合が多いのではないだろうか。オフィスの環境整備は従業員のモチベーションやモラールを上げることで企業業績に直結するだけでなく、優秀な人材の確保、ブランディングにも不可欠だ。第5の経営資源といわれる「ファシリティ」への戦略的な取り組みが企業の優勝劣敗の鍵を握っている。

最重要のライフラインの一つとして、わが国では公営で始まった上下水道システムだが、世界ではビジネスとして捉えられている。安心・安全な水を各所に届け、排水を回収して、環境負荷をかけずに自然に返す。このサイクルを持続させ、生活環境の向上と経済成長をサポートするビジネスである。新興国がインフラ整備を進める一方で、先進国は設備老朽化に直面。水ビジネスは新たな局面を迎えている。

家族のライフスタイルが変われば、求める住まいの形も変わってくる。日本の住宅の性能は、年々進化し続けているが、ハードの追求に加え、ソフト面の機能にも注目して選びたい。「夫婦で仕事、育児、暮らしをシェアする」ことを提案している、ワーク・ライフバランス代表の小室淑恵氏に、これからの住まい選びについて聞いた。
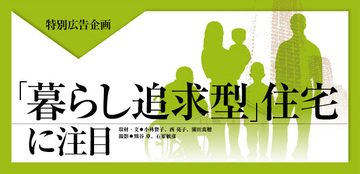
いずれ本格化する採用難の時代に優秀な人材をどう確保し、つなぎ止めるべきか。コストを最小限に抑えつつ、社員のやる気や帰属意識を最大化する人事制度のあり方が問われている。
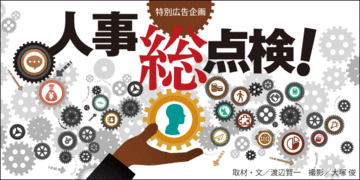
私学に比べ数の少ない国公立大学は、その魅力に触れる機会も多くない。進路選択に際しての着目点を、河合塾の近藤治氏に聞いた。
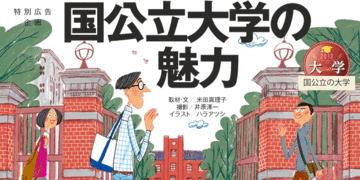
再来年の税制改正とともに、相続税の申告や納税を余儀なくされる家族が大幅に増えることが見込まれている。だが、生前からきちんと対策を打っておけば、資産評価額を抑えて納税を回避することも可能だ。その決め手となるのが不動産活用である。
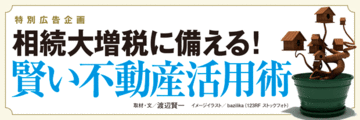
仕事と家族に重い責任を負うビジネスパーソンにとって健康管理は基本中の基本。体調に気を配ったり、年1回健康診断を受けて生活習慣病の予防や疾患の早期発見に努めているだろう。しかしそれだけでは万全の健康管理とはいえない──。
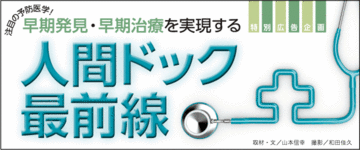
クラウド型グループウエアで組織の活性化を果たした企業が増えている。クラウドとモバイル端末の普及を受けて、コミュニケーションや情報共有の環境を実現するグループウエアはますます使いやすいものになった。どのようなビジネス効果が期待できるのだろうか。

首都圏の受験者動向を見ると、学校間格差が生じてきている。大学合格実績に対するシビアな親の意識が働いているからだ。中高の6年間で、本当に子どもの能力を伸ばしてくれる学校はどこなのか。入りやすくて「お得」な学校を見分けるためのヒントを探してみよう。

グローバル化の急速な進展は、社会で必要とされる人材にも変化をもたらした。一握りのエリートだけではなく、多くの社会人にグローバル人材としての素養が求められるようになったのだ。日本人としてのアイデンティティを確立し、国内外で多様な背景を持った人々と共に生きていく。そんな力を養成する大学に、今、注目が集まっている。
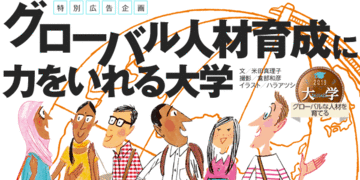
国内の企業立地動向も、これまでの政府の各種支援策の効果もあって、厳しい中にもやや上向きの兆しが見え始めている。誘致活動では、内外企業の立地戦略を的確に捉え、技術力や人材の高度化を進めて、立地企業のイノベーションを支援する体制づくりが求められる。

身近になった電子マネーをはじめ、決済サービスの進化が目ざましい。「便利な支払い機能」にとどまらず、マーケティングツールとしての役割など新たな可能性に注目が集まる。
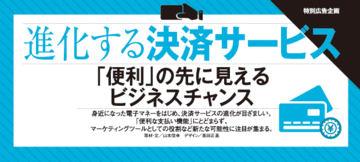
高齢者向けの住まいの不足が問題となる中、政府が供給促進を図っているのが「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」だ。注目が高まるサ高住とはどのようなものなのか、施設との違いは。
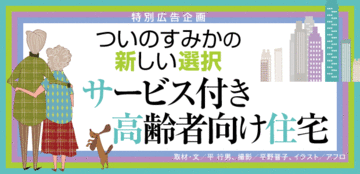
景気回復の兆しが見えつつあるものの、大学新卒者の就職はまだ厳しい局面が続きそうだ。そうした中で、早期のキャリア教育による学生の意識向上やインターンシップなどの活用によって社会の実際を知るなどのプログラム強化を進める大学が増えた。これらの取り組みに対し、学生はもちろんのこと、企業側からの評価も高まっている。

マンションの大規模修繕は、建物の経年劣化に対応し、分譲時の水準まで「戻す」作業だ。さらに、陳腐化した建物性能を「上げる」改良作業も欠かせない。2つを同時に行うバリューアップ改修が今、大きな注目を集めている。
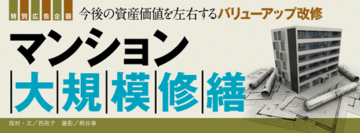
今後数十年内に起こると想定されている巨大地震、東海、東南海、南海、首都直下などによる地震被害は甚大で、被害額は国家予算をはるかに超える額になるという。東京大学生産技術研究所の目黒公郎教授に、地震防災対策の秘訣を聞いた。

論理的な考察力や分析力、実験における作業の協調性、チーム研究におけるリーダーシップの資質などが育成されることから、自然科学にとどまらず、広い分野での活躍が期待されている理工系の人材。理工系人気の背景と学生たちを支える環境について、日本物理学会 キャリア支援センター長である栗本猛教授に聞いた。
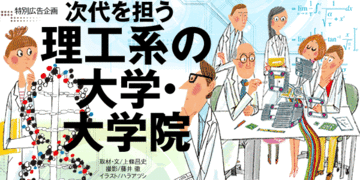
電力消費を抑える「省エネ」から、電気を創る「創エネ」、あるいは貯める「蓄エネ」へ。今、企業や家庭でのエネルギー対策は大きな転換点を迎えている。再生可能エネルギーの代表格、太陽光発電では普及の拡大と共に技術者の育成が、また蓄電池の分野では安全性確保に向けた技術的課題が大きなテーマとなっている。電力を賢く使う「スマート化時代」の課題と今後の方向性をレポートする。
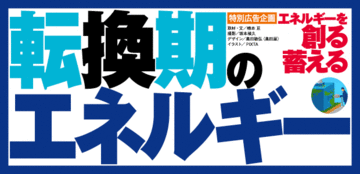
成功している製造業の共通項は、販路をしっかりと確立していて、ブランド力があることだ。このブランド力は、技術力と言い換えてもよいだろう。日本の中小企業の生き残りは、大量生産品ではなく、技術力を背景に高く売れるものを目指すことにある。
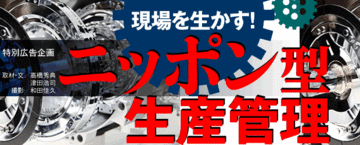
企業サイトを検索で上位表示に導く「SEO」の考え方に根本的な転換が求められている。自動生成コンテンツや隠しリンク、不適切な外部リンクといった企業側の対応が、Googleのガイドライン違反警告を受け、検索表示順位を落とす事例が続出。従来のSEO手法はもはや通用しなくなっている。SEO専門企業として高い実績を誇るウィルゲートの吉岡諒氏に新時代のSEOのあり方を聞いた。