ダイヤモンド・オンラインplus
循環型社会構築に必要なのは「人と人のつながり、場の形成だ」と説くのは、立教大学・見山謙一郎特任准教授。ネットワークを結びながら発展する環境対策「日本型モデル」へのアプローチを聞いた。

受験生の大学選びの基準が変わりつつある。偏差値だけではなく、その大学らしい特色、つまりブランドに注目し始めているのだ。各大学も多様な取り組みで応えている。

今、震災という国難にも襲われ、日本は大きな変革を迫られている。この試練に日本企業はどう立ち向かうべきなのか――。長年、経営者として「変革」に携わってきた、NTTデータの山下徹社長に話を聞いた。

クラウドサービス「IIJ GIO(ジオ)」を提供するIIJでは、自社システムと同様のIT環境で利用できるクラウド基盤を提供。節電対策とBCPの「一石二鳥」を提案する。

企業間取引(B2B)を支援するグローバルなビジネス基盤を提供しているGXS。企業は、クラウド上のB2B基盤に接続して国内外のさまざまな取引先とシームレスにデータを交換でき、国際競争力の強化に加え、事業継続性の獲得が可能になる。

東日本大震災後、BCP(事業継続計画)見直しや節電対策が急務になるなか、ネットワークを介してITリソース(ハード、ソフト)を利用できるクラウドの有用性が注目されている。その背景を探る。
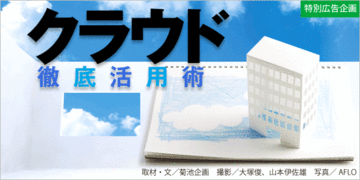
インターネットを舞台に、誹謗中傷のようなネガティブ情報が拡散し、企業に不利益をもたらすこともある。こうした事態を放置すれば、損失は増えるばかり。そんなときのための対策を提供している。

日本のさまざまな組織が今、リスクマネジメントの再考を求められている。複雑化する社会は、その一方で脆さも内包している。そんな現実を直視し、新しいリスクマネジメントを構築する必要がある。

首都圏・関西圏を中心に展開する葬儀会社を傘下に、上場企業として業界をリードする燦ホールディングス株式会社。葬儀を取り巻く現状と今後について、同社および株式会社公益社の代表取締役社長・古内耕太郎氏が語った。

コモディティ化が進む市場のなかで今、新業態の創造は可能なのか?新たな成長機会をつかみ、新業態への挑戦の成功確率を高める、MDBDの方法論を紹介する。

日立情報システムズは、VMware製品を用いた「おてがる仮想化パック」を独自開発して大きな業績を上げた。スモールスタートから基幹システム仮想化まで、幅広いニーズに対応できるのが大きな特徴だ。

VMwareのパートナー向けセールスプログラム「Advantage+」を効果的に活用し、優れた総売上と成約率を達成したことが評価された兼松エレクトロニクス。その成果は、顧客にコストメリットというかたちで還元されている。

日本アイ・ビー・エム人財ソリューションが開催する、VMwareの仮想化製品群を使ったシステムの構築、運用管理のポイントを習得できる講座では、受講者のスキルに合わせたきめ細やかな対応が評判を呼んでいる。

VMwareの可能性に早くから注目し、プラットフォーム戦略を推進してきたNEC。同社は「クラウド指向サービスプラットフォームソリューション」と銘打ち、クラウドに関するさまざまなサービスを打ち出している。

中小企業における仮想化環境の導入を、検証から構築、運用保守までのワンストップメニューでトータルに支える大塚商会。豊富な提案で、顧客企業の信頼を獲得している。

エス・アンド・アイは仮想デスクトップからさらに一歩進んで、セキュリティレベルをより強固にできる「Secured Desktop Cloud」を開発し、金融業界で実績を重ねている。

VMwareのサーバ分野における市場開拓、売り上げ増加などへの貢献が評価された日本ヒューレット・パッカード。同社の新戦略においても、VMwareによる仮想化は重要な技術基盤と位置づけられている。

数多くの「VMware認定プロフェッショナル」資格保有者を育成した富士通エフサス。今後は、社内実践を通じて蓄積したノウハウを基に「クラウドのエフサス」へとさらなる飛躍を目指す。

VMwareの仮想化アプリケーションを活用し、多くの大型仮想化システムの導入を行った富士通。仮想化・クラウド化のモデルとなる意欲的な事例を数多く創出したことが、受賞を引き寄せた。

OEM販売されたVMware製品の売上高などが評価された日本IBM。同社の「IBM System x」は、今日の仮想化プラットフォームとしても、多くのユーザーから選択され、支持されている。
