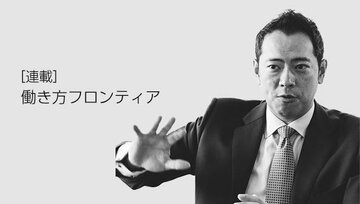アウトバウンドM&A 成功のための方程式
国内市場の縮小が見込まれる中、成長を求める日本企業による海外M&Aが近年増加傾向にある。半面、買収した海外子会社の減損処理をはじめ、M&Aが当初企図した結果を生んでいない事例も多い。海外M&Aを志向する日本企業にとっては、最大限の事前準備に加え、失敗による損失を一定範囲に抑えつつ、失敗からも学び、経験を積んでいく姿勢こそが肝要となる。海外M&Aを機に、みずからも生まれ変わる覚悟を持って当たらない限り、グローバル市場における成功はおぼつかない。問われるのは、ほかでもない自社のあり方そのものである。
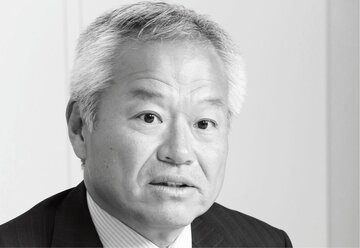
監査業務のあり方と働き方を一新する「次世代監査」
テクノロジーの進化で、知的労働の多くをAIが代替するといわれるが、会計監査もけっして例外ではない。その可能性、業務内容にどのような変化が起きているのか。AI活用の衝撃は監査のあり方、監査人の働き方、キャリア、組織体制にまで影響を与えそうである。「次世代監査」は何を、どう変えるのか、そのインパクトを探ってみた。

不良債権が膨れ上がったことで経営危機を招き、3兆円を超える公的資金の注入を受けて“実質国有化”されたりそなホールディングスは「公的資金の返済ができず、いずれ破綻するだろう」と銀行関係者の間でもささやかれていた。りそなグループの前身は大和銀行とあさひ銀行で、いずれも都市銀行の下位に甘んじており、それだけに体力以上の無理を重ね、財務内容を悪化させていた。 実質国有化と同時に、りそなホールディングス会長に就任した細谷英二氏は旧国鉄で改革を推進した一人だが、金融業界は未経験。周囲が反対する中、不退転の決意を固め火中の栗を拾う道を選んだ。素人の目、一般の利用者の目で、銀行のおかしな実態、内輪の論理にメスを入れ、銀行界の横並び意識、内向きの体質に切り込んでいく。 細谷氏は病魔に襲われ、道半ばで斃れた。だが、「細谷改革のDNA」はりそなグループに根付き、銀行業界、金融界初のサービスを次々と開発し、業務改革、新サービスの導入など、チャレンジを続けている。 IT企業、ネット企業の金融ビジネスへの参入が相次いでいるが、りそなグループは何を目指しているのか。細谷氏の下で財務改革の陣頭指揮を執り、細谷イズムを身近で体験してきた東和浩氏を直撃し、りそな改革の全容、金融ビジネスの展望について聞いた。

不良債権が膨れ上がったことで経営危機を招き、3兆円を超える公的資金の注入を受けて“実質国有化”されたりそなホールディングスは「公的資金の返済ができず、いずれ破綻するだろう」と銀行関係者の間でもささやかれていた。りそなグループの前身は大和銀行とあさひ銀行で、いずれも都市銀行の下位に甘んじており、それだけに体力以上の無理を重ね、財務内容を悪化させていた。 実質国有化と同時に、りそなホールディングス会長に就任した細谷英二氏は旧国鉄で改革を推進した一人だが、金融業界は未経験。周囲が反対する中、不退転の決意を固め火中の栗を拾う道を選んだ。素人の目、一般の利用者の目で、銀行のおかしな実態、内輪の論理にメスを入れ、銀行界の横並び意識、内向きの体質に切り込んでいく。 細谷氏は病魔に襲われ、道半ばで斃れた。だが、「細谷改革のDNA」はりそなグループに根付き、銀行業界、金融界初のサービスを次々と開発し、業務改革、新サービスの導入など、チャレンジを続けている。 IT企業、ネット企業の金融ビジネスへの参入が相次いでいるが、りそなグループは何を目指しているのか。細谷氏の下で財務改革の陣頭指揮を執り、細谷イズムを身近で体験してきた東和浩氏を直撃し、りそな改革の全容、金融ビジネスの展望について聞いた。

裁量労働制の拡大、高度プロフェッショナル制度の導入など、働き方改革をめぐる議論は、今や国家的課題としての高まりを見せている。しかし、その現場に目を向ければ、依然として労働時間の短縮という「各論」のレベルで語られているのが現実だ。働き方改革を、社会的責任を越えて生産性の問題として捉え直すと、企業が取り組むべき課題として、働き方改革の本来の姿が見えてくる。
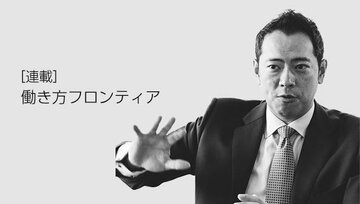
デジタル・トランスフォーメーションでイノベーションを創発せよ
モノの製造販売、サービスの提供を中心にするビジネスから、ソリューションを提供するビジネスモデルに転換する時、それを支えるのがデジタル・トランスフォーメーション(デジタル変革)である。イノベーションを促し、企業と消費者の関係、社会のあり方を変えるデジタル・トランスフォーメーションをどのように進めればいいのか。組織に根付かせるには何をすべきか。2人の実践者に語ってもらった。

不確実性時代の企業成長論
世界的な地政学リスクの浮上や経済動向の流動性に加え、破壊的テクノロジーの発展が企業経営の見通しをいっそう不透明にしている今日。そうした不確実性がもたらす不安が、成長への自信を上回り、経営の保守化傾向を強めてはいないだろうか。不確実性の時代にあって日本企業が取るべき針路を、KPMGジャパンのリーダーが提言する。

破壊的変化の中でCEOが持つべき視点
KPMGは2016年に続き、「KPMGグローバルCEO調査2017」を実施した。経済的、あるいは地政学的な不確実性がますます高まる中で、世界のCEOたちは事業への影響をどう見極め、自社の成長に向けてどう対処しようとしているのか。 もはや不可逆的となった破壊的変化の荒波に向き合わざるをえないこの時代、CEOが持つべき視点と資質について、2017年11月にKPMGインターナショナルのトップであるチェアマンに就任した、ビル・トーマス氏に聞いた。

日本発多国籍企業への挑戦
少子高齢化による国内市場縮小で、企業のクロスボーダーM&Aやグローバル化はもはや不可欠。積極果敢にそれらを推し進めるには、いったい何が必要なのか。そのカギを握るのが、「経営ダッシュボード」と呼ばれる経営指標の可視化だ。属人的な意思決定ではなく、主要な経営指標を常時チェックしながら迅速に意思決定を下し、会社をよき未来へと導くことができるか――。多国籍企業へと舵を切った日本企業の経営陣の中でも、攻めと守りの両方を担えるCFOの存在が重要になってくる。

CEATEC JAPAN 2017の特別セミナーとして10月6日に開催された『DIAMOND Quarterly』創刊1周年記念フォーラム。基調講演に登壇したのは、ソニー・プレイステーションの生みの親として知られる、サイバーアイ・エンタテインメント代表取締役社長兼CEOの久夛良木健氏である。本誌2016年冬号のロングインタビューで「デジタル時代のイノベーション」について語った久夛良木氏が今回の講演テーマに選んだのは、目覚ましい進化を見せるAIだ。AIは私たちの暮らしやビジネスをどのように変えていくのか。久夛良木氏はその最新動向を交えつつ、AIと人間が共創する未来について語った。

地方の小さな製造業の女性活用が話題を呼んでいる。創業78年。ステンレスねじ業界において国内トップの生産量を誇る静岡市の興津螺旋では、2012年、それまで男性しかいなかったねじの製造現場に初めて女性社員が配属された。「ねじガール」と呼ばれるようになった女性社員はその後着々と増え続け、現在では10人を数える。「私もねじを作ってみたい」という女性社員の一声から始まった試みは、同社の風土や経営の在り方にも影響を及ぼすようになっている。「ねじガール」の活躍は、老舗中小企業の何を、どのように変えたのか。同社の代表取締役社長の柿澤宏一氏に話を聞いた。
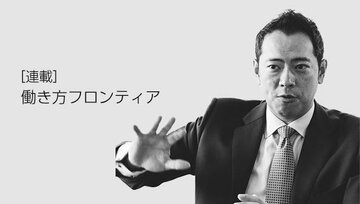
W・L・ゴア・アンド・アソシエーツ(以下ゴア)というグローバル企業をご存じだろうか。日本では、ゴアテックスの製造元と言えば、ピンと来るのではなかろうか。社員を何より大切にしている会社としてもよく知られており、たとえば1984年以来、『フォーチュン』誌の「働きがいのある会社」100社にランクインし続けている。ユニークな人事制度、柔軟な働き方、手厚い福利厚生、充実した各種施設などは、多くの場合、本社のある国に限られるが、ゴアは本社のある国以外でも評価が高い。

W・L・ゴア・アンド・アソシエーツ(以下ゴア)というグローバル企業をご存じだろうか。日本では、ゴアテックスの製造元と言えば、ピンと来るのではなかろうか。社員を何より大切にしている会社としてもよく知られており、たとえば1984年以来、『フォーチュン』誌の「働きがいのある会社」100社にランクインし続けている。ユニークな人事制度、柔軟な働き方、手厚い福利厚生、充実した各種施設などは、多くの場合、本社のある国に限られるが、ゴアは本社のある国以外でも評価が高い。

多様な働き方を受容し、働き手の量と質を確保する――。生産年齢人口が減り続けるなかで、多くの企業が推進する働き方改革の動機だが、そこには長期的な労働力確保のためのコストという見方が横たわり、事業の成長が多少犠牲になってもやむを得ないと捉える向きもある。これとは一見、逆方向ともいえる顧客視点の働き方改革を進めているのが伊藤忠商事だ。フレックス制の廃止や若手社員の寮の整備など、過去の働き方に戻るような施策を次々に導入している同社が目指す働き方改革の狙いとは何か。改革を先頭に立って進めている同社人事・総務部企画統括室長の西川大輔氏に話を聞いた。
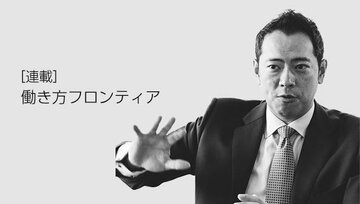
一つの収益認識で連結経営を強化する【第2部】新基準の導入メリットを最大化する
2017年7月20日、我が国における収益認識基準の公開草案が公表された。国際会計基準(IFRS)や米国会計基準とほぼ同様の内容だ。この新収益基準の導入により、実務は大きな影響を受けるであろう。会計のグローバルスタンダード化が加速する中で的確に対応するため、従来基準と何が違うのか、適用によりどんな影響があるのか、経営者が知っておかなければならない新収益基準がもたらす経営へのインパクトを聞いた。

一つの収益認識で連結経営を強化する【第1部】収益認識の新基準導入で企業はどう変わるのか
2017年7月20日、我が国における収益認識基準の公開草案が公表された。国際会計基準(IFRS)や米国会計基準とほぼ同様の内容だ。この新収益基準の導入により、実務は大きな影響を受けるであろう。会計のグローバルスタンダード化が加速する中で的確に対応するため、従来基準と何が違うのか、適用によりどんな影響があるのか、経営者が知っておかなければならない新収益基準がもたらす経営へのインパクトを聞いた。

金融サービスが好循環をもたらす近未来社会
デジタル金融革命の時代が到来した。テクノロジーの進化によって新しいサービス技術が登場したことで、金融機関は新たなビジネスモデルの構築を迫られている。キーワードはオープンイノベーション。金融、流通、医療というように分断されてきた業種単位のシステムインフラは、金融サービスを軸に連携し、新しい形態への進化を猛スピードで遂げつつある。

豊田喜一郎置かれた状況で最善を尽くす
喜一郎の人生はまさに曲がりくねった道を行くがごとくであった。けっして彼は目的に向かってまっしぐらに邁進できたわけではない。しかし、後から振り返ってみると、曲がりくねった道や回り道のような経路が、のちの自動車事業の創出・育成に意味があったかのように見えてくる。敬虔なキリスト教徒の英訳者スクリプチャック氏からすれば、喜一郎という人物は、神が与えた使命・目的を果たすべく「曲線で描いた直線」を真摯に突き進んだ、といった風に見えたのではなかろうか。本人は大いに悩んでいたが、迂回していたように思っていても、それこそが使命を達する「まっすぐな道」だったのだと。 戦後日本の礎をつくった偉大な経営者の一人として喜一郎も評価されるようになったとはいえ、その足跡をたどってみると、目標に向かって一直線に邁進できたわけではない。彼の片言隻句や行動の一端を取り上げて示唆を得ようとするのではなく、おのれが置かれた状況の中で最善を尽くし、目の前の課題と格闘し続けた姿勢こそ学ぶべきではなかろうか。みずからの使命をまっとうする「まっすぐな道」を切り開いていくためにも。

「働き方改革」を支援する立場として、現場の担当者の方にお話をうかがうと、意外と誰にも喜ばれていないという現実に出くわす。総論としてはどんな人にもメリットがあっても、各論としては犠牲となる人が生じる。こうした状況のまま改革ブームが進んでいいものか。そんな問題意識で開催した「現場視点で考える働き方改革セミナー」だったが、ご登壇者からも、聴衆の方々からも想像以上に改革のリアルを求める空気が伝わってきた。
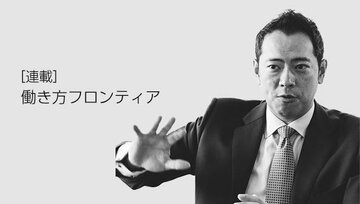
長寿命化がもたらす働き方や生き方の変化を『ワーク・シフト』『ライフ・シフト』の2冊の著作で鮮やかに描き出し、私たちが今すぐ取り組むべきことを多彩な観点から示唆したリンダ・グラットン氏。しかし、個人が会社に依存せずにキャリアデザインを描くことは、組織やネットワークが不要になることを意味するわけではない。新時代の組織はどうあるべきか、マネジメントの役割はどう変わるか、そして私たち一人一人は何を選択すべきなのだろうか。