藤本隆宏氏は、漠然とした可能性や推測を排し、べき論や安易な演繹論を避け、現場の観察と調査を通じて現実を語る、数少ない経営研究家である。本インタビューは、現場の視点で読み直した日本産業の歴史観に始まり、これからのグローバル競争のあり方、自動車産業の近未来、IoT(モノのインターネット)やインダストリー4・0の現実、プラットフォーム戦略やビジネス・エコシステム論の功罪、ビジネス・ジャーゴンの陥穽等、多岐にわたっているが、ものづくりにまつわる偏見や誤解を正し、21世紀こそ強くて明るい「良い現場」づくりがグローバル競争には不可欠であることを、一人でも多くのビジネスリーダーと共有することを目的としている。
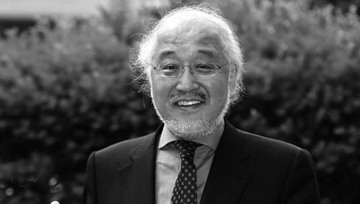
現在のように先が読みにくく、判断に迷う時代には、地に足の着いた「中庸の徒」の言うことに耳を傾けたい。藤本隆宏氏は、漠然とした可能性や推測を排し、べき論や安易な演繹論を避け、現場の観察と調査を通じて現実を語る、数少ない経営研究家である。本インタビューは、ものづくりにまつわる偏見や誤解を正し、21世紀こそ強くて明るい「良い現場」づくりがグローバル競争には不可欠であることを、一人でも多くのビジネスリーダーと共有することを目的としている。
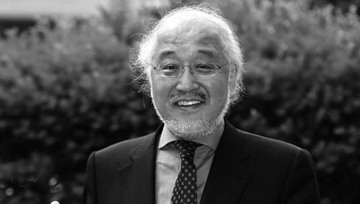
盛田昭夫可能性の海を渡り、 世界をモチベートした日本人
盛田昭夫は「自由闊達にして」冒険心あふれる経営者だった。少なくともその心意気を失わないことを自身に課していた。それは、みずからが名付けた「ソニー」という画期的なブランド名を持つ企業を常に未来に向けて架橋するためであり、新たな可能性の海を渡ることが、世界からリスペクトされる日本人の行き方であると、世に訴えたかったからだ。
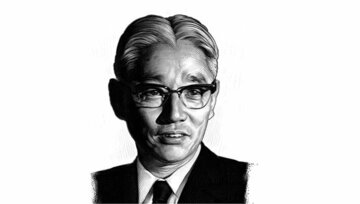
世界に先駆けて本格的な人口減少に入った日本において、「働き方」も変化を余儀なくされている領域の一つ。だが、企業の雇用制度やビジネスモデルの変化は鈍い。豊かな働き方を実現するためにはどうしたらいいのか。世界最大の人材サービス企業アデコグループの日本法人トップ、川崎健一郎が「新しい働き方」をビジネスの力で実現する方法を探る。
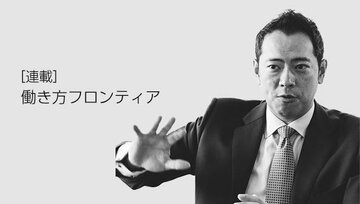
ベストセラー『コア・コンピタンス経営』の共著者であるゲイリー・ハメルは、戦略やイノベーションの研究家として世界的な評価を得ている。21世紀に入ってから、彼の問題意識は「マネジメントイノベーション」に大きく傾いており、もっぱら「未来の経営」「マネジメント2.0」について持論を披露している。今回のインタビューでは、彼が主宰するマネジメントラボの最新調査を踏まえながら、組織の官僚制を可能な限り縮小し、従業員一人ひとりのポテンシャルを引き出すことの重要性とインパクトについて考える。

ベストセラー『コア・コンピタンス経営』の共著者であるゲイリー・ハメルは、戦略やイノベーションの研究家として世界的な評価を得ている。21世紀に入ってから、彼の問題意識は「マネジメントイノベーション」に大きく傾いており、もっぱら「未来の経営」「マネジメント2.0」について持論を披露している。今回のインタビューでは、彼が主宰するマネジメントラボの最新調査を踏まえながら、組織の官僚制を可能な限り縮小し、従業員一人ひとりのポテンシャルを引き出すことの重要性とインパクトについて考える。

ベストセラー『コア・コンピタンス経営』の共著者であるゲイリー・ハメルは、戦略やイノベーションの研究家として世界的な評価を得ている。21世紀に入ってから、彼の問題意識は「マネジメントイノベーション」に大きく傾いており、もっぱら「未来の経営」「マネジメント2.0」について持論を披露している。今回のインタビューでは、彼が主宰するマネジメントラボの最新調査を踏まえながら、組織の官僚制を可能な限り縮小し、従業員一人ひとりのポテンシャルを引き出すことの重要性とインパクトについて考える。

パナソニックの「津賀改革」には、いくつかの特徴がある。ほぼ6カ月単位で勝負をかけメリハリをつけていること。インパクトのあるメッセージを常に意識して打ち込むこと。しかも、それらは時代と世界への観察をもとに、「構図」を描き、シンプルなキーワードで発信されている。さらに、朝令暮改を恐れず物怖じしない。それでいて、基軸はぶれない。

パナソニックの「津賀改革」には、いくつかの特徴がある。ほぼ6カ月単位で勝負をかけメリハリをつけていること。インパクトのあるメッセージを常に意識して打ち込むこと。しかも、それらは時代と世界への観察をもとに、「構図」を描き、シンプルなキーワードで発信されている。さらに、朝令暮改を恐れず物怖じしない。それでいて、基軸はぶれない。

パナソニックの「津賀改革」には、いくつかの特徴がある。ほぼ6カ月単位で勝負をかけメリハリをつけていること。インパクトのあるメッセージを常に意識して打ち込むこと。しかも、それらは時代と世界への観察をもとに、「構図」を描き、シンプルなキーワードで発信されている。さらに、朝令暮改を恐れず物怖じしない。それでいて、基軸はぶれない。

森本博行氏は、ソニーで長らく経営戦略に携わり、その後はビジネススクールで戦略論やビジネスモデルの研究者として教鞭を執ってきた。いわく「グローバル戦略はいま移行期にある」。本インタビューでは、日本企業の経営者が理解しておくべき、新しいゲームルールと競争優位の条件について考える。

森本博行氏は、ソニーで長らく経営戦略に携わり、その後はビジネススクールで戦略論やビジネスモデルの研究者として教鞭を執ってきた。いわく「グローバル戦略はいま移行期にある」。本インタビューでは、日本企業の経営者が理解しておくべき、新しいゲームルールと競争優位の条件について考える。

生活用品からインフラまで幅広く使われる塩化ビニル樹脂(塩ビ)で世界トップ企業の信越化学工業。その中核となるのがアメリカ子会社のシンテックだ。金川千尋会長はかつてシンテックの社長として、アメリカで最後発の参入にもかかわらず世界一の塩ビメーカーに育て上げた。さらに同社で培った経営ノウハウをグループ内の他事業にも導入し、13期連続で最高益を更新するなど、業績を大きく向上させた(図表参照)。奇しくも信越化学工業(当時は信越窒素肥料)と同年に生まれた金川会長は今年で90歳。いまも経営の最前線に立つ同氏が、みずから体得した経営論の真髄を語った。

松下幸之助企業理念を“シンプルな戦略に翻す”名人
幸之助さんが他界されて四半世紀が経つが、多くの日本企業が目的の喪失、理念の喪失に陥っている現在、あらためて彼の歴史をひもとくと、はたと気づかされること、いまだからこそ肝に銘じるべきことが少なくない。
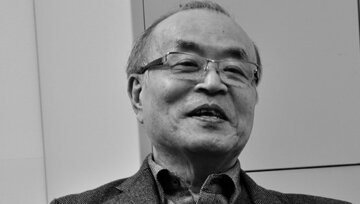
生活用品からインフラまで幅広く使われる塩化ビニル樹脂(塩ビ)で世界トップ企業の信越化学工業。その中核となるのがアメリカ子会社のシンテックだ。金川千尋会長はかつてシンテックの社長として、アメリカで最後発の参入にもかかわらず世界一の塩ビメーカーに育て上げた。さらに同社で培った経営ノウハウをグループ内の他事業にも導入し、13期連続で最高益を更新するなど、業績を大きく向上させた(図表参照)。奇しくも信越化学工業(当時は信越窒素肥料)と同年に生まれた金川会長は今年で90歳。いまも経営の最前線に立つ同氏が、みずから体得した経営論の真髄を語った。

「プレイステーションVR」の発売で、再び脚光を集めているプレイステーション。その生みの親といえるのが、久夛良木健氏だ。一介のサラリーマンエンジニアだった同氏は、世界からベストプラクティスを集め、製品開発と事業化を実現。8年で売上1兆円という巨大インダストリーをつくり出した。たえず未来を洞察しながら変革のうねりを牽引してきた久夛良木氏に、デジタル時代におけるイノベーションの核心について聞いた。

「プレイステーションVR」の発売で、再び脚光を集めているプレイステーション。その生みの親といえるのが、久夛良木健氏だ。一介のサラリーマンエンジニアだった同氏は、世界からベストプラクティスを集め、製品開発と事業化を実現。8年で売上1兆円という巨大インダストリーをつくり出した。たえず未来を洞察しながら変革のうねりを牽引してきた久夛良木氏に、デジタル時代におけるイノベーションの核心について聞いた。

「プレイステーションVR」の発売で、再び脚光を集めているプレイステーション。その生みの親といえるのが、久夛良木健氏だ。一介のサラリーマンエンジニアだった同氏は、世界からベストプラクティスを集め、製品開発と事業化を実現。8年で売上1兆円という巨大インダストリーをつくり出した。たえず未来を洞察しながら変革のうねりを牽引してきた久夛良木氏に、デジタル時代におけるイノベーションの核心について聞いた。

2008年にタイヤ事業で世界一となるが、食品、鉄鋼、化学、電機、金融など全産業で、日本企業が世界トップを守っているのはトヨタ自動車とブリヂストンだけだ。今年、コーポレートガバナンス(企業統治)に取り組む企業を対象にした賞が新設され、第1回の大賞に輝いた。試行錯誤を繰り返しながら、グローバル経営体制、ガバナンスを整備し、買収から28年、アメリカでの事業を稼ぎ頭に変貌させたブリヂストンの経営に迫った。

2008年にタイヤ事業で世界一となるが、食品、鉄鋼、化学、電機、金融など全産業で、日本企業が世界トップを守っているのはトヨタ自動車とブリヂストンだけだ。今年、コーポレートガバナンス(企業統治)に取り組む企業を対象にした賞が新設され、第1回の大賞に輝いた。試行錯誤を繰り返しながら、グローバル経営体制、ガバナンスを整備し、買収から28年、アメリカでの事業を稼ぎ頭に変貌させたブリヂストンの経営に迫った。

