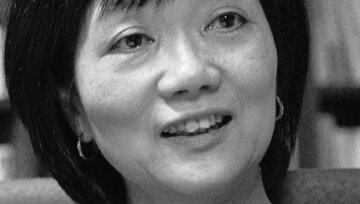安藤百福偉大なる発明家であり、起業家であり、経営者であった
日清食品の創業者、安藤百福は2007年1月5日に亡くなった。96歳だった。その4日後、『ニューヨークタイムズ』紙は、「ミスター・ヌードルに感謝」と題する社説を掲載し、次のような文章で結んだ。「インスタントラーメンの発明によって、安藤は人類の進歩の殿堂にその名を永遠に残すことになった。人に魚を釣る方法を教えれば、その人は一生食べていける。人にラーメンを与えれば、何も教える必要はない」これは、安藤と彼の発明に対する最大級の賛辞を表したものにほかならない。彼はまさしく偉大な発明家だった。しかしそれだけではない。偉大な産業人であり、また起業家、経営者でもあった。

グーグルがチームの生産性要因を統計学的に明らかにした「プロジェクト・アリストテレス」をはじめ、現在「ピープルアナリティクス」と呼ばれる「人事を科学する」試みが広がっている。このピープルアナリティクスは、これまでの常識や定説、属人的な経験則に頼った人材マネジメントの誤りや弊害を定量的に明らかにし、自社にふさわしい人事制度や能力開発プログラムを導き出すというもの。労働経済学の専門家である大湾秀雄氏は、企業の人事担当者たちと一緒にピープルアナリティクスを実践する「人事情報活用研究会」を主宰している。本インタビューでは、大湾氏らの研究・分析の成果から、これからの人事政策、人づくりのあり方、そしてピープルアナリティクスの活用法について考える。

日本経済の復活はDXなくしては始まらない
オックスフォード大学の研究者による「10~20年以内に、労働者の大半がAIやロボットに職を奪われる」という衝撃的な予測と並行して、世界的なIT業界のビジョナリーたちも「デジタル・オア・ダイ──。デジタル・トランスフォーメーション(DX)に取り組まなければ衰退は免れない」というメッセージを投げかける。日本の場合、雇用や就労形態が他国と大きく異なるため、これら2つの課題には適度なバランスが求められるが、のんびりしてもいられない。そこで、日本と産業構造が似ているだけでなく、日本以上に労働者の権利に敏感なドイツにおいてさまざまな経験を重ねてきた、デジタル分野のコンサルティングのプロであるクリスチャン・ラスト氏に、DXに関する知見と日本企業へのアドバイスを聞いた。

デジタル時代のM&A戦略
テクノロジーの進化は顧客を変え、企業を変え、産業そのものを再定義する破壊力を持つ。その破壊力は、M&Aの領域においても、その戦略や手法に大きく影響を及ぼし始めている。テクノロジーによって価値を高めた企業のM&Aには、従来のM&Aとは異なる機会とリスクがある。最新テクノロジーを活用した独自ツールを組み合わせ、海外・業種間M&Aを中心にアドバイザリー業務を展開するKPMG FASのポール・フォード氏と渡辺麻紀子氏に話を聞いた。

高まる地政学的リスクの下で求められる税務マネジメント
トランプ政権下のアメリカに端を発した自国第一主義や保護貿易主義の台頭、米中貿易摩擦に代表される大国間の覇権争い、Brexitといった既存の政治的枠組みの見直しなど、歴史的な変革期に見られる混乱が世界経済を襲っている。地政学的リスクの高まりを受け、企業は持続可能なビジネスのあり方を模索しているが、忘れてはならないのが税務マネジメントである。国際税務や関税などの税制が変化する中で、企業価値の源泉たる利益の最大化には税務の最適化が不可欠だ。

イノベーションをマネジメントする
日本がイノベーション後進国といわれて久しい。しかし近年、21世紀にふさわしいイノベーションを創出すべく、多くの企業で新たな試みが始まっている。それは、「オープンイノベーション」と「デジタル・トランスフォーメーション」だ。イノベーションそのものが“手段の目的化”とならないよう、これらにどう向き合い、マネジメントするかが問われている。みずから先頭に立ち、未来の課題解決のためのイノベーションに取り組む2人に、その要諦を聞いた。

AIが企業経営にもたらすインパクト
AIによる経営の高度化や新ビジネスに関する記事をよく目にするが、投資額を見る限り、本気で取り組んでいる日本企業はそう多くはない。よそがやっているからうちも何もしないわけにはいかない──そんな本音も透けて見える。しかし、一時のブームととらえてやり過ごすには、この革新的技術の波はあまりにも高くて激しい。安易に乗れば地面に強く打ち付けられるし、タイミングをつかめずに見送ってばかりいれば先駆企業の後ろ姿さえ見えなくなってしまう。すでに到来したAI時代は、企業経営にどんなインパクトを与えるのだろうか。

成長の試練に直面する経営者が克服すべき課題
デジタル変革やデータ経済への対応の遅れ、ガバナンス不全を露呈する不祥事の続発、あるいは世界的に要求が高まる社会的課題解決への貢献など、日本企業は成長への試練ともいうべきさまざまな課題に直面している。そうした課題の克服に向けて、経営者はいまどう判断し、行動すべきなのか。KPMGジャパンの2人のトップがその指針を提示する。

『ダイヤモンドクォータリー』創刊2周年を迎え、2018年11月1日、東京ミッドタウン日比谷にて、CXOや執行役員を対象に、「人づくり」をメインテーマとしたカンファレンスが開催された。いまなお世界のベストプラクティスとされる日本企業の人間重視の経営。事業環境が激変する中、日本を代表する大企業はどのような「人づくり」によって時代の荒波に立ち向かい、さらなる成長を遂げようとしているのか。現在進行形のさまざまな施策が披露され、21世紀の人づくりについて知見を深める機会となった。
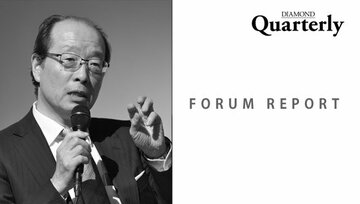
自律型人財の育成~人づくりのための基礎づくり
『ダイヤモンドクォータリー』創刊2周年を迎え、2018年11月1日、東京ミッドタウン日比谷にて、CXOや執行役員を対象に、「人づくり」をメインテーマとしたカンファレンスが開催された。いまなお世界のベストプラクティスとされる日本企業の人間重視の経営。事業環境が激変する中、日本を代表する大企業はどのような「人づくり」によって時代の荒波に立ち向かい、さらなる成長を遂げようとしているのか。現在進行形のさまざまな施策が披露され、21世紀の人づくりについて知見を深める機会となった。

人材育成のためのデータ活用
『ダイヤモンドクォータリー』創刊2周年を迎え、2018年11月1日、東京ミッドタウン日比谷にて、CXOや執行役員を対象に、「人づくり」をメインテーマとしたカンファレンスが開催された。いまなお世界のベストプラクティスとされる日本企業の人間重視の経営。事業環境が激変する中、日本を代表する大企業はどのような「人づくり」によって時代の荒波に立ち向かい、さらなる成長を遂げようとしているのか。現在進行形のさまざまな施策が披露され、21世紀の人づくりについて知見を深める機会となった。

経営のゲームチェンジと「チーム経営2.0」の時代
『ダイヤモンドクォータリー』創刊2周年を迎え、2018年11月1日、東京ミッドタウン日比谷にて、CXOや執行役員を対象に、「人づくり」をメインテーマとしたカンファレンスが開催された。いまなお世界のベストプラクティスとされる日本企業の人間重視の経営。事業環境が激変する中、日本を代表する大企業はどのような「人づくり」によって時代の荒波に立ち向かい、さらなる成長を遂げようとしているのか。現在進行形のさまざまな施策が披露され、21世紀の人づくりについて知見を深める機会となった。

日立の事業変革とグローバル人材戦略
『ダイヤモンドクォータリー』創刊2周年を迎え、2018年11月1日、東京ミッドタウン日比谷にて、CXOや執行役員を対象に、「人づくり」をメインテーマとしたカンファレンスが開催された。いまなお世界のベストプラクティスとされる日本企業の人間重視の経営。事業環境が激変する中、日本を代表する大企業はどのような「人づくり」によって時代の荒波に立ち向かい、さらなる成長を遂げようとしているのか。現在進行形のさまざまな施策が披露され、21世紀の人づくりについて知見を深める機会となった。

オープンイノベーションで日本を「起業家社会」に転換する
2018年9月、KDDIの専門組織、高度な専門性を有するパートナー企業、そしてお客さま企業が新規事業の共創に取り組む「KDDI DIGITAL GATE」がオープンした。KDDIには、オープンイノベーションの場を提供し、スタートアップを支援する「KDDI ∞ Labo(ムゲンラボ)」がある。これら2つのイノベーション加速装置が“結合”することで、スタートアップと大企業がオープンに共創する好循環システムが生み出された。

エコシステム形成による価値創造
デジタル化社会の到来が、競争相手と競争のルールを一変させようとしている。こうしたディスラプションの時代を生き抜くカギとなるのは、エコシステムの形成を通じた新たな価値創造である。では、そのエコシステム形成の戦略はどうあるべきか。戦略コンサルティング、EYパルテノン(*)の中川勝彦氏に聞いた。

日本のイノベーション能力低下が著しい。従来型のビジネスモデル起点の発想から、生活者視点に根差したライフモデル起点の事業構想への転換が、新たなビジネス創造性を喚起すると嶋本達嗣氏は説く。

「監査の質」向上がもたらすマネジメントへのインパクト
会計不正が長く見過ごされていたケースが相次いで発覚し、関係した監査法人に批判が集中した。資本市場の信頼性を根底から揺るがしかねない事態に、金融庁をはじめとする関係当局は、不正リスクに着眼した監査の実施や監査プロセスの透明化など、監査品質の向上に乗り出した。しかし、より大きな視点で見れば、問われているのは企業の財務情報の信頼性と、それを前提とした資本市場そのものにほかならない。監査の厳格化が経営に及ぼす影響を考察する。

「おもしろおかしく」というユニークな社是を掲げる堀場製作所(以下ホリバ)は、「ほんまもん」のグローバル経営へ駆け上ろうとしている。世界トップシェアの分析・計測機器で知られる同社は、技術の変化を先取りして成長してきた。 根底には「おもしろおかしく」のスピリットがある。1971年に大阪証券取引所への上場を機に、創業者の堀場雅夫氏(日本の学生ベンチャー第1号)が、みずからの経営フィロソフィーである「おもしろおかしく」を社是にしたいと社内で提案した時、「普段はヨイショの意見しか言わんくせに」(雅夫氏)、役員全員が猛反対。正式に社是となるまで7年の歳月を要した。 難しいことに挑戦し、働くことをおもしろがって追求してこそ、人も会社も成長する――というのが本来の趣旨。それでも「吉本興業じゃあるまいし、もっと真面目な社是に」という批判もあったが、嫡男で3代目社長となった堀場厚氏は、「おもしろおかしくなければ、独創的な発想は生まれない。仕事のための仕事ではなく、自分の想いで働くことが革新を生む原動力となる」として、海外向けにも英訳。「JOY&FUN」を大きく打ち出した。 そのフィロソフィーがエキサイティングだと海外でも受け入れられ、感銘を受けたフランスやドイツの企業から、「傘下に入りたい」と買収を逆提案される〝おもしろい〟現象まで生まれた。 厚氏が社長に就任して以来、26年。この間に、売上げは5倍、営業利益は9倍となり、過去最高の業績を更新中である。しかも、売上げ・従業員数ともに海外比率が全体の7割近いグローバル企業に成長した。 今年(2018年)1月、厚氏は社長のバトンを足立正之氏に託し、みずからは会長兼グループCEOとして、副会長兼グループCOOの齊藤壽一氏とともに、グローバル経営の次のステップへ舵を切った。それは「技術の潮目が変わる」時代にグローバル化の新次元を駆け上るための、「タイミング・スピード・継続」の3点セットをゆるがせにしない決断だった。 景気変動とテクノロジーの大転換という荒波に立ち向かう新鋭「びわこ工場(注1)」で、京都発グローバル企業の成功の要諦と次の一手を、縦横に語ってもらった。

「おもしろおかしく」というユニークな社是を掲げる堀場製作所(以下ホリバ)は、「ほんまもん」のグローバル経営へ駆け上ろうとしている。世界トップシェアの分析・計測機器で知られる同社は、技術の変化を先取りして成長してきた。 根底には「おもしろおかしく」のスピリットがある。1971年に大阪証券取引所への上場を機に、創業者の堀場雅夫氏(日本の学生ベンチャー第1号)が、みずからの経営フィロソフィーである「おもしろおかしく」を社是にしたいと社内で提案した時、「普段はヨイショの意見しか言わんくせに」(雅夫氏)、役員全員が猛反対。正式に社是となるまで7年の歳月を要した。 難しいことに挑戦し、働くことをおもしろがって追求してこそ、人も会社も成長する――というのが本来の趣旨。それでも「吉本興業じゃあるまいし、もっと真面目な社是に」という批判もあったが、嫡男で3代目社長となった堀場厚氏は、「おもしろおかしくなければ、独創的な発想は生まれない。仕事のための仕事ではなく、自分の想いで働くことが革新を生む原動力となる」として、海外向けにも英訳。「JOY&FUN」を大きく打ち出した。 そのフィロソフィーがエキサイティングだと海外でも受け入れられ、感銘を受けたフランスやドイツの企業から、「傘下に入りたい」と買収を逆提案される〝おもしろい〟現象まで生まれた。 厚氏が社長に就任して以来、26年。この間に、売上げは5倍、営業利益は9倍となり、過去最高の業績を更新中である。しかも、売上げ・従業員数ともに海外比率が全体の7割近いグローバル企業に成長した。 今年(2018年)1月、厚氏は社長のバトンを足立正之氏に託し、みずからは会長兼グループCEOとして、副会長兼グループCOOの齊藤壽一氏とともに、グローバル経営の次のステップへ舵を切った。それは「技術の潮目が変わる」時代にグローバル化の新次元を駆け上るための、「タイミング・スピード・継続」の3点セットをゆるがせにしない決断だった。 景気変動とテクノロジーの大転換という荒波に立ち向かう新鋭「びわこ工場(注1)」で、京都発グローバル企業の成功の要諦と次の一手を、縦横に語ってもらった。

「明君(めいくん)(賢い君主)と暗君(あんくん)(無能な君主)との違いは何か」、唐の第2代皇帝太宗(たいそう)は、腹心の魏徴(ぎちょう)にこう尋ねた。すると、魏徴答えていわく「明君の明君たるゆえんは、広く臣下の進言に耳を傾けることであります。また、暗君の暗君たるゆえんは、お気に入りの家臣の言葉しか信じないことであります。(中略)君主たる者が臣下の進言に広く耳を傾ければ、一部の側近に耳目を塞がれることなく、よく下々の動きを知ることができるのです」。 これは『貞観政要(じょうがんせいよう)』の一節である。この書物は、「貞観の治」(627〜649年)と呼ばれる太宗の治世について、その要諦をまとめたものであり、古来より帝王学の教科書といわれてきた。 太宗はこのように語る。「人は自分を見ようと思えば、必ず鏡を使う。君主が過ちを知ろうと思えば、必ず忠臣の諫言(かんげん)が必要である。(中略)君たちは人民が苦しんでいる状況を見たならば、必ず思う存分言い尽くし、私を正し、諫(いさ)めなければならない(注1)」 不都合な真実や耳の痛い話を教えてくれたり、自分をいさめてくれたりする人が、周囲にいるだろうか。「直諫(ちょっかん)は一番槍より難(かた)し」といわれるように、現代の日本にあって側近や部下には望むべくもない。実際、なかなか見つからないのではないか。 本田由紀氏は、あえて空気を読まない、直球勝負の研究者だ。通説や常識を疑い、精緻な調査と分析に基づく事実(ファクト)ベースの言説は、鋭く、時に挑発的だが、総じて小気味よい。ただし、企業リーダー(とその側近の人たち)にすれば、辛辣で、あまり心地よくないかもしれない。 しかし、ビジネスパーソンがついつい忘れがちな「社会の視点」「辺境の視点」を提供してくれる。それは、いわゆる批判や諫言に聞こえようとも、実は自戒や内省のチャンスであり、変革やイノベーションのヒントにほかならない。 本田氏の専門である教育社会学は、教育に関わる事象や問題を社会学の手法によって分析する学問分野であり、本田氏は、教育と仕事(企業)と家族の3領域の関係についてずっと研究や実地調査を続け、声なき声をすくい上げ、発信し続けている。いわく「肉声のリアリティを束にして示すということが、ひしめくように苦しんで生きている人間たちがいることを説得力をもって社会に打ち出すためには、すごく重要なのです(注2)」。 本インタビューでは、まだまだ十分認識されていない若者や女性の雇用や就業の現実、中高年に関する課題について指摘してもらう一方で、いま各所で議論されているメンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への転換に向けた「新たな選択肢(オルタナティブ)」を提示してもらった。