記事検索
「数学」の検索結果:1781-1800/2839件
【中学受験への道】第50回(簡易版)
首都圏で最初の一般入試が大々的に行われる埼玉の動向は、多くのメディアでも取り上げられ、注目を集めている。これまで志願者動向についてお伝えしてきたが、入試問題にはどのような変化が起きているのだろうか。志願者の多い、栄東と開智の算数の問題を例に、長年入試問題を見続けてきた森上教育研究所「親のスキル研究会」講師である小板橋肇貴氏の解説を交えて見ていこう。

【中学受験への道】第50回
「中高一貫校」入試算数の新傾向、埼玉「栄東・開智」の実際の問題から解読【完全版】
首都圏で最初に一般入試が行われる埼玉の動向は、多くのメディアでも取り上げられ、注目を集めている。これまで志願者動向についてお伝えしてきたが、入試問題にはどのような変化が起きているのだろうか。志願者の多い、栄東と開智の算数の問題を例に、長年入試問題を見続けてきた森上教育研究所「親のスキル研究会」講師である小板橋肇貴氏の解説を交えて見ていこう。

第20回
本当に苦しいときに強いのは「センスがいい人」よりも「言語化できる人」
何かが「できる」とは何か。東大卒プロゲーマーのときどさんは、「できる=言語化できる」ことだと言います。それはなぜなのでしょうか?

【中学受験への道】第47回
男子御三家「武蔵」も取り入れる最先端の学び、「探究」とは
迷走する大学入試改革を横目に、日本の教育のあり方は急速に変化している。とりわけ、これからの時代を「生き延びる力」を培うために、高校で導入される「探究」的な学びは、生徒自らが問いを立て、その解決をしていく思考の実践となる。高大接続で大学側も入学者選抜と大学での学びに「探究」に代表されるような新しい教育の成果を生かしていくことになる。最先端の学びの姿を、各分野の第一人者と分かち合う絶好の機会が新年早々、催される。

第67回
「平均」にダマされる日本人
世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破した“現代の知の巨人”、稀代の読書家として知られる出口治明APU(立命館アジア太平洋大学)学長。歴史への造詣が深いことから、京都大学の「国際人のグローバル・リテラシー」特別講義では世界史の講義を受け持った。その出口学長が、3年をかけて書き上げた大著が、全国で話題のベストセラーとなっている。BC1000年前後に生まれた世界最古の宗教家・ゾロアスター、BC624年頃に生まれた世界最古の哲学者・タレスから現代のレヴィ=ストロースまで、哲学者・宗教家の肖像100点以上を用いて、世界史を背骨に、日本人が最も苦手とする「哲学と宗教」の全史を初めて体系的に解説した本だ。なぜ、今、哲学だけではなく、宗教を同時に学ぶ必要があるのか?脳研究者で東京大学教授の池谷裕二氏が絶賛、小説家の宮部みゆき氏が推薦、某有名書店員が激賞する『哲学と宗教全史』が、発売後たちまち第7刷を突破。「日経新聞」「日経MJ」「朝日新聞」「読売新聞」「北海道新聞」「中国新聞」「京都新聞」「神戸新聞」「中日新聞」で大きく掲載。“HONZ”『致知』『週刊朝日』『サンデー毎日』「読売新聞」でも書評が掲載された。過日、立命館アジア太平洋大学(APU)創立20周年を記念して、東京駅直結の立命館東京キャンパス(東京駅直結・サピアタワー)に約100名が集結。「歴史とは何か?」と題した出口氏講演会が開催された。今回から、その後開催され盛り上がった「質疑応答」の模様を特別公開する。

【中学受験への道】第46回
中高一貫校「東京・神奈川共学校」最終予想実倍率、中堅校が躍進!【2020年入試版】
いよいよ本番1カ月前となった。「2020年入試・最終予想実倍率」の最終回では東京・神奈川の共学校を取り上げる。別学から共学化の流れは一息ついた状態だが、東京を中心に小6人口が増加しただけでなく、中学受験をする生徒も増加しており、近年では最も厳しい入試となりそうである。

シリーズ累計50万部突破のベストセラー入門書が、人気漫画家“うめ”さんの手によってついにマンガ化!「はじめに」と第1話は、特別に全ページを無料で公開します

ブラック・スワンへの対処法「反脆弱性」とは何か?
難解な概念「反脆弱性」とは、「知の巨人」タレブが私たちのために考えてくれた、ブラック・スワンへの対処法だった!? ナシーム・ニコラス・タレブの新作『身銭を切れ』刊行を記念して、その思想の軌跡を紐解く短期連載。第2回は『反脆弱性』に迫る。
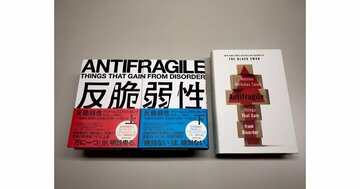
【中学受験への道】第42回
都立「国立高・立川高」、多摩の伝統2校に挑む新興勢力はどこか?
中学受験が盛んな23区と異なり、多摩地区には戦前にルーツを持つ伝統校は多くない。そのため進学校では戦前派と戦後派が競い合っている。一方、都立の新たなエリート校である中高一貫校が年々実力を付け、その人気は高まっている。

なぜ私たちは「不確実性」に手を焼くのか?
「知の巨人」タレブが教える、私たちが「不確実性」にうまく対処できない本当の理由とは?ナシーム・ニコラス・タレブの新作『身銭を切れ』刊行を記念して、その思想の軌跡を紐解く短期連載。第1回は『ブラック・スワン』と不確実性。

2020年度から実施される大学入学共通テストにおいて、英語民間試験の採用延期に続き、国語と数学への記述式問題導入までもが見送りになった。焦点となっている「公平性」について、的を射ない議論が続けられているように感じるのは、なぜだろうか。

第2回
「ハッタリイノベーション」に『WIRED UK』創刊編集長がブチ切れる
「ハッタリイノベーション」は、もうウンザリだ。「シリコンバレーの次」のビジネス戦略を、『WIRED UK』創刊編集長が全網羅。中国、エストニア、フィンランド、UAE、インド、イギリス、オーストラリア、南アフリカ、ペルー、そしてアメリカ。世界6大陸、10か国の知られざる「小さな最先端企業」を、たった1人旅して回った全記録。真のイノベーションに共通していた「16の行動」を1冊に圧縮。

中国が掲げる「一帯一路」の重要拠点でありながら、中国人でさえも日常でほぼ接点がない旧ソ連の小国・アルメニア。まして日本人には、同国の実情など知る由もない。しかしこの国、実はIT分野で世界屈指の実力を持っているのだ。

学習塾といえば、どんな田舎町であっても、駅や学校の近くには必ずあるというイメージだ。しかし近年、そんな学習塾の倒産が相次いでいるという。その理由を「知窓学舎」塾長で、教育実践ジャーナリストの矢萩邦彦氏に聞いた。

第10回
世界の弱者は、大手と同じ戦略では勝てない!ソースネクストがセキュリティソフトの更新料ゼロに踏み切ったときの勝算
ソースネクストといえば、若い人でも「ウイルスセキュリティZERO」を覚えていらっしゃる方が多いようです。業界慣習として当たり前だったセキュリティソフトの年間更新料を0円にしたきっかけと、実施に至る勝算について、同社の松田憲幸社長に聞きました。
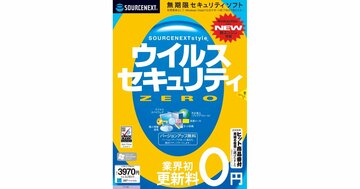
【中学受験への道】第38回
都立「日比谷高校」を合格辞退した生徒は、どこに行ったのか?
そろそろ早めの合格を得るため、併願優遇のある私立校に足を運び始める中学3年生も多い東京の高校受験だが、冬休み前のこの時期は、学校の先生と進路について相談する最終段階でもある。親の時代とはだいぶ様相が異なる都立高の「下克上」について見ていこう。併せて、毎年のように動く私立併願校の新潮流も押さえておきたい。

第25回
【第1回 羽生善治さん×濱口秀司さん対談】喜怒哀楽の感情は思考やアイデアにどう影響するのか
約30年にわたってトップ棋士として活躍をつづける将棋界のレジェンド、羽生善治九段と、USBフラッシュメモリのコンセプト開発などでも知られるビジネスデザイナーの濱口秀司さんによる、異業種トップランナー対談。この第1回では、フィールドは違えど「思考の鬼」であるお二人が、「考える」きっかけやプロセス、コントロール方法などについて語り合います。
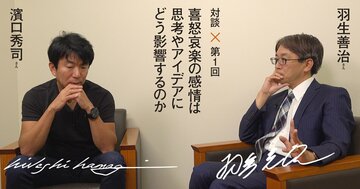
第3回
猫が飼い主をたっぷり困らせるための10の方法
全仏ベストセラーシリーズ最新刊『猫は気まぐれに幸せをくれる』から、15年間、どんな時でもそばにいてくれた愛猫が教えてくれた、もっと楽しく快適に生きる秘訣を紹介します。

第31回
昨今日本でも、非人道的な暴力事件が目立つこともあり、人の心や社会の状態が悪くなっていると感じる人が多いといいます。確かにこうした劣化を示すデータは多くあります。その背景にあるのが格差の拡大です。

金融庁のホームページで面白い求人案件を見つけた。投資教育に携わる職員を募集しているのだ。これは「社会や顧客に正しいことを伝えたい」と思っている金融関係者にとってはなかなか魅力的な仕事ではないか。そこで、筆者がこの求人で採用されたら投資教育で何を伝えるべきか、7つのポイントを挙げてみた。
