週刊ダイヤモンド編集部
台湾・鴻海精密工業の傘下でシャープは、グループの総力を挙げて劇的に業績を改善させている。2017年度は4年ぶりの最終黒字化を狙って、売り上げ拡大にかじを切った。

豊田通商が今春、大掛かりな組織再編に乗り出した。その狙いや今後の成長戦略について、加留部淳社長に聞いた。

ゴルフレッスンプロら1000人以上を巻き込んだ「ゴルフスタジアム(GS)信販問題」で、被害者の会のメンバーたちが東京地裁にGSの破産を申し立て、7月21日に破産手続き開始が決定した。恨みつらみだけで破産へ追い込んだのではない。自らの破産危機に陥るメンバーもいる中で申し立てを急いだのには、深い理由があった。

子ども向けの実験教室と言えば、夏休み恒例のイベントだが、それがバーチャルの世界に拡張されることになった。8月1日、ドイツの化学メーカーのBASF(ビーエーエスエフ)が、過去20年間続けてきた「子ども実験教室」の発展形として、インターネット上で各種の化学実験が楽しめる「バーチャル実験教室」をローンチしたのだ。

東京電力ホールディングスの先行きが、ますます見通せなくなっている。その主因は、東電柏崎刈羽原子力発電所が立地する新潟県柏崎市の櫻井雅浩市長。同市長はかねて柏崎刈羽原発6、7号機再稼働には1~5号機の廃炉が条件だと発言していたが、7月25日、正式にその意向を東電の小早川智明社長に伝えたのだ。

東京都の小池百合子知事は、築地市場の移転をめぐり、「築地は守る、豊洲を活かす」との方針を発表した。突然の方針転換に、豊洲新市場に計画されている観光施設への進出を決めていた万葉倶楽部が猛反発。トップは怒りをぶちまける。

日本労働組合総連合会(連合)が未曽有の危機に見舞われている。働き方改革の目玉メニューである「高度プロフェッショナル制度」への対応をめぐり、連合執行部と傘下の下部組織との間にあつれきが生まれているのだ。背景にあるのは、連合組織の弱体化だ。産業界も、連合混乱のとばっちりを受けることになりそうだ。

新国立競技場の土壌改良工事をしていた建設会社の社員の男性(23歳)が、1ヵ月間で約200時間の残業を行い、今年3月に失踪、自殺していた。ここ数年、建設業界の人手不足と過重労働が懸念されてきたが、遂に悲劇が起こった。今後どのような対策をとるべきなのか。遺族の代理人を務める川人博弁護士に話を聞いた。

トヨタ自動車とホンダが今夏以降、それぞれの看板といえる代表車種の新型モデルを相次いで日本市場に投入する。7月10日にトヨタが発売したカムリ、9月29日にホンダが発売するシビックだ。両車には共通点がある。いずれも初代からモデルチェンジを重ねて節目の10代目を迎えること。そして国内よりむしろ米国など海外で売れに売れ、その実績を引っ提げて日本に凱旋することだ。

エレクトロニクス・電子部品各社の2017年度第1四半期決算が出そろった。パナソニック、シャープ、ソニーとも前年同期比増収増益。特にソニーは第1四半期営業利益としては過去最高となる1576億円をたたき出した。一見順風満帆の内容だが、不穏な影が垣間見える。その最たるものが、各社が売上げを依存するスマートフォン市場の軟化の気配だ。

3094人のビジネスパーソンにチェックテストを実施して「疲労」の実態に迫った、題して「サラリーマン疲労危険度ランキング」。まずはホワイトカラーを見てみよう。

3094人のビジネスパーソンにチェックテストを実施して「疲労」の実態に迫った、題して「サラリーマン疲労危険度ランキング」。現場業務はどのような状況か見てみよう。

2017/8/12・8/19号
介護保険制度は、体が衰えていくシルバーエージが“自分らしく”生きるために整えられた“共助”の制度だ。ところが、いま、国がどんな美辞麗句でお化粧を施しても、利用者からすれば、総じて“改悪”としか言いようのない制度改革がひっそりと進んでいる。

歌に音階があり、英語に文法があるように、実は、仕事にもきちんと確立された方法がある。それがロジカルシンキングや問題解決法、フレームワークというものだ。家事にその手法を持ち込み、今年3月に「ロジカル家事」を出版した経済評論家の勝間和代氏(元マッキンゼー)に、日常的な論理的思考の方法や効率的な家事の進め方などを聞いた。

インバウンド観光客の“爆買い”需要が去り、減収減益に陥った百貨店各社。本業を支えるための多角化を模索する中、高島屋は不動産事業とシンガポールの店舗で地歩を固めつつある。

東芝の2017年3月期決算に対し、監査を担当するPwCあらた監査法人が“NO”を突き付けようとしている。8月10日までに判断が下されそうで、上場廃止の危機が、いよいよ現実味を帯びている。

賃貸住宅最大手である大東建託の営業力に“ほころび”が見え始めている――。『週刊ダイヤモンド』6月24日号「不動産投資の甘い罠」でそう指摘したところ、編集部に同社の現役社員、元社員から続々と切なる声が寄せられている。さながら駆け込み寺状態だ。彼らに共通する思いは「良い会社に生まれ変わってほしい」という一点だ――。今回は、大東建託社員の悲痛な叫び、第3弾をお届けする。
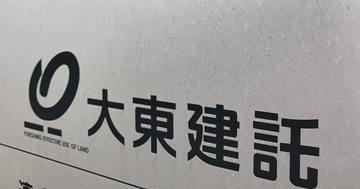
賃貸住宅最大手である大東建託の営業力に“ほころび”が見え始めている――。『週刊ダイヤモンド』6月24日号「不動産投資の甘い罠」でそう指摘したところ、編集部に同社の現役社員、元社員から続々と切なる声が寄せられてきた。さながら駆け込み寺状態だ。彼らに共通する思いは「良い会社に生まれ変わってほしい」という一点だ。今回は、大東建託社員の悲痛な叫び、第2弾をお届けする。

「30周年を迎える2020年が一つのゴール。『一番搾り』を日本のビールの本流にしていきたい」。キリンビールの布施孝之社長は、一番搾りのリニューアルを発表した今夏の説明会でビール再起への熱を込めた。「一番搾りをビールの本流に」という社長発言の背景にあるのは「トップシェア奪還」。キリン幹部はそう語気を強める。

第24回
アップルといえば、iPhone。ソニーといえば、ウォークマン。多くの企業には代名詞となる商品が付きものだが、あなたが普段利用している銀行の独自商品は、と聞かれて、連想するものはあるだろうか。住宅ローンはどの銀行でも扱っているし、投資信託などの金融商品も銀行は他社商品を売っているにすぎない。となると、お手上げという人も多いかもしれない。
