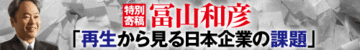冨山和彦
30歳でピークを迎えるプログラマーにおすすめの“超意外なセカンドキャリア”とは…文系の花形職種で高給です!
どんな仕事にも「旬」がある。ここ20年ほどはITエンジニアが重宝されてきたが、AIの進化が止まらないいま、かつてのスキルだけで生き残るのは難しい。だが、前職の知見を活かし、法律という新たなフィールドで力を倍増させる道があるという。株式会社IGPIグループ会長、株式会社日本共創プラットフォーム(JPiX)代表取締役会長の冨山和彦が、今後の法曹界を占う。※本稿は、内田 貴編著『弁護士不足――日本を支える法的インフラの危機』(筑摩書房)の一部を抜粋・編集したものです。

「地方創生」は日本経済再生の「本丸」だが、人手不足の時代に入り、付加価値労働生産性をどう上げるかが勝負となる。高付加価値のツアーリズムや介護などの効率化、ニッチのモノづくりを中心に外部からの経営人材受け入れやコンパクトなインフラ整備など、発想を転換した取り組みが重要だ。

生産性向上が日本全体で渇望されている。方法論としての2種類の「両利きの経営」
日本経済、そして日本企業にとって最大の課題は、人手不足だ。その解決のため、労働生産性の向上はいま、万人が望む施策である。まさにそれを目的として1955年に設立された日本生産性本部が、経営層向けに毎夏実施し、今年で66回目を迎えた「軽井沢トップ・マネジメント・セミナー」を取材した。その総合コーディネーターを務めた冨山和彦氏の講演に、フォロー取材を加えて、談話記事としてまとめた。(文/ダイヤモンド社 論説委員 大坪亮)

#5
「出世したら改革を実現する」。そう語る管理職たちが結局何もできない理由とは?特集『結果を出す管理職はみな非情である』の最終回は、リーダーのインフルエンスについて解説。ハードパワーとソフトパワーの違いとは?リーダーの本質は「権力」ではなく「人間力」である理由とは?組織を変革し、結果を出すリーダーシップの極意を学べます。

#4
パーパスやビジョンを語るリーダーが失敗する本質的な理由とは?特集『結果を出す管理職はみな非情である』の第4回は、リーダーに必須のコミュニケーション術について解説。なぜリーダーは「情に訴えしつこく」語り続けないといけないのか。合理タイプのリーダーが失脚してしまう理由とは?成果を上げるための「人と組織を動かす」技術が学べます。

#3
部下に対する中途半端な情が、最悪な結果を招く理由とは?特集『結果を出す管理職はみな非情である』の第3回は、リーダーに「非情さ」が求められる本質的理由を解説。合理と情理を兼ね備えることで初めて可能となる「人と組織を動かす」技術が学べます。
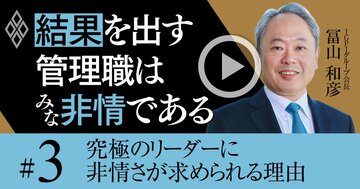
#2
なぜ多くの日本企業が、明らかに「間違った判断」をしてしまうのか?特集『結果を出す管理職はみな非情である』の第2回は、「合理的な判断」ができなくなる本質的理由を解説。合理的は判断を妨げる情緒と慣性とは?また合理的判断こそ反対にあう理由とは?優れたリーダーこそ陥る、意思決定の落とし穴が学べます。
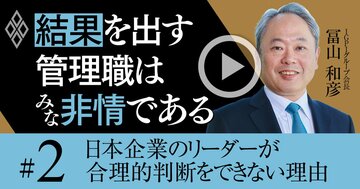
#1
企業が低迷する根本原因は、リーダーにあり!特集『結果を出す管理職はみな非情である』の第1回は、不確実性の時代に求められるリーダーシップのあり方を徹底解説。日本企業の旧来型リーダーがこれから通用しなくなってしまう理由とは?また意思決定力が軽視されてきた歴史的要因とは?管理職に必須の「人と組織を動かす」方法論を学べます。

INDEX
管理職は「非情」であれ!結果を出すリーダーの条件を徹底解説【冨山和彦・動画】
IGPIグループ会長の冨山和彦さんが、「これからの時代のリーダー論」を徹底解説。リーダーが合理的であると同時に、“情の論理”にあつくあるべき理由とは?またビジョンやパーパスを語るリーダーが失敗する理由とは?結果を出すリーダーの「人と組織を動かす方法論」が学べます。
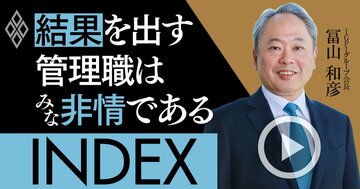
ダイヤモンド・プレミアム(有料会員)ならダイヤモンド社のベストセラーが電子ブックでお読みになれます!月ごとに厳選して提供されるダイヤモンド社の話題の書籍から、ここでは一部を抜粋して無料記事としてお届けします。全体をお読みになりたい方はぜひダイヤモンド・プレミアム(有料会員)にご登録ください!今回は2021年3月提供開始の『結果を出すリーダーはみな非情である 30代から鍛える意思決定力』。自分がトップのつもりで考え行動するリーダーシップの鍛え方をお教えします。

第5回
常に「与党」の立場で考え、行動せよ
組織や集団の主流派にいる人間こそが、革命をなし得る。現状の課題や解決に向けた複雑さと、権力の使い方や限界をよく知っているからだ。一見舌鋒鋭く批判するが、自分は火の粉を被ろうとしない無責任野党は、問題の実態や責任ある立場で直面する矛盾を知らない。自分はどちらに身を置くか考えよう。
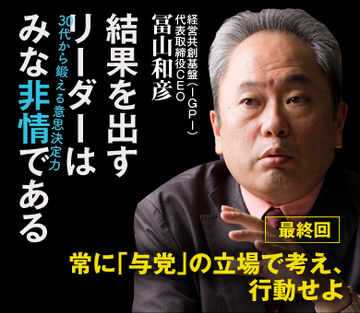
第4回
「合理」からも「情理」からも逃げるな
経営が直面する本当の苦しい決断というのは、単純ではない。合理的に考え尽くした末に何かを「捨てる」ことにこそ、戦略の本質はある。そして、その戦略を実行する際は、関係者の情理・情念を理解しながらも流されず、対応しなければならない。「合理」と「情理」の両面を見据えることが大切である。
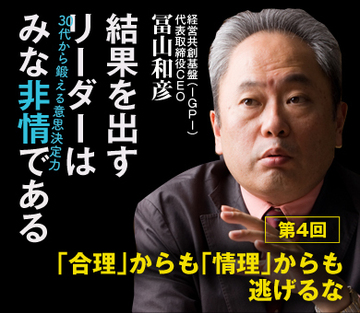
第3回
上司も社長もチームメンバーとして“使う”
あるプロジェクトを進めるうえでは、そのチームメンバーに属する者は上司であろうと部下であろうと成功に向けた駒だと考えるべきである。常に、目指す成果のために何をすべきか、という“社長”の目線で考え、何事にも取り組もう。
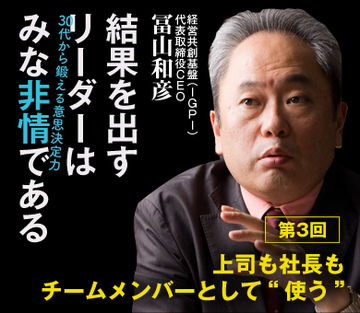
第2回
トップリーダーと現場リーダーは似て非なるものである
東日本大震災後の復旧作業など、「現場の作業員の心を一つにして同じ方向に向かって進んでいく」というリーダーシップが上手な日本人は多い。しかし、トップがすべき意思決定には痛みや犠牲が伴い、それに基づいて組織を動かしていかなければならない。先の現場力とは違った思考と行動力が求められる。
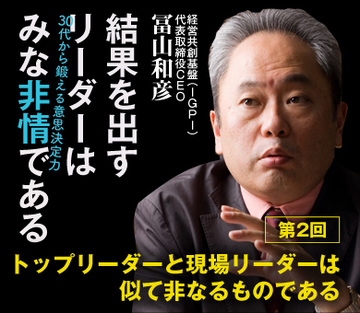
第1回
時代を動かすのは課長クラスの「ミドルリーダー」である
失われた20年を経ても、日本企業や日本は変われないのだろうか?守旧派と戦いながら会社や社会に新たなルールを敷くのは容易でない。しかし、変革への戦略を“実質的に”主導できるのは、課長クラスのミドルリーダーに他ならならない。そのために不可欠な「実行力」は若いうちからこそ鍛えられる。
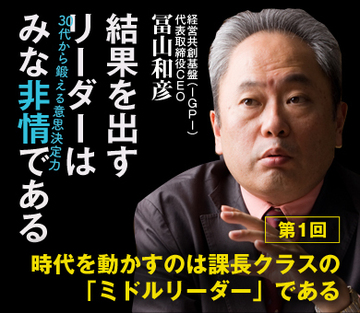
後編
産業再生機構で41社の企業再生を成し遂げた、経営共創基盤CEOの冨山和彦氏の特別講演録「経営者の条件」。後編では、経営に必要なのは「合理」だけではない、揺るぎない哲学であると説く。

前編
産業再生機構で41社の企業再生を成し遂げた、経営共創基盤CEOの冨山和彦氏の特別講演録「経営者の条件」前編。冨山氏は、経営危機に陥る企業には、ある共通項が存在する、と指摘する。

第2章
産業再生機構のトップとして企業再生支援に携わる中で浮かび上がったのは日本の「会社」というシステムの限界でもあった。
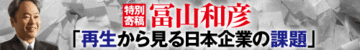
第1章
日本企業の強みと弱みとは何か?戦後未曾有の高成長の牽引車となってきた大企業の破綻、そして再生の現場で垣間見えたリーダーに求められる資質とは?