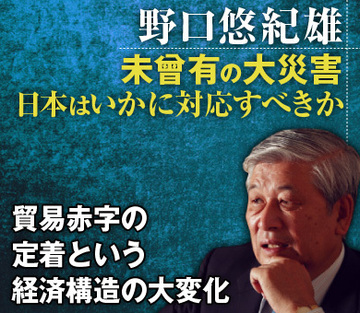野口悠紀雄
第31回
日本の貿易収支は、震災直後に大きな赤字になったもののその後回復して、6、7月には黒字になった。しかし、リーマンショック前と比べると、大きく減少している。現在、歴史的円高が続いているが、円高が輸出頭打ちの直接的な原因なのだろうか。
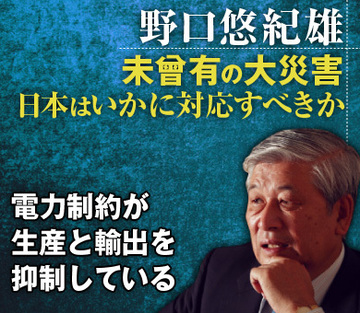
第30回
4-6月期のGDP統計の改定が発表された。ほとんどすべての需要項目が対前期比でも、対前年同期比でも減少している。復興過程が始まっているのであれば、これらはかなり高い増加率を示すはずだが、なぜ復興投資が増えないのであろうか。
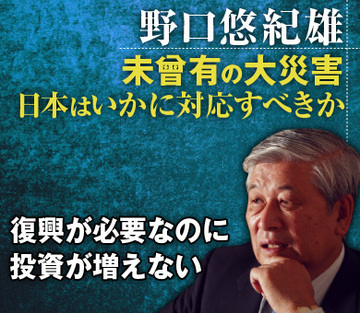
第29回
震災後、再稼働できなくなった原発が増えたため、火力シフトが進み、CO2の排出量も増えているはずだ。しかし、震災後発生したさまざまの問題解決が優先するから、環境基準達成は忘れてもよいのだろうか?
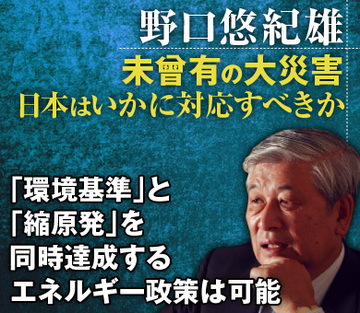
第28回
電力需要は経済成長と密接に関わっており、なおかつ政府による成長率の見通しは過大だ。したがって、今後の成長率を現実的なものに見直せば、再生可能エネルギーに過度に依存することなく、また環境基準も達成しつつ、脱原発を実現する可能性がある。
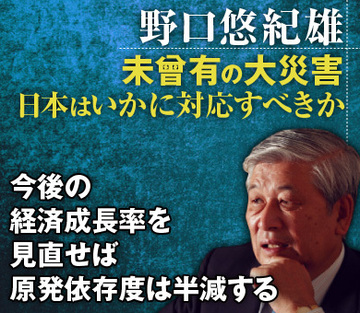
第27回
電力需要は、経済活動水準とその内容に大きく依存する。しかし、エネルギー基本計画で想定される経済成長率の見通しは過大と考えられる。もしこれを補正すれば、将来の電力需要は減り、再生可能エネルギーに過度に依存しない脱原発も実現できるはずだ。
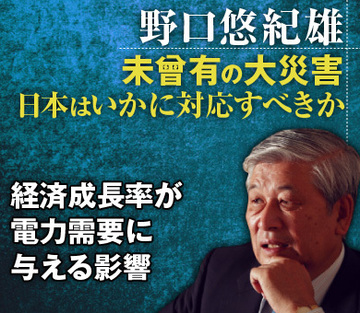
第26回
脱原発の議論においては電力需要に関する検討が不可欠だが、現実にはこの側面についての検討は十分に行なわれていない。そこで今回は、電力需要と強い相関関係がある製造業の生産水準を加味しながら、今後の原子力発電の位置づけを考えたい。
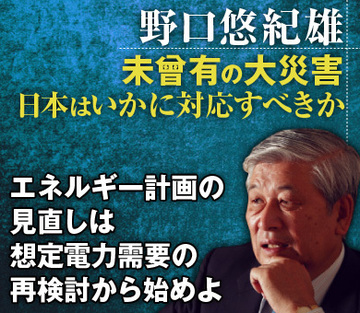
第25回
脱原発をすすめるうえで再生エネルギー拡大が焦点となっているが、コストや供給の安定性などの問題が指摘されている。では、脱原発は不可能かといえば、そうではない。需要等の見直しで、再生エネルギーだけに頼らない脱原発達成も不可能ではないのだ。
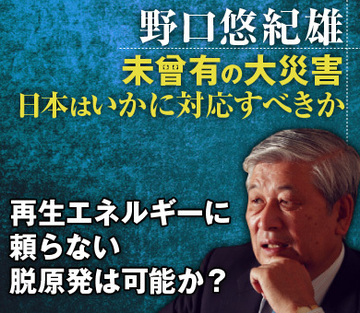
第24回
電力需要は、鉱工業生産と同方向に変動するが、変動率の絶対値は生産の変動率より小さい。つまり画期的な省電力技術が開発されない限り、円高よりもむしろ電力が今後の生産拡大に強い制約をかけていると考えざるをえない。
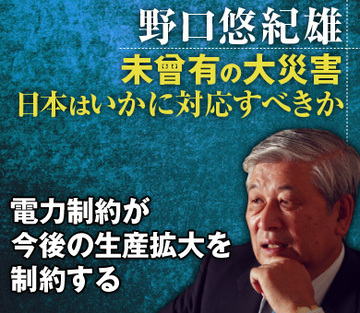
第23回
6月の貿易収支は黒字になった。ただし、黒字額は707億円に過ぎず、なんと前年比約9割減の著しい減少ぶりだ。貿易赤字に陥ったのは一時的で、黒字が正常だと考えている人が多いなか、今後の貿易収支はどうなるのだろうか。
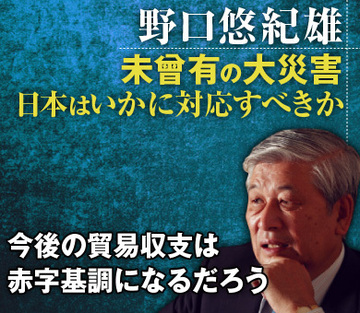
第22回
復興財源を議論する場合、財源の選択が経済活動にどのような影響を与えるかは、必ずしも意識されていない。しかし、震災後の日本経済は全体として強い供給制約に束縛されているので、マクロ的条件を勘案して財源とその影響を考えねばならない。
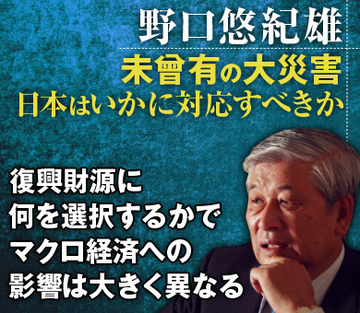
第21回
日本の貿易収支は、大震災後に赤字化したものの、6月中旬からは黒字化の兆候がある。しかし、原油価格の下落が貿易収支好転の要因とも考えられ、今後の原油価格や発電用燃料の増加によって赤字化の可能性がある。では、今後の日本の貿易収支はどうなるだろうか。
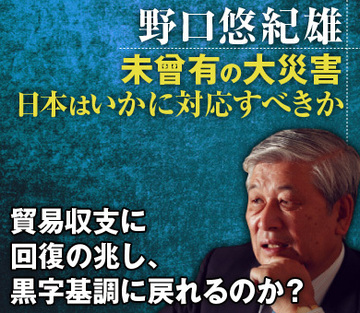
第20回
震災で自動車生産のサプライチェーンが損傷したために自動車輸出が落ち込み、日本の貿易収支は赤字になった。ただし、サプライチェーンが秋頃に回復するという予測に伴って日本経済の回復を期待する向きが多い。しかし、本当にそうなるだろうか?
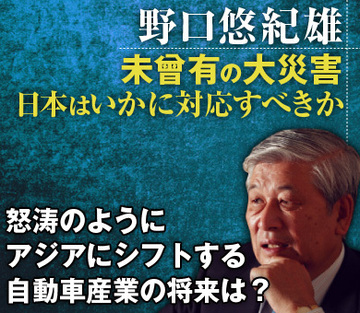
第19回
震災翌月である2011年4月の輸出総額は、前年より12.4%も減少した。品目別に見ると、なかでも乗用車は67.9%減と非常に大きな落ち込みを見せている。乗用車輸出は、なぜ他に突出して落ち込んでしまったのだろうか。
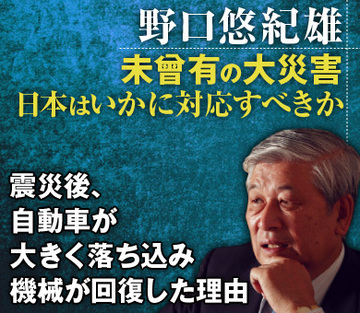
第18回
経済危機後の貿易収支改善をもたらした要因の1つは、対中国輸出の増加である。ただし、「中国に対する輸出が、今後の日本経済を支える」とは必ずしも言えない。なぜなら、輸出量が中国経済の成長に見合って増加しているとは言えないからだ。
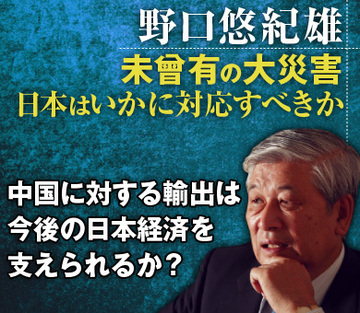
第6回(最終回)
補論:総需要・総供給モデルによる復興過程の分析
野口教授の最新刊『大震災後の日本経済』(ダイヤモンド社)第1章の全文を順次掲載。最終回の今回は、復興投資が金利や為替相場、物価にどのような影響を与えるかを「IS-LMモデル」と「総需要・総供給モデル」を使って分析する。
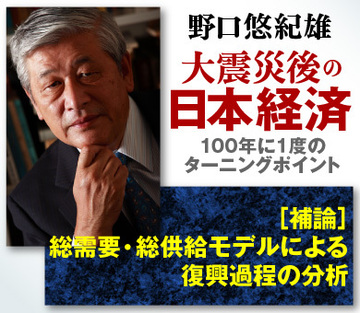
第17回
日本は、組立型製造業の輸出輸入比率が低下している反面、鉄鋼などの原料型産業の輸出・輸入比率は上昇している。現在、原子力から火力発電へのシフトにより鉱物性燃料の輸入増加が不可避だが、そのなかで貿易構造はどう変化すべきだろうか。
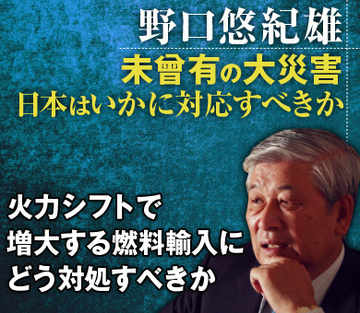
第5回
5.これまでの経済ショックとの違い
野口教授の最新刊『大震災後の日本経済』(ダイヤモンド社)第1章の全文を順次掲載。第5回目の今回は、東日本大震災が経済活動に及ぼした影響を、世界経済危機や阪神大震災など、過去の経済ショックと比較する。
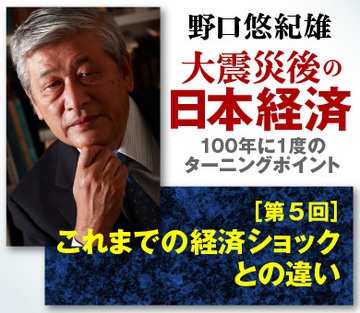
第16回
自動車の輸出激減と原油やLNGの輸入増加によって、4月の貿易収支は赤字となった。また、中長期的には生産活動の海外比率が高くなることが考えられる。それは、日本の貿易赤字をさらに拡大させるが、この傾向をどう評価すべきだろうか。
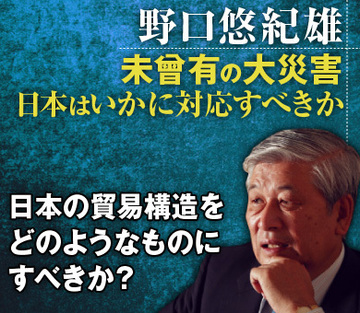
第4回
4.円高も増税も拒否すればインフレになる
野口教授の最新刊『大震災後の日本経済』(ダイヤモンド社)第1章の全文を順次掲載。第4回目の今回は、マクロ経済の需給バランスの観点から、これから本格化する復興投資にどう対応すべきかを論じる。
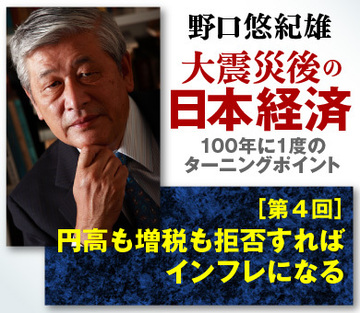
第15回
5月30日に公表された5月上旬の貿易赤字は6464億円となった。日本の貿易構造が東日本大震災によって大きく変わったことをこの数字は示している。貿易収支の赤字は今後どの程度の期間にわたって継続し、どの程度の規模になるのだろうか?