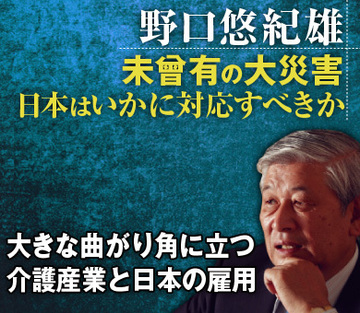野口悠紀雄
第15回
2009年以降、サービス価格の下落があった。07年以降、ほぼ継続してプラスであったが、09年6月から11年3月までかなり顕著なマイナスとなった。総合指数の下落幅増大にも寄与している。今回は、こうした変化がいかなる要因によって生じたのかを考えることとしよう。
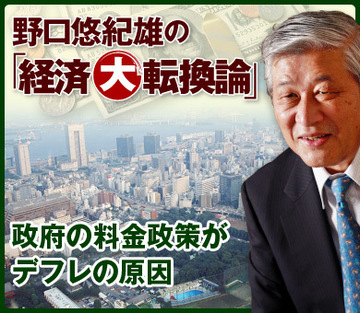
第14回
需要の動向と消費者物価の動向は、正反対だったことは、前回までのコラムで解説した。これは、「需要が不足するので物価が下がる」という考えが誤りであることを、明確に示している。

第13回
これまでの連載で、「量的緩和はマネーストックにほとんど影響を与えず、消費者物価にも直接影響しない」ことを述べた。だが、データを見ると、円安によって輸入物価を引き上げている。

第12回
2001年に行われた量的緩和はマネタリベースを増加させたがマネーストックは増加させず、物価にも影響しなかった。2008年の経済危機後、アメリカでもQE(量的緩和)が行われたが、結果は同様だった。
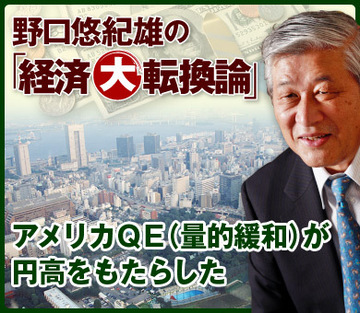
第11回
第10回連載では日銀が銀行から国際を買い上げることができたのは、利子率が低下してきたからであると述べた。では日銀が直接政府から購入、つまり日銀引き受けをすればどうか。検討してみよう。
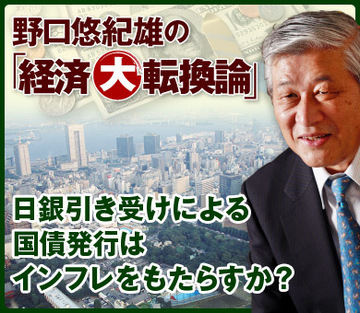
第10回
景気回復は望ましいことだ。そのために、政府や日銀はさまざまな対策をうっている。しかし、よくよく考えれば、景気回復すると国債が暴落する可能性がある。一体、どういうことなのだろうか。
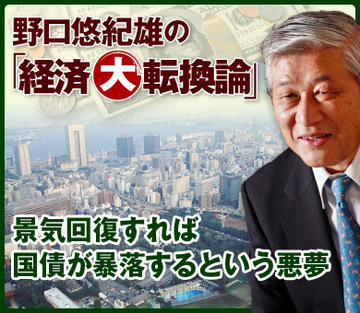
第9回
政府・日銀の為替介入をきっかけに円安が進み、2003年頃から輸出主導型経済成長が実現した。今、当時と同じような金融緩和が行われようとしている。そのためにも当時の金融緩和過程を詳細に見てみよう。
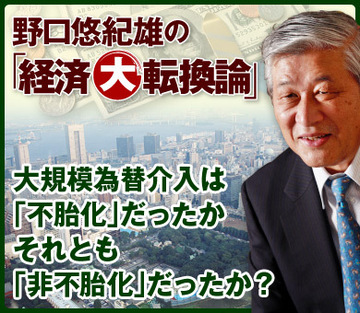
第8回
2001年から実施された「量的緩和政策」。しかし、ベースマネーは伸びたがマネーサプライは低迷し、GDPや物価に関しても効果がなかった。真の目的は難だったのか。そこで立てられる仮説は真の目的が「国債購入」ではなかったのか、ということだ。
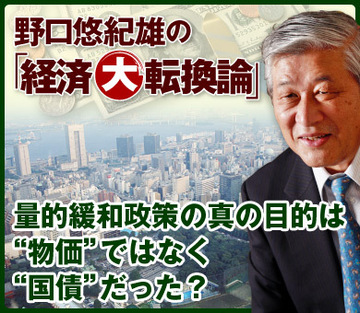
第7回
2月14日に日本銀行が行った金融緩和策で、長期国債の購入限度額が拡大、株高が進み円高に歯止めがかかった。一見、この事態は好ましいように思えるが、本当にそうなのだろうか。
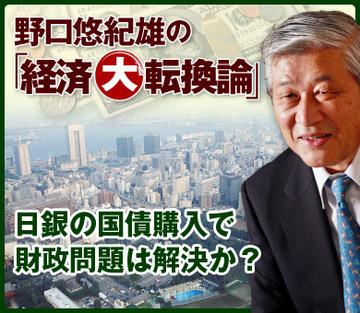
第6回
対中国輸出は日本にとって重要であることは言うまでもない。ところが、中国経済に占める日本の輸出のウエイトは、経済危機前に比べると低下している。今後、対中輸出は日本を支えるほどの存在になるのだろうか。
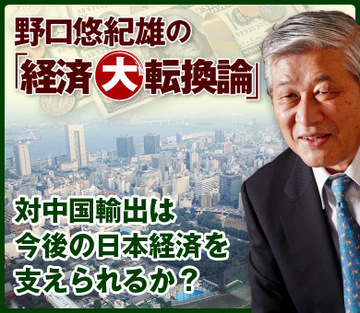
第5回
日本の電機産業は軒並み大赤字の予想だ。基幹産業として位置づけられている電機産業は、はたして生き残れるのだろうか。日本の貿易構造の変化から、電機産業と日本の産業構造の将来を推察した。
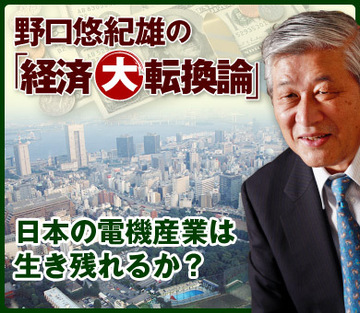
第4回
日本経済を支えてきた自動車産業。その自動車産業が補助金なしでは成り立たない産業、つまり“農業化”してしまった。いったいどういうことなのか。
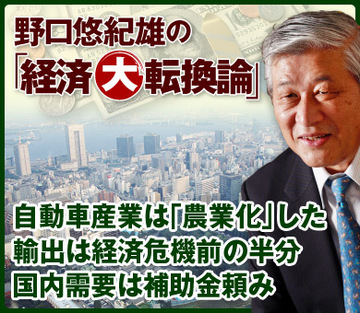
第3回
2011年の貿易赤字になったのは、日本経済が「ニューノーマル」の時代に入ったということだ。今後、日本経済は「ニューノーマル」の経済条件に対応していかなくてはならない。

第2回
野田佳彦首相は消費税増税に政治生命を賭けるとまで宣言し、増税へ向けて突き進む。財政再建が実現できるというのがその理由だ。しかし、果たしてそうなのだろうか。
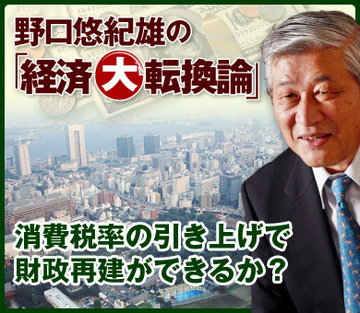
第1回
東日本大震災でもっとも大きな変化は貿易収支が赤字に転じたことである。そして、この赤字は一時的なものではなく、今後、続いていくことになる。これは経済政策全般に大きく関わる重大な変化だ。

第42回・最終回
介護産業の確立には「公的な仕組みで運営する」という、現行制度の基本的な発想を変えることが重要である。その上で、税制や金融の仕組み、製造業を直接に介護産業へ転換する仕組みを構築するべきである。
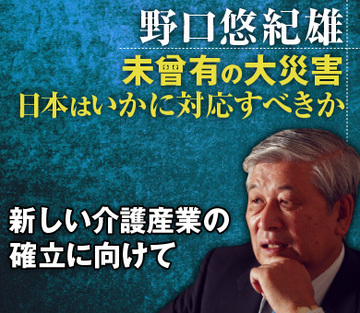
第41回
第40回で労働力不足に陥る可能性を述べた。今回はさらに労働力率の推移を加味して労働力の過不足を予測した。その結果、日本がとるべき雇用政策の方向性が見えてきた。
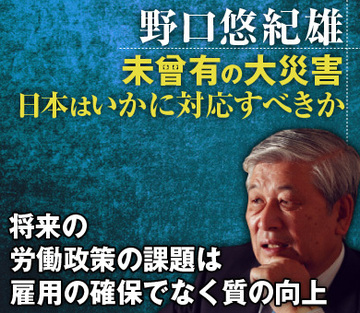
第40回
製造業で雇用が減少し、介護医療分野では雇用が増加する。一方で日本全体は高齢化で労働人口は減少する。これらはバランスするのか、それとも労働力過剰になるのか。多角的に分析してみよう。
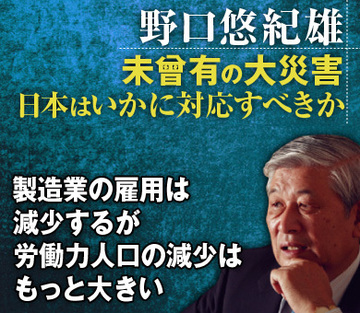
第39回
有料老人ホームは入居者が集まらず採算ラインに達しないところがある一方で、特別養護老人ホームは2~3年入居待ち。介護施設はその種類によって状況が大きく異なる。どのような問題があるのだろうか。
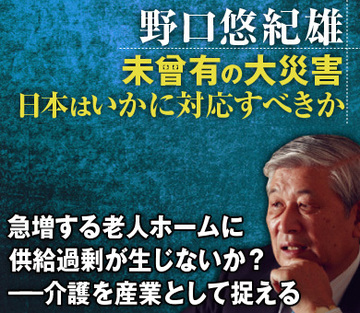
第38回
1990年代の後半以降、日本で起こった基本的な構造変化は、製造業の雇用が減り、介護の雇用が増えたことである。同時期に生じた日本の所得低下の基本的な原因は、製造業よりも平均賃金の低い介護の雇用が増加にあった点に注意が必要だ。