
安田賢治
第33回
私大文系入試は「機能不全」に?進む少子化と受験生の心構え
終わりの見えない少子化は、大学入試のあり方を根本的に変えていく。高校の進路指導もそれに合わせて変わる。新しい学習指導要領が本格的に反映されることで、入試問題自体も変わらざるを得ない。私立大は、今後も独自の入試問題を作り続けられるのだろうか。

第31回
「探究型」日本史と世界史で一変する大学入試
ここ数年で大きく変わろうとしているのが、高校の「歴史」である。古代から現代へと通史的に教えられてきた「日本史」と「世界史」も、「探究」の要素を取り入れた新しい学習指導要領の求める姿と、大学入学共通テストなどでの問われ方の変化に直面することになりそうだ。

第29回
「大学入試改革」は頓挫していなかった!次は“歴史”が焦点に
安田賢治さんが突然この世を去ってから半年近くが過ぎた。「大学入試改革は失敗した」という世評とは裏腹に、2回実施された大学入学共通テストで見られたように、改革は着実に進展している。生前の安田さんとも親交のあった石川一郎さんと後藤健夫さんが、故人の意志を継ぎ、大学入試のこれからの姿について語り合う。

第27回
“敗者復活戦”になる、2月の「私立大一般選抜入試」
2022年の大学入試を振り返ると、少子化が進む中で、構造的な変化が急速に顕在化している様相がうかがえる。特に、私立大学の合格をどのようにして得るか、という観点での進路指導が、年内での非一般入試に傾斜している。そのため2月の私大入試が、年内に合格を得られなかった受験生と国公立大の受験生の併願先という「敗者復活戦」の色合いが濃くなってきているようなのだ。

第26回
「大学合格者特集」2度の危機!個人情報保護より強烈な卒業生の圧力
20年前に施行された個人情報保護法により、合格者の実名報道が困難を来すようになった。多くの読者から期待されていた東京大合格者特集号など大学特集は、その後、どのように変わっていったのか。今年の4月10日号で創刊100周年を迎えた「サンデー毎日」での出来事を振り返りながら、大学入試の変遷についても考えてみたい。

第25回
「大学合格者特集」編集秘話、100人が泊まりがけで2000校に電話…
安田賢治さんの解説に耳を傾けることが毎年春の恒例だった。しかし、この3月に逝去されたため、2022年度入試の振り返りを一緒に行うことが不可能となった。そこで今回と次回は、生前の安田さんをよく知るお二人に語り合ってもらう。この対談の相方である後藤健夫さんと、「サンデー毎日」誌で大学合格者特集を長年共にした中根正義さんである。まずは、同誌の恒例企画を振り返りながら、故人に思いをはせたい。

第21回
【大学入試2022】女子学生と留学生が示すこれからの進学
地方創生の教育面での切り札の一つが新たな工学部の設置にある。とはいえ、失われた30年間で金欠状態の日本にとって、取り得る選択肢は限られている。女子大のあり方も含め、これからの受験生が進学先を考えるためのヒントを、40年にわたって大学受験を見つめてきた二人が語り合う。

第20回
【大学入試2022】早期合格志向と少子化には「強気」の姿勢で臨もう
2回目となる大学入学共通テストの出願も締め切られ、2022年度一般選抜型入試の幕が開けた。新型コロナ禍が小康状態のいま、アフリカから新たな変異株オミクロンがやってきた。年明けの感染状況がどのようになっているのか余談を許さないものの、少子化の進行で大学入試は親世代のような苛烈さは薄れており、強気での出願を考えてもいいかもしれない。

第14回
【大学入試2022】これからの受験生を左右する「探究」と教員の資質
新型コロナ禍で受験生の学力に一抹の不安感もある2022年大学入試。「探究」的な学びが当たり前になってきた現在、入学選抜の中身はどのように変わっていくのだろう。疲弊する地方経済は、受験生の選択にも大きな影響を与えている。そして、地方国立大の教員養成系学部に潜む闇は深い。

第13回
【大学入試2022】東大推薦入試、各大学の募集定員はどうなる?今後の受験状況を展望
大波乱だった2021年入試の結果は出そろった。これから5年間の18歳人口の推移予想を見ても、基本的に大学入試は易化していくものと思われる。大きく変わった東京大の推薦入試状況、大学の募集定員を巡る問題点、首都圏と地方との進学に関する格差など、一足早く2022年以降の大学入試を展望してみよう。今回も、大学通信常務の安田賢治氏と教育ジャーナリストの後藤健夫氏による舌鋒が冴える。

第12回
【大学入試2021】志願者ほぼ半減の横浜国大、「国公立大」入試が抱える闇
大学入試センター試験に代わって、国公立大学受験者には必須の大学入学共通テスト。その開始初年を新型コロナウイルス禍が襲った。私立大学ほどひどくはなかったものの、全体的に志願者数は減少した。中にはほぼ半減近くまで志願者数を減らした大学も出ている。ここでも、大学入試に内在する問題点をコロナ禍があぶり出した側面を見ることができる。

第11回
【大学入試2021】よもやの志願者数12%減!「私大入試」が抱える闇
新型コロナウイルス禍は、私立大学入試に潜む問題点を次々にあぶり出している。当初は、その実施すら危ぶまれた2021年度大学入試(一般選抜)は、大きな事故もなく終えることができたものの、その結果は衝撃的なものだった。志願者数だけを見ても、大学間の優勝劣敗が鮮明に表れており、これまでの経験則が通用しないような事態が起きている。

第5回
【大学入試2021】初めての「大学入学共通テスト」に潜む闇
緊急事態宣言が再発令され、対象地域が拡大される中、2021年1月16日・17日に、初めての「大学入学共通テスト」が実施される。その前身である「大学入試センター試験」の時代から、表立っては誰も触れてこなかった“闇”がここにも潜んでいた。大学通信の安田賢治さんと教育ジャーナリストの後藤健夫さんによる「Y&G大学対談」で、受験生の知らない“真実”について語り合う。

第4回
【大学入試2021】高校の進路指導に潜む闇
前回は、2020年内に合否が分かる総合型選抜(AO入試)や学校推薦型選抜(指定校推薦入試)の状況について話し合った。年明けから初めての大学入学共通テストを皮切りに、一般選抜(一般入試)が始まる。新型コロナウイルスに翻弄され、前年よりも多くの受験生が過酷な一般入試に直面することになりそうだ。ここで考えておきたいことが、こうした情勢の変化に応じた適切な動きが高校の進路指導で取れているかという問題である。

第3回
【大学入試2021】AO・推薦入試に潜む闇
新型コロナウイルス禍で教育界が混乱を極めた2020年。中でも、大学受験生は甚大な被害をこうむっている。大学と大学入試を40年近く見つめてきた旧知の間柄でもある大学通信の安田賢治さんと教育ジャーナリストの後藤健夫さんによる「Y&G大学対談」が、年内に行われている入学者選抜の底に潜む闇に切り込んだ。

過去9年間で志願者がほぼ倍増した東洋大学。これは、過去20年にわたって頻繁に手がけてきたキャンパス改革や学部学科増設など、不断の努力が実を結んだからだ。進学校の教師たちも一目置く、東洋大の「改革力」に迫った。

4年連続志願者数が日本一、全国の高校教諭たちからも「改革力ナンバーワン」と評価されている近畿大学。従来の大学にない発想で改革を進めていることに加え、それをきちんと広報していくという戦略が奏功しているのだ。
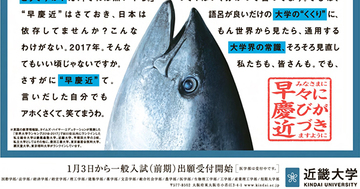
自他ともに認める日本最高峰の東京大学が、矢継ぎ早に入試改革を手がけ、高校の進路指導教諭や予備校関係者を驚かせている。今年からスタートした推薦入試に加えて、来年からは女子学生に家賃補助を開始する。東大の狙いは一体どこにあるのだろうか?

第12回・最終回
私立中高一貫校を選びには先入観や誤解が常につきまとう。情報の多寡や一般的な先入観、学校ごとの誤解…これらを排除して、本当に我が子に合った学校を選ぶにはどのような点に注意すればよいのだろうか。
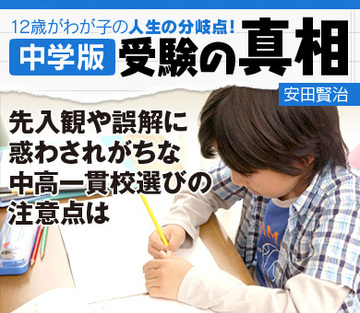
第11回
一貫校は大きく進学校と付属校の二つに分かれる。進学校は当然のことながら、入試を経て大学に進学を目指す学校。一方、付属校は併設大へ優先的に入学できる学校だ。付属校を選ぶと中学入学の段階で、大学までの進学がほぼ決まることになる。
