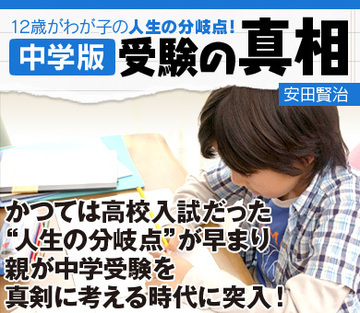安田賢治
第10回
いよいよ学校説明会のシーズンが始まった。ピークは秋になるが、受験直前の1月に開催する学校も少なからずあるという長丁場である。志望校がどんな学校かを知るいちばんいい方法が、この学校説明会に参加することだ。
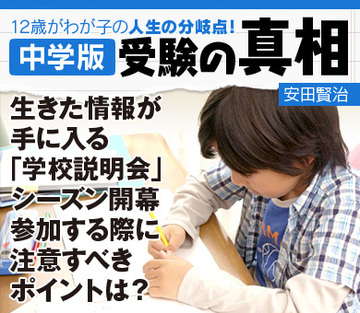
第9回
一貫校の大学への合格状況に詳しい父母は多いが、さらに先の大学卒業後の進路について詳しいかというと、それほどでもない。就職は、かなり先の10年後のことと思っている人が多いからなのか。
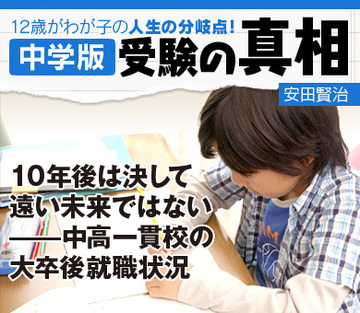
第8回
今年の一貫校の大学合格実績がほぼ出揃った。大学合格実績は翌年入試の志願者数増減に直結する。とりわけ影響力の大きいのが東京大学だ。最難関に合格者がいるということは、確かな教育力がある証しに他ならない。
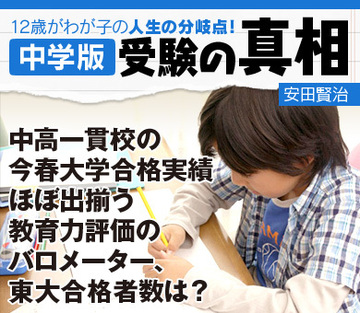
第7回
今年の首都圏の中学受験の受験者は約5%減ると見られていたが約1.9%の微減にとどまり、受験率、受験生1人当たりの併願校数も昨年とほぼ同じだったという。厳しい経済不況の中でも私立中人気は根強かったことになる。
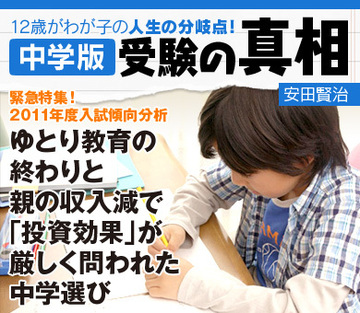
第6回
中学受験は塾通いが大前提となる。高校受験の場合と違い、公立小学校の先生は頼りにならず、塾頼みにならざるを得ないからだ。それだけ塾選びは大切だ。それでは、どう塾を選んでいけばいいのだろうか。
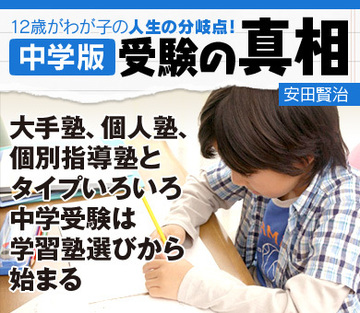
第5回
今年の中学入試は「動向がつかみにくい」と言われている。大手進学塾主催の“3大模試”のデータからでは上位層の動向が見えなくなったからだ。そこで今回は、読みにくい2011年度の入試を分析してみよう。

第4回
いよいよ受験が近づく12月からは、親子ともども精神的な負担が大きくなる。どんな試練が待ち受けているのか、準備、入試本番、合格、入学、学校生活、そして3年目に訪れる転機までを、流れに沿って見てみよう。
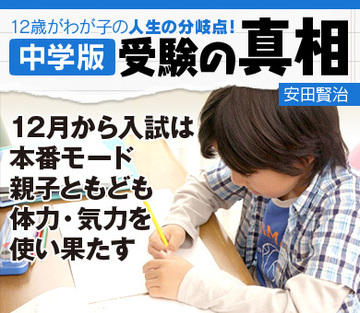
第3回
中学受験はいわゆるピアノや水泳などの習い事の延長線上とは考えないほうがいい。子ども一人が頑張る個人戦ではなく、家族全体で合格を目指す“団体戦”なのだ。そこでは家族それぞれの役割分担、負担が求められる。
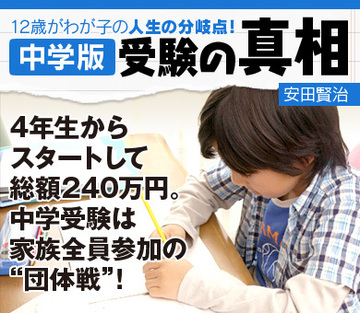
第2回
私立中に入学しながら、公立中に転校してしまう子どもがいるが、親としても中学入学はゴールではなくスタートだとしっかりわきまえておくことが必要だ。もっとも注意して見極めるべきは、入学する学校への適性だ。
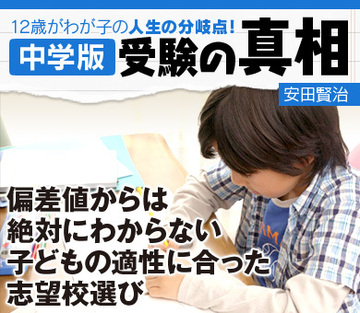
第1回
なぜ、今、中学受験なのだろうか。中学受験が増えた大きな理由は、公教育への不信。ゆとり教育に不安を覚えた保護者が、私立中を選んだのが始まりだ。高校入試がない一貫教育校の環境で、大学進学に備えたいと考えたのだ。