
高橋洋一
第24回
ギリシャ国債のデフォルト(債務不履行)危機が深刻化している。ギリシャ問題を複雑にしているのは、ギリシャの特殊性とユーロという共通通貨制度だ。歴史と最適通貨圏理論を土台に、問題の本質を読み解いてみよう。

第23回
朝霞公務員宿舎の建設は野田首相の決断で建設が凍結された。だが、これは単なる結論の先送りに過ぎない。国有財産はできるだけ売却し、必要であれば政府がそれを借り上げる。その方が法人税収まで考えると、ずっと国全体のためになる
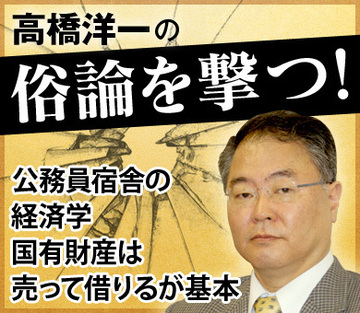
第22回
増税一直線の野田政権は、着々と増税の環境作りをしている。枝野経産相が人口減少下では低成長は避けられないといえば、五十嵐財務副大臣は都合のよいデータを使って、財政危機を煽っている。政府発表のデータについては疑ってかからないと、誤った結論を導く。
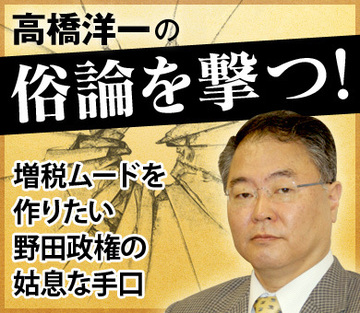
第21回
野田新政権は財務省の戦略通りに「増税一直線」。ホップ、ステップ、ジャンプの増税3段跳びの絵姿が浮かび上がってくる。しかし、復興財源にしろ、社会保障財源にしろ、増税に代わる財源はある。そのことを示そう。
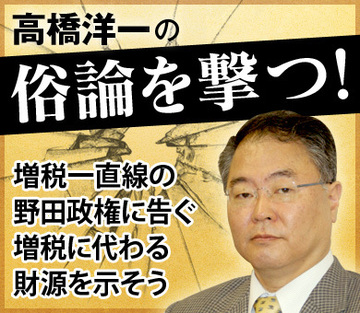
第20回
与謝野馨経済財政担当相は、インフレによる財政健全化策は俗論であるという。だが、過去15年間の税収弾性値は異常値処置したとしても3程度はある。つまり物価上昇によって、名目成長率が高まれば、財政再建は容易になる。それは過去の実績が示している。
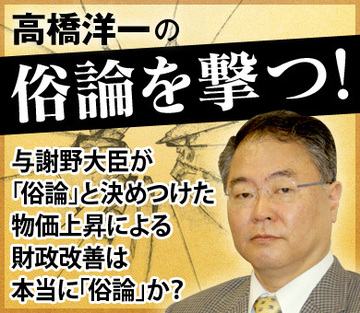
第19回
円高傾向が続いている。だが、マスコミなどの”俗論“では、その理由がわからない。為替レートを決める最も大きな要因は、通貨同士の相対的な「量」である。その意味で、円高は政府・日銀の怠慢が生み出している。
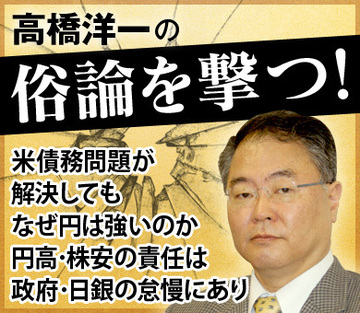
第18回
「原子力損害賠償機構法案」は、民主・自民・公明3党の修正合意が成り、8月上旬にも成立する見通しだ。その中身を見ると、「2段階方式」で東電の破綻処理もありえるように見えるが、これは欺瞞。修正は国民負担を増やす改悪である。
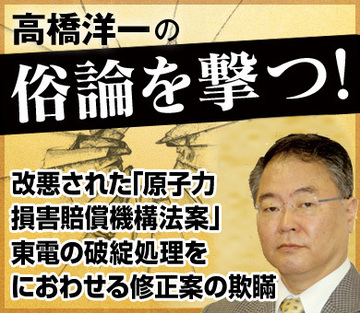
第17回
経産省の現役官僚の古賀茂明さんが、経産事務次官から「肩たたき」を受けている。民間会社なら取締役にも相当する高級官僚は首になってもいいのだが、その制度がない。古賀さんを首にすると、官僚たちが最も嫌う「身分安全保障制度」を変えなくてはいけないというジレンマに陥っている。
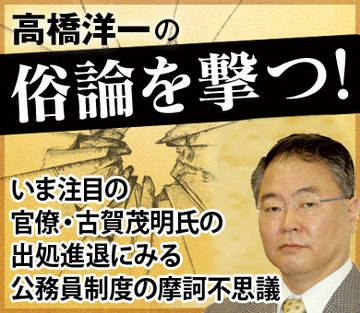
第16回
菅首相は唐突に自然エネルギーへの転換を言い出したが、それは政権の延命策に過ぎない。なぜなら、所信表明演説ではその他大勢の扱いだからだ。加えて、ご執心の「電力買取法案」にも、経産省・電力会社の思惑が反映されている。
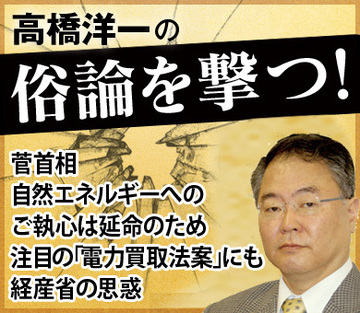
第15回
6月2日の「税と社会保障の一体改革案」で、消費税引き上げの方針が明らかになった。この考え方は財務省がバックにいるのだが、消費税の社会保障目的税化は理論的に正しいとはいえない。社会保障で重要なことは再配分機能と負担と給付の明確化。この観点から、政府の改革案を評価してみよう。
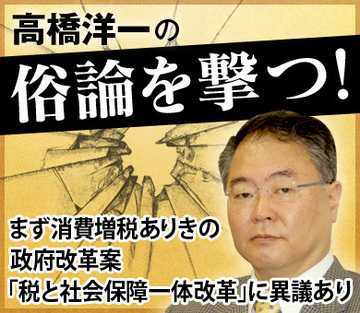
第14回
民主、自民が提出した復興の基本法案は共に中身がない。依然として中央集権思考にとらわれているからだ。道州制特区推進法を使えば、現在でも実質的な「道州制」が実現できる。これによって三ゲン(権限、財源、人間)を被災地に与えるべきだ。
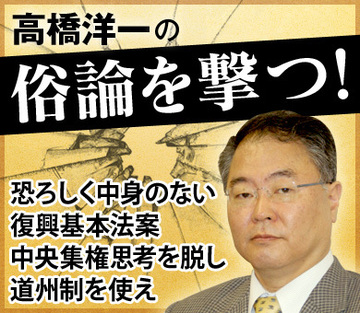
第13回
原発事故に伴う賠償スキームの議論が大詰めを迎えている。現在検討されている政府案は東電を温存し、賠償負担を国民に転嫁するもの。東電の株主、債権者にも負担を負ってもらい、資産売却も活用すれば、国民負担を少なくし、電力料金引き下げも可能な処方箋が描ける。

第12回
「復興増税、国債の日銀引受禁じ手」論は正しいのか。現状の財政法、今年度予算を前提としてもなお、日銀には18兆円もの国債引き受け余力がある。通貨、国債の信認低下論は、増税向けた財務省の学者・マスコミ・国民の洗脳策である。
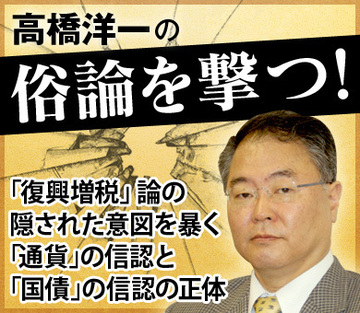
第11回
東日本大震災の復興財源を巡る議論が活発化してきた。さまざまな増税論が出ているが、まずは国債発行による調達がセオリーだ。国債を使えば負担が分散化されるからである。現状では、これを日銀が引き受ければ、経済効果はさらに大きくなる。

第10回
東北関東大震災の被災地を支援しようと、義援金の動きが高まっている。その場合、「ふるさと納税」制度が活用できる。どの自治体にも送れるうえに、税額控除も適用されるからだ。今のふるさと納税を拡充すれば、人々の善意が震災復興支援につながり、国民に連帯ができる。
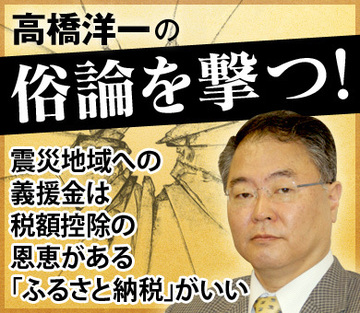
第9回
新興国のインフレから資源価格の上昇まで、その原因は米国の量的金融緩和でマネーが世界にあふれ出したためだと解説されている。本当にそうか。国際金融の為替理論やトリレンマを知っていれば、波及のメカニズムは金融政策の自由度の違いを通じて起こり、新興国に原因があることがわかる。
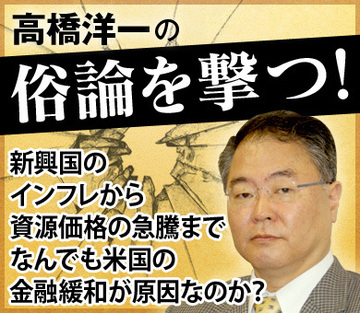
第8回
白川日銀総裁は最近講演で、人口減少が潜在成長率の低下を招き、潜在成長率が下がるから物価も下がると述べている。しかし、人口減少の影響は小さいうえ、予想インフレ率の低下が潜在成長率の低下を招いているのではないか。とすれば、金融政策によってデフレは解消できる。
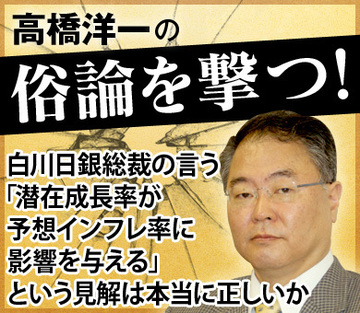
第7回
菅総理は税・社会保障改革と並んでTPPにも強い意欲を見せている。その影響については、主要官庁ごとに試算も大きく違う始末。そこで貿易自由化の判断基準と農業が生き残るための条件を考えてみる。

第6回
菅政権が与謝野馨氏を経済財政担当大臣に据え、消費税増税に向けて走り出した。だが、そもそも所得再配分機能を担う社会保障の財源に、消費税を充てるのはおかしい。それは社会保障を人質に消費税を上げるための屁理屈にすぎない。
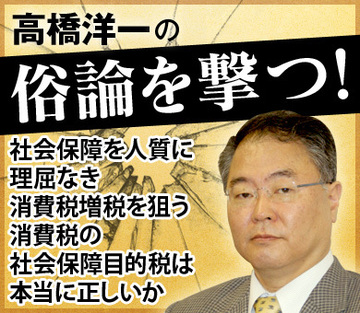
第5回
このところ日本のデフレは、人口減少による需要の減少が原因という議論が勢いを増している。しかし、この議論はデフレ=一般物価の低下を個別価格の低下と混同している面があるうえ、実証的に検証しても、一般物価の低下と人口減には関係がないことがわかる。
