
高橋洋一
第102回
日銀の黒田東彦総裁は16日、大阪市内で講演した。消費増税は新たな景気の下振れ要因ではないというこというだが、その内容を読み解くと、2つの点で矛盾がある。今となって景気後退を防ぐ最善の手は、5%への消費減税だ。

第101回
今回の安倍内閣改造では、増税シフトという解説が多い。確かに消費税再増税「なし」は政治的にはギャンブルだが、「なし」にも対応できる配置になっている。久々に老獪な政治家人事を見たような気がする。

第100回
今年上半期の経常収支が初の赤字となり、注目を集めている。だが、経常赤字=悪というのは短絡的で、経常赤字と金利は無関係だ。むしろ問題は財政赤字だが、財政再建の手法も増税より経済成長が王道である。
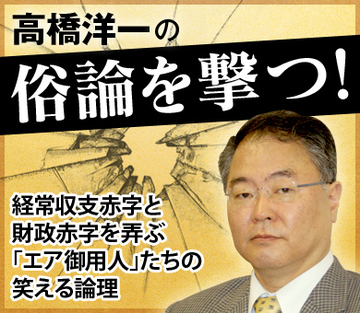
第99回
景気情勢は出てくる指標によってまちまちの結果になっている。当面の景気にとって、金融政策と財政政策の動きがカギを握っているのだが、前2回の消費税増税と異なり今回はネット増税だ。景気に悪影響がないはずがない。

第98回
このところ発表が続いた景気関連指標をみると消費、住宅投資、機械受注とも大きく悪化している。にもかかわらず、政府は7月の月例経済報告で景気判断を「上方修正」した。すでに消費税の再々増税のうわさも飛び交っている。

第97回
消費税増税の影響が少しずつ出てきているようだ。1世帯当たりの消費支出は実質で前年同月比8.0%減。1981年以降の33年間では、最悪だった東日本大震災直後の2011年3月に次ぐワースト2位の数字だ。
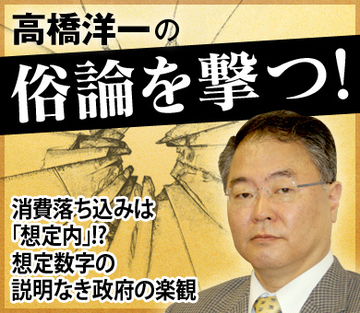
第96回
政府が骨太の方針で法人税減税を打ち上げた。が、財源論に収支していては税率はぎりぎり20%台まで下げるのが精いっぱい。二重課税を廃止し、税執行の仕組みを大胆に改革すれば、10%台を実現できる可能性がある。
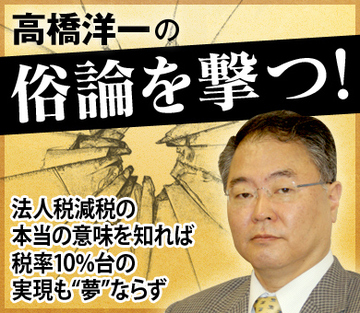
第95回
欧州中央銀行(ECB)が「マイナス金利」の導入を決めた。マイナス金利も量的緩和も狙いは同じ。だが、政策効果は量的緩和の方が大きい。では、なぜECBはマイナス金利を選んだのか。そこにECBの苦境が覗く。

第94回
岩田規久男日銀副総裁が言うように、現在のインフレは日銀の金融政策の効果によるディマンド・プル型だ。問題はこれから。消費税増税の影響は景気が腰折れした1997年型に近づいているように見える。

第93回
安倍総理は、15日に安保法制懇から提出される報告書を踏まえて、政府としての検討の進め方の基本的方向性を示す。本稿執筆時において、まだ確認できていないが、各種情報から集団的自衛権を考えるための基礎知識を提供したい。

第92回
去る4月28日、財政制度等審議会財政制度分科会に、「我が国の財政に関する長期推計」が報告された。「2060年度 債務残高は8000兆円余に」という数字に焦点が当たっているが、推計の前提条件を検討すると、増税路線をひた走る財務省の思惑が透けて見える。
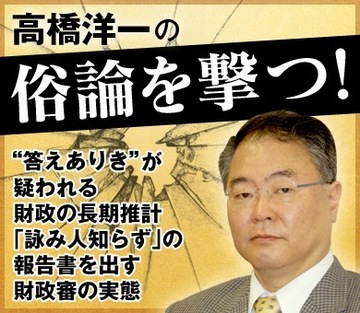
第91回
STAP細胞問題における理研と小保方氏の関係に対して、組織の管理責任を問う声も強い。ただ、それはサラリーマン的な視点によるもので、研究者の視点に立ってこの問題を理解しないと、問題の本質を見逃してしまう。

第90回
4月1日から、とうとう消費税増税が始まった。金融緩和の足を引っ張る消費税増税は「景気が本格的に良くなる前」なので失敗になるだろう。そうした状況下、日銀が「短観」の中で「企業の物価見通し」を新設した。その狙いは何か。

第89回
20日は、日銀の黒田総裁が就任してちょうど1年。物価上昇率は及第点だが、GDP成長率は下振れしている。今後の最大のリスクはもちろん消費税増税だが、さらに、「女性の社会進出促進」を隠れ蓑に、政府・財務省は所得税改悪で増税を狙っている。
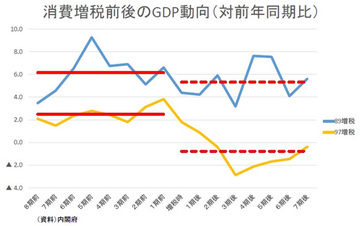
第88回
中国のシャドーバンキングが行き詰まりをみせ、連鎖的な金融・経済危機、リーマンショックの再来を世界はおそれている。バブル崩壊後の対処法はあるのだが、それを拒むのは共産党一党独裁から発生する政治リスクだ。

第87回
集団的自衛権の政府見解に大きな役割を果たしていたのが内閣法制局である。一般の人にはなじみがないこの局の権威の背景を検証すると、「官僚内閣制」を支える構図が浮かび上がってくる。
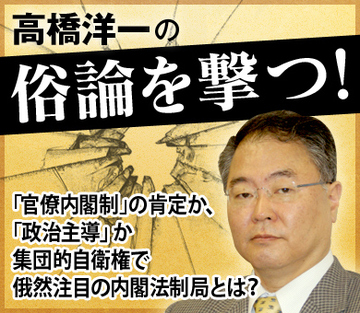
第86回
今金融界で話題になっているテーパリングに動揺する新興国市場とイエレン新FRB議長の課題について、書いてみよう。市場関係者が慌てるのは、彼らがマクロ経済の基本的な「関係式」からではなく、「人」から政策変更を「占って」しまうからだ。

第85回
細川・小泉元首相連合が唱える「原発ゼロ」は原発を再稼働させないという意味だ。それでは、原発が無価値となり東電は債務超過に陥るだろう。原発は民間が運営するにはリスクが高すぎる。ここは東京都が原発を買い取ることを提案したい。
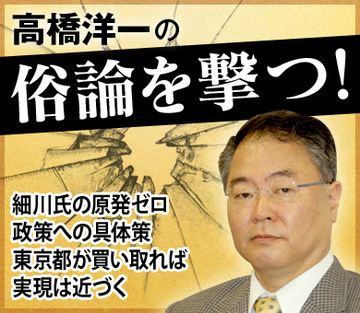
第84回
今年は4月に消費税増税という大きなイベントが控えている。ここまで順調に効果を発揮してきたアベノミクスの行方はどうなるのか。新年にあたって、それを見極めるためのポイントを解説しよう。

第83回
政府は、24日、総額が過去最大の95兆8823億円となる2014年度予算案を閣議決定した。その内容を見ると消費増税は「財政再建」のためではなく財務省の「歳出権の拡大」のためであることがわかる。予算の推移を追うことで、この主張を裏付けてみよう。
