
翁 邦雄
日本銀行が、YCCの柔軟化に踏み切った。次の焦点はマイナス金利をいつ解除するか、である。現在のフォワード・ガイダンスに従えば、物価上昇率が2%を超える状態が相当程度続いてもマイナス金利を継続する可能性がある。しかし、それはインフレに苦しむ国民からの信頼を失わせるリスクがある。

日本銀行の新総裁に植田和男氏が就任し、新執行部がスタートした。日銀の金融政策変更に関心が集まる中で、国際的な金融不安に遭遇した例としては1987年のブラックマンデーがある。金融不安は日銀新執行部の政策にどんな影響を与えるのか。

【翁邦雄・元日本銀行金融研究所所長に聞く】日銀の金利引き上げが金融政策正常化につながらない理由:「YCC手直しの内容」を検証
日銀がついに2022年12月20日野金融政策決定会合で、事実上の金利引き上げに踏み切った。これは金融政策正常化への一歩となるのか。元日本銀行金融研究所所長で、『金利と経済――高まるリスクと残された処方箋』などの著書もある翁邦雄氏による寄稿の後編をお届けする。

【翁邦雄・元日本銀行金融研究所所長に聞く】日銀の「超低金利固定」からの脱却はなぜ「必要だが困難」なのか
日銀がついに2022年12月20日野金融政策決定会合で、事実上の金利引き上げに踏み切った。これは金融政策正常化への一歩となるのか。元日本銀行金融研究所所長で、『金利と経済――高まるリスクと残された処方箋』などの著書もある翁邦雄氏の寄稿を2回に分けてお届けする。

【翁邦雄・元日本銀行金融研究所所長に聞く】円安構造の固定化であきらかになる金融政策の不都合な真実
「円安がGDPを押し上げ、日本全体にプラスに働く」というのは本当か? 為替レートの変動によって、その受益者と被害者はどの程度入れ替わっているのだろうか。元日本銀行金融研究所所長で、『金利と経済――高まるリスクと残された処方箋』などの著書もある翁邦雄氏が、長期的に為替レートの推移をみて受益者と被害者を分析した。

【翁邦雄・元日本銀行金融研究所所長に聞く】「急速な円安の進行は好ましくない」という日銀の真意
日銀の黒田東彦総裁が最近繰り返している「急速な円安の進行は、企業の経営計画に不確実性をもたらし好ましくない」というフレーズにはどのような含意があるのか。その真意について、元日本銀行金融研究所所長で、『金利と経済――高まるリスクと残された処方箋』などの著書もある翁邦雄氏に聞いた。

【翁邦雄・元日銀金融研究所所長に聞く】インフレはそれ以上に賃上げ率を高める、という幻想。国民の求める「物価安定」とは何かを考え直す
黒田日銀総裁が2013年に就任した際「グローバルスタンダード」と強調していた2%のインフレ目標。ようやくそれに達しようとしている今、国民の強い反発にさらされている。いま、国民の求めている「物価安定」とはなにかをもう一度考える必要がある。

【元日銀金融研究所所長・翁邦雄氏に聞く】円安はどこまで進むのか?「後出しじゃんけん」になっている日銀の言い分
円安はどこまで進むのか? 元日本銀行金融研究所所長で、『金利と経済』などの著書もある翁邦雄氏に、政府・日銀は現在の急激な円安に対してどのような対処をしうるのか、円安はどこまで進みうるのか、などをまとめた緊急寄稿を寄せてもらった。

新型コロナウィルスの感染拡大を受け、思い起こさせられるのは1970年代の狂乱物価である。上尾駅の騒乱、千里ニュータウンのトイレットペーパー・パニック、豊川信用金庫の取り付け騒ぎなどが起きた。事態の収束が見通せない中、日本経済全体へのインパクトや必要な対応、「日本売り」の可能性などについて、元日銀金融経済研究所所長の翁邦雄・法政大学客員教授に緊急寄稿いただいた。

第11回
2017年ベスト経済書3位受賞『金利と経済』著者・翁邦雄氏インタビュー
大規模な金融緩和策をとってきた米連邦準備制度理事会(FRB)と欧州中央銀行(ECB)が“出口”に向かいはじめ、政策の軸足を量から金利に移してきた日本銀行の動向にも注目が集まるなか、書籍『金利と経済 高まるリスクと残された処方箋』が「週刊ダイヤモンド」の「経済学者・経営学者・エコノミスト111人が選んだ2017年『ベスト経済書』」で第3位に選ばれました。これを記念し、著者である元日銀金融経済所長の翁邦雄氏に、本書執筆の狙いや異次元緩和以降を見据えた注目点などについて聞きました(『週刊ダイヤモンド』2017年12/30・2018年1/6新年合併号の232ページより転載)。

第10回
過大債務の実態は不変 銀行課税リスクは避けられないスティグリッツ教授の「日銀保有国債の無効化」提案
ジョセフ・スティグリッツ米コロンビア大学教授が、3月14日の経済財政諮問会議で行ったプレゼンテーションが反響を呼んでいる。同教授の提案の狙いを考察し、その実現方法と効果(副作用)を検討してみよう。これは、『金利と経済』でも触れた、「統合政府という観点から財政コストを考える」点の応用問題ともいえる。

第9回
米国金利が上昇傾向にあるなかマイナス金利と銀行経営を考える
2016年1月末に日銀がマイナス金利政策導入を発表した際、銀行株が急落した。マイナス金利政策は、地銀などの経営や金融システムにどのような影響を与えるのか。長期金利上昇の可能性がささやかれるなか、あらためて検討してみる。

第8回
異次元緩和が意図せず招いた積極財政論の台頭日本が人口ペシミズムを乗り越えるのに必要なこと
安倍首相が「アベノミクスで大事なのは“やってる感”」と語ったそうだが、「やってる感」を醸成する政策だけでは、日本経済の隘路は解消しない。なにより人口減少・高齢化を迎えた日本の社会経済の中長期的な姿を踏まえて、健全な自然利子率の上げ方について考える必要がある。そのためにはどうすればよいのか。クルーグマンの意見や財政拡張の是非など、とりうる策について検証する。

第7回
自然利子率の低下を金融政策で追いかけると生じる「不都合な真実」:住宅投資の盛り上がりに期待してよいか
自然利子率の変化に対応して実質金利を誘導し、景気変動の振幅を小さくし安定化させる、という政策は景気安定化の観点からみて望ましい。しかし、自然利子率が趨勢的に低下する環境下では大きな問題をはらむ。その理由について、自然利子率や実質金利誘導の基本に立ち返って解説していく。

第6回
金融政策による期待へ働きかけはなぜ失敗したか:クルーグマンが変心した理由
中央銀行の無責任さをアピールすることで期待インフレ率を上げる、という問題提起を最初に行ったのは、1998年のポール・クルーグマンによる「金融政策による期待への働きかけ」という政策提言であった。なぜ、それがうまくいかなかったのか。クルーグマンの認識変化を軸にわかりやすく解説する。

第5回
「シムズ理論」を使うと物価安定は破壊される期待に働きかける「無責任」政策の危険性
2016年11月15日付の『日本経済新聞』で、金融緩和主導のアベノミクスの理論的支柱とされ、財政規律毀損の観点からヘリコプターマネーに否定的な論陣を張っていた浜田宏一・内閣官房参与の発言が大きな反響を呼んだ…

第4回
本当に将来の増税を回避できるのか?ヘリコプターマネーの効果を考える
日銀が国債を全部買い上げても、統合政府の利払い負担が減るとは限らない。それなら、中央銀行当座預金を使わず、直接銀行券を使ったらどうか。銀行券ならいくら発行しても利払い負担は生じないのではないか。これは、ミルトン・フリードマンのヘリコプターマネーの思考実験どおりの政策を実施したらよいのではないか、という議論になる。その可能性と効果を考えてみたい。

第3回
日銀が国債をどんどん買って行き着く先は「永遠のゼロ」か、銀行課税か?
日銀が量的緩和で大量の国債を買い続けてきた結果、民間が保有している国債が激減している。だから、これから金利がかなり上がることがあっても、政府から民間への利払いは少なくて済み、財政危機は起きにくくなっている、という見方がある。果たして本当だろうか。<詳しくは新刊『金利と経済』でご覧いただけますが、同書で取り上げたトピックに一部手を加えて、ご紹介していきます>

第2回
レーガノミクスとの共通点と相違点から考えるトランプノミクスが日本に与える影響とは?
日銀のいわゆる異次元緩和政策は、目新しい名称を量産し、マイナス金利政策を経て、イールドカーブ・コントロールに到達した。これらの政策はいったいどのようなもので、日本経済にどのような効果と副作用をもたらすのか。さらにトランプの登場でいっそう関心の高まる財政政策だが、日本への影響は?「金利」を軸にそうしたさまざまな問題を解きほぐす『金利と経済』から一部をご紹介していく。
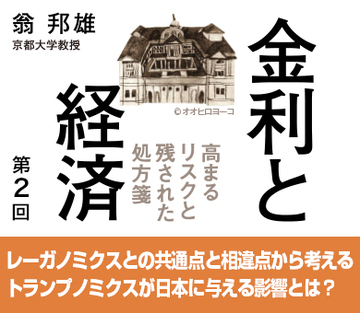
第1回
長期金利抑え込みか、円安抑制か?トランプ登場で迫られる究極の選択
トランプの登場により、日本の金融政策を取り巻く状況は大きく変わった。トランプノミクス期待で米国金利が急騰し円安が急激に進行する一方、大統領当選後もトランプが日本や中国の通貨安誘導を批判し続けたからだ。そっとしておきたい円安が、対米関係の焦点のひとつになってしまった。
