上田惇生
第140回
一つの市場に焦点を合わせるほど事業はよりよくマネジメントできる
多様な製品、技術、市場を持つ企業にとっては、単なる分権化では十分ではない。別個の事業として分離していく必要があるとさえドラッカーは言う。

第139回
人の強みではなく弱みに焦点を合わせる者に、マネジメントの資格はない
経営が本気であることを示す決定打は、人事において断固人格的な真摯さを評価することである。リーダーシップが発揮されるのは人格においてであり、人の範となるのも人格においてだからである。

第138回
リーダーシップはうつろいやすく短命である
リーダーシップは確固たりえない。市場や情報というものは、誰の専有物でもない。いかなるリーダーシップも一時的な優位性にすぎない。物理の世界と同じように、企業の世界においてもエネルギーは拡散する。

第137回
大事なものは地位ではなく責任である
成功の鍵は責任だという。自らに責任を持たせることである。責任ある存在になるということは、真剣に仕事に取り組むということであり、仕事にふさわしく成長する必要を認識するということである。
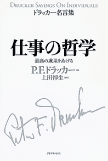
第136回
今日の姿ではこれからの30年を生き延びられない
この壮大な転換期において社会の安定を確実なものにするには、既存の組織が生き残り、繁栄してくれなければならない。そのためには、あらゆる者が起業家として成功するための方法を学ばなければならない。
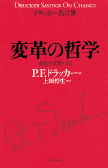
第135回
あえて変化の先頭に立ちその生み手となる
今日のような乱気流の時代、200年に一度という大転換期においては、変化が常態だとドラッカーは言う。この変化の時代を乗り越える唯一の方法が、あえて変化の先頭に立ち、変化の生み手になることだという。

第134回
組織の機能は起業家的たるべきものである
イノベーションこそマネジメントの中核に位置づけなければならないとドラッカーは言う。なぜならば、組織の機能とはもともとが起業家的なものだからである。

第133回
行うべき仕事の内容を明らかにしてその仕事に集中する
知識労働の生産性についての研究は始まったばかりである。知識労働者の生産性は、仕事の質を中心に据えなければならない。しかも、最低を基準としてはならない。量の問題を考えるのは、その後である。

第132回
歴史をつくるのは一人ひとりの働く人間だ
イノベーションを行なう企業人こそ、全体として見るならば、歴史家たちが認識しているよりもはるかに大きな影響を人類の歴史に与える。歴史をつくるのは、一人ひとりの働く人間だ、とドラッカーは繰り返し言う。

第131回
知識労働者の多くは意味のない仕事で忙しさが増大する
ドラッカーは今日、技術者、教師、販売員、看護師、現場の経営管理者など、知識労働を行なうべき人たちが、ほとんど意味のない余分の仕事を課されて、忙しさを増大させていると指摘する。

第130回
上司たる者は部下の強みを最大限に生かす責任がある
上司は部下の仕事に責任をもつ。部下のキャリアを左右する。したがって、強みを生かす人事は、成果をあげるための必要条件であるだけでなく、倫理的な至上命令、権力と地位に伴う責任である。

第129回
仕事の基盤の移行が知識に関わる者に新たな責任を課す
ドラッカーは、これまでの怪しげな歩みを見ても、知識の仕事への適用が心躍る偉業であることは明らかであると言う。そこに秘められた可能性は、かつての技能のそれと同じくらい大きい。

第128回
人を育てる能力を失うのは小利に目が眩んだと同じ
圧倒的に多くのマネジメント、特に中小企業のマネジメントが業績向上のための時間がないとこぼす。本業の仕事ではなく、雇用関係の規制という問題に取り組まされている。

第127回
いかに努力しても達成できない目標は、目標として間違っている
公的機関は実現可能な目標を必要とする。正義の実現は永遠の課題とすべきものである。いかに控えめにいっても、正義が完全に実現することはありえない。

第126回
仕事の能力が仕事の質だけでなく人間を変える
自らの成長に責任を持つ者は、自分である。上司ではない。したがって、組織と自らを成長させるためには、何に集中すべきかを自ら問わなければならない。

第125回
子供の才能を成果に向けて方向づけるには
本来教師の果たすべき役割は動機づけし、指示し、激励することである。教師は相談相手となるべきものであり、教師を学ぶことの監視者の役から解放し、教師本来の仕事のための時間をつくらなければならない。

第124回
自らの陳腐化が競争相手による陳腐化を防ぐ
研究開発の成否の鍵は、研究開発にかかわる10の原理を知ることにある。知識でもなければ知力でもない。激しく働くことでもない。いわんや幸運でもない。

第123回
自らの得意とする仕事の仕方を知りそれを向上させる
驚くほど多くの人たちが、仕事にはいろいろな仕方があることを知らず、そのため得意でない仕方で仕事をし、当然成果は上がらないという結果に陥っているとドラッカーは言う。

第122回
乱気流時代には、機会に糧食を与え問題に糧食を絶つ
資源を成果に向けて集中することほど面倒で評判の悪いことはない。ノーと言わなければならないからである。ドラッカーは、機会には糧食を与え、問題からは糧食を絶て、が鉄則だと言う。

第121回
企業は公益をもって自らの利益としなければならない
社会のリーダー的存在としてのマネジメントの責任とは、公共の利益をもって企業の利益にすることであるという。公益を私益とすることによって、両者の調和を実現しなければならない。
