深野康彦
第14回
今年も確定申告の季節がやってきました。会社員などが支払った税金を取り戻すことのできる唯一のチャンスですから、有効に活用したいものです。今回は、今年の確定申告で押さえておきたい4つのポイントに絞ってお話しします。

第13回
今回ご相談を寄せてくださったのは、2年後の56歳で退職され、経営が悪化している家業を継ごうと考えられているNさん。家業を継いだ後、Nさんの収入が0円になってもやっていけるのかどうかというお悩みをお持ちでした。

第12回
今回ご相談をいただいたのは、80代の両親と同居する55歳の独身女性。現在の勤務先からの給与だけではこれからの生活が厳しくなるとの見通しから、将来へ向けてどう資産形成をしたら良いのか、というご相談です。

第11回
新年を迎え、今年こそはお金を貯めるぞ!と決意した人は多いことでしょう。しかし実際は、なぜお金が貯まらないのか、貯められないのでしょうか。それは、自分に無理を強いているか、ストレスのたまる方法で貯蓄を行っているからです。

第10回
今回のご相談者Oさんは筆者より1歳年上の57歳の男性で、長年の過労がたたりうつ病を患われたとのこと。寄せられたご相談は、現在休職中のまま会社を退職して良いか、復帰して定年退職の60歳までの2年間働くべきか、というものでした。

第9回
例年、ふるさと納税は所得税額と年収が確定する年末に駆け込みで行う人が多いのですが、思いがけない失敗をしてしまうケースが少なくありません。そこで今回は、「駆け込み」でふるさと納税する際に注意すべき点をおさらいしましょう。

第8回
今回は、50代前半での早期退職を考えているKさんからのご相談です。Kさんは現在、年収2000万円で、金融資産3000万円を保有している方。一見、早期退職は問題なさそうですが、実際はとても厳しい事情を抱えていらっしゃいました。

第7回
老後に向けてできるだけ資産の山を築いておきたいもの。まして退職金は大切な虎の子ですから、しっかり増やさねば肩に力が入ってしまう人も多いでしょう。今回はそんな方にこそ知ってほしい、60代が陥りやすい投資の罠についてお話しします。

第6回
60歳で定年退職を迎えた後も、老後資金の不足などを理由に仕事を続ける方がとても増えています。そんななか、今のスキルでは60歳を超えてから十分な収入が得られるのか不安に思い、資格取得を考えている方もいるようです。

第5回
子どものいる家庭であれば、大学までの教育費として、学資保険なども含めて用意しているケースが多いと思います。しかし、子どもの進路変更によって、老後資金計画を大幅に変更しなければならないほど、教育費貧乏に陥ることがあります。

第4回
早期退職の鍵は「住居費」と「生活費」が握っていると言っても過言ではありません。そこで今回は、筆者の元に早期退職の相談に来たYさんとKさんの例を挙げながら、どんな人であれば早期退職が可能かどうかを探ることにしましょう。

第3回
共働きで高級タワーマンションを購入する夫婦は少なくありません。Zさん夫婦も6000万円のタワーマンションを購入しましたが、妻が妊娠を機に突然の退職を宣言。これによって世帯年収は500万円もダウンし、家計が急に火の車へと転じました。

第2回
都内在住のAさんは、夫婦で年収1150万円もの年収がある高所得世帯の方でした。子どもを小学校から私立へ行かせたい希望を持っていましたが、小学校から高等学校まで私立に通わせると12年間の総学習費は約1630万円もかかります。

第1回
年収1000万円以上でも貯金ができない世帯は少なくありません。およそ10世帯に1世帯は貯金ゼロというデータもあります。ファイナンシャルプランナーの筆者が出会った、年収が多いのに貯金額が少ない世帯の代表例を2つほどご紹介しましょう。
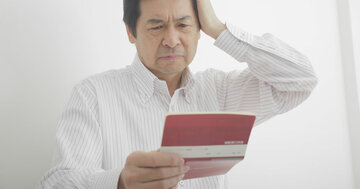
第2回
逆風下でも買ってもいい健全な毎月分配型投信とは?
投信の残高の約半数を占める大人気商品の毎月分配型投資信託。足元の株高に反して、分配金をどんどん減らしたり、基準価額が下がるなど運用環境が悪化していたりするファンドが続出している。今回はそんな危ない毎月分配型投資信託から乗り換えたり、新規に買ったりするのにピッタリな健全な毎月分配型投資信託について、その分析方法を『あなたの毎月分配型投資信託がいよいよ危ない!』の著者が解説する。

第1回
親の毎月分配型投信が危ない!
投資信託の残高の5割を占める「毎月分配型投資信託」。投信の主役で、「誰もが買う投信」と言っても過言ではありません。中には退職金のかなりの額を投じて買っている人、月々の分配金を老後の命綱としている人もいます。しかし、金融情勢や経済状況の変化で、そんな毎月分配型投信に危機が迫っています…
