
鈴木一之
日本では、春から夏の移行期(5月から7月)に雨期(梅雨)が訪れるため、梅雨は約40日間に及ぶ「第5の季節」と呼ばれている。梅雨は嫌われがちだが、農作物にとって恵みの雨でもあり、貴重な水資源をもたらす大切な時期でもある。梅雨が発生するメカニズムや、梅雨が空梅雨、長梅雨になる理由を解説するとともに、気象庁でも難しい気象予報に関連する注目銘柄を紹介する。

新型コロナウイルスの感染者は、完全に終息したわけではない。また在宅ワークの機会も増え、運動不足になりがちだ。運動不足の解消と、感染症に備えた自己免疫力の強化に対する注目度が高まり、乳酸菌を多く含むヨーグルトが見直されている。ブルガリアやコーカサスで長寿が多いのもヨーグルトのお陰といわれている。ヨーグルトに含まれる乳酸菌の体内での働きを整理し、プロバイオティクス時代の注目銘柄を探る。
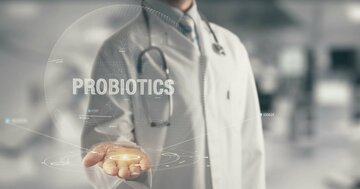
トヨタ自動車の2020年3月期決算では、売上高、営業利益はともに前年割れ。ただし今期見通しでは営業黒字を確保するとした。長年の原価低減がここで生きた格好だ。これは「トヨタ生産方式」と呼ばれる独自の生産システムによるもの。リーマン・ショック後の景気回復局面では、トヨタが工場稼働率を引き上げるというニュースが市場を動かした。トヨタ生産方式の仕組みを整理するとともに、今回のコロナショックでも、2009年当時と似たような状況になるかを考察する。

新型コロナウイルスが猛威を奮っている。ウイルスは細菌や真菌などの微生物と違い、細胞壁や細胞膜、細胞質、核などの構造体を持たず、大きさは0.02~0.3マイクロメートル(μm)と著しく小さな微生物だ。ウイルスほど小さい微粒子は、気流に乗って移動・拡散し、重力によっても落下せずに空中に漂ったままだ。微小な浮遊物を大気中から取り除く装置として、クリーンルームが改めて注目されている。クリーンルーム銘柄の有望度を考えよう。
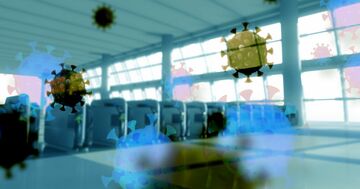
東日本大震災から9年目を迎えるが、日本の大分部の活断層は東日本地震をきっかけに活発に動き出す時期に入ったとみられ、震災前後でマグニチュード3~6までの地震の数は5倍に増えた。「水と安全はタダ」ではなくなっている。

海外では和食ブームが続いており、日本の農産物輸出は7年連続で史上最高を更新。農業参入への規制緩和、法人化、農地バンクなどによって企業サイドにも農業が有望なビジネスとして映っている。地方都市では私鉄、ガス会社、スーパーマーケット、エンタメ企業など、その地方の中堅企業が相次いで農業への参入を試みている。さらなる農業の活性化に向けて、取り組みを強化すべき方策や、すでに農業分野に進出している企業群を紹介する。

地球温暖化を防止する切り札として、磁石が新しいエネルギーの創出や省エネ化に大きな役割を果たすようになっている。電気製品による電気エネルギーの消費を抑えるためには、モーターの効率向上が必要だが、それには磁石の性能向上が不可欠となる。磁石の重要性を解説するとともに、磁石・モーター関連の注目銘柄を紹介する。

クリスパー・キャス9は、第3世代のゲノム編集の技術とされており、2012~13年ごろに技術的に確立された。クリスパー・キャス9による遺伝子の改変は、極めて有効であることが実証された。まだ研究途上の科学技術だが、数々の研究成果は人類の到達点が着実に上がっていることを示している。この分野で活躍が期待される企業はどこだろうか。

日本では、インフルエンザは例年11月下旬ごろから流行し始め、翌年の1月から2月にかけて患者数がピークを迎えるが、今年はかなり早い段階から流行が始まっている。インフルエンザは毎年、数百万人の規模で患者を出しており、間接的な原因も含めると死に至る人は1シーズンで1万人を超える。世界中がインフルエンザで危機的状況に陥りかねないが、それをビジネスチャンスとする企業もいる。

異常な猛暑、冷夏、干ばつ、集中豪雨など自然災害は大規模化している。原因は、化石燃料由来の二酸化炭素による温室効果だ。石油に由来するエネルギー需要が今後も増していきそうななか、代替えエネルギーとして注目されるのが人工光合成だ。

宇宙ベンチャー「スペースX」の出現など、宇宙に係るマーケット(宇宙ビジネス)が急拡大している。宇宙ビジネス拡大の背景には打ち上げコストの急速な低下があり、使用後ロケットの再利用や周回衛星の小型化といったコスト削減策が普及している。宇宙ビジネスの開発期間とコストは、かつてのような「10年=100億円超」から「1年=1億円」に小さくなっており、有望な宇宙ビジネス銘柄は日本株市場でもいくつかみられる。

マイクロ・プラスチックごみや資源ごみが世界的に問題化している。中国が一昨年、資源ごみや廃棄物の輸入禁止措置に踏み切ったことで、だぶついたプラスチックがアジア諸国から一気に海洋へ流れ出しているためだ。今後、プラスチックごみはマレーシアなどが受け入れ先になっていくと見られるが、彼らの処理能力が充足されるには時間を要するだろう。そうなると、日本のリサイクル業者が注目されるはずだ。

スマホで動画を楽しむユーザーは着実に増えている。民間企業の調査によると、有料動画配信サービス利用者の7割近くが「リアルタイムのTV番組」を視聴しており、NHKの参入などでネットを経由した動画配信は、これまで以上に急速な広がりを見せることになると思われる。米国ではネットフリックスの株価が過去最高値に接近しており、アップルなど他コンテンツメディアもサブスクリプション型の動画配信に参入する。各社の戦略は、ユーザーの需要動向を含めて非常に興味深い。

我々が暮らす現代社会は「第四次産業革命」に突入している。時価総額で20兆円を超えるトヨタ株が下げる一方で、AI銘柄のHEROZが上昇を続けるように、時代が大きく変わるとき、最初に見られるのは株価の動きだ。第四次産業革命によって地域コミュニティの在り方から個々人の健康、教育、社会衛生、消費活動、生活上の意思決定にいたるまで、あらゆるものが変わろうとしている。第四次産業革命の中核技術であるAI関連銘柄から目を離すことはできない。

GWの大型連休を挟んで、日経平均株価は7日間の続落を記録した。不調の理由は、米中貿易摩擦の再燃や、日本景気の急速な悪化だ。企業は次々と設備投資を控え始めた。そんな空気を打ち破る起爆剤になりそうな分野が、デジタルトランスフォーメーションだ。

最近、「MaaS(マース)」という言葉を耳にすることはないだろうか。令和元年は通信業界における「5G元年」であるが、同時に「MaaS(マース)元年」でもある。世界規模の巨大な技術革新の動きが始まっているのだ。その全容をわかりやすく解説しよう。
