野木森 稔
トランプ政権がウクライナ停戦交渉でウクライナの希少資源確保に動くのは軍事・国防上の思惑からだ。日本や西側諸国が進める新エネルギー推進や経済安全保障のための重要鉱物サプライチェーン強靭化と趣が異なる。むしろトランプ政権の「脱・脱炭素」政策によってその取り組みが遅れ、脱炭素に必要な鉱物資源の中国依存が強まる懸念がある。

中国経済はトランプ新政権による最恵国待遇撤廃や関税引き上げで実質GDP成長率が▲1%ポイント下押しされる見通しだが、第1次トランプ政権時代と違って国内も不動産不況と消費不振の問題を抱える。習近平体制はデフレ不況に陥るリスクを軽視しているように思われ、判断を誤ると深刻な経済悪化が懸念される。

少子高齢化と不動産不況、消費マインド低迷で中国経済の減速は長く続く可能性が高い。労働人口は足元でピーク時の2%減だが、2050年までに3割減り、若者層の6割が低価格を追求する。バブル崩壊以降の日本に酷似する状況だが、他の新興国でその大きな市場や「世界の工場」の役割を担える国は出ておらず、世界へのマイナス影響の波及が懸念される。

少子高齢化と不動産不況、消費マインド低迷で中国経済の減速は長く続く可能性が高い。労働人口は足元でピーク時の2%減だが、2050年までに3割減り、若者層の6割が低価格を追求する。バブル崩壊以降の日本に酷似する状況だが、他の新興国でその大きな市場や「世界の工場」の役割を担える国は出ておらず、世界へのマイナス影響の波及が懸念される。

G7が中国によるEVや太陽光パネルなど新エネ製品の「過剰生産」への牽制や対抗処置の検討を打ち出した。補助金や安い労働力、緩い環境規制によるコスト競争力を背景に流入し自国の脱炭素産業育成を妨げるとの危機感からだ。だが高関税での流入排除はインフレによる景気悪化リスクを強める両刃の剣の危うさがある。

中国経済の「日本化」が進む背景には投資偏重の成長を是正するための構造改革が先送りされてきたことがある。社会不安定化を回避したい習近平指導部は「共同富裕」など政治的成果を重視するほど長期停滞から抜け出せない可能性が高まる。

中国政府はゼロコロナ政策の緩和を打ち出したが、習近平体制の「柔軟性を欠く政策運営」と「経済問題の軽視」を考えると、政策の抜本的な転換は難しく成長減速や企業の「脱中国」の動きは止まりそうにない。

習近平総書記は異例とされる3期目の続投を実現したが、経済はコロナ対応、不動産不況、米中対立の「三重苦」だ。新体制は内外の政治的な成果にのみ固執し経済軽視から序盤でつまずく可能性さえある。

「台湾有事」の一つの鍵を握るのは、先端半導体製造で世界トップの台湾半導体産業だ。米中ともに当面は半導体の供給を台湾に頼らざるを得ず、台湾半導体を巡る綱引きが「新たな台湾問題」となり始めている。

ゼロコロナ政策に加えウクライナ問題で二次制裁を受けるリスクを嫌って企業が他国に代替地を探す動きや中国株売却が活発化する。コロナ規制次第では「中国離れ」加速の引き金なる恐れがある。

中国政府の介入が強まる国際金融都市香港は中国広東省や「一帯一路」沿線国などの中国市場に特化した金融センターになる可能性が強い。米中対立が激化するほど中国化が加速しそうだ。

米中新冷戦で ASEANの対米中バランス外交が難しい局面だ。コロナ禍で貿易や投資での中国依存が深まる一方、米国からはファーウェイ排除の圧力が強まり、板挟みのジレンマが増す。
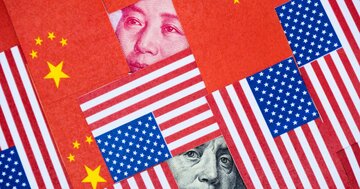
国家安全維持法が施行された香港の国際金融都市の機能は当面残るが、米中対立深刻化で米国が厳しい金融制裁を発動することになれば、深刻な打撃を受け中国の資金調達にも支障をきたすことになる。

新型ウイルスの感染拡大で、中国人旅行客の急減だけでなく生産休止によるアジアのサプライチェーンへの影響も出始めた。1-3月期は香港や台湾などマイナス成長が見込まれ、最悪の場合、アジア通貨危機再燃の懸念がある。
