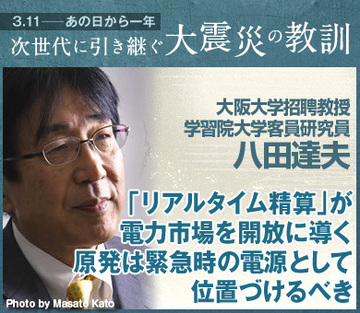下河辺和彦会長(奥)と廣瀬直己社長(手前)にとって、スマートメーター問題は避けては通れない課題となる
下河辺和彦会長(奥)と廣瀬直己社長(手前)にとって、スマートメーター問題は避けては通れない課題となるPhoto:REUTERS/AFLO
7月6日午前、東京・内幸町の東京電力本店内の一室に、7人の男が集まっていた。6月末に発足した新体制で「改革の司令塔」となる経営改革本部の初会合である。配られた資料には当面の重点経営課題として、福島第1原子力発電所の廃炉や賠償、柏崎刈羽原発の再稼働と並び「スマートメーター」との文字が記されていた。
「改革の第一歩」として1700万台の国際入札が実施される予定だった東電のスマートメーターだが、旧体制下で、下請けメーカーらに有利なように“出来レース”が仕組まれていた。さらに東電はメーター導入に合わせ、必要でない光ファイバー網を約1100億円かけて自前で敷設することをもくろんでいた(週刊ダイヤモンド4月14日号特集2などで詳報)。
この問題の解決が、重要課題の一つに挙げられ、新生東電を象徴する最初のプロジェクトとなったのだ。先立つ7月2日に開かれた経済産業省の電気料金の値上げを審査する専門委員会では、値上げの根拠となる原価を計算する際、スマートメーターの調達費を削減し、光ファイバーの敷設費用も計上しない方針が確認された。
東電のコストカットを請け負う原子力損害賠償支援機構も12日に、新たなメーターの仕様を発表。従来東電が主張していた光ファイバー型メーターを採用しない方針を明確に打ち出した。これでようやく東電の高コスト体質に本格的なメスが入ったことになる。
ところが、「東電は“不死鳥”のような粘りを見せている」と入札関係者は漏らす。
抵抗しているのは東電の電子通信部。光ファイバー型メーターに執拗にこだわり、原賠機構と最後までもめた上、原賠機構との共同案件であるはずの新仕様発表も、東電側は内容を隠すようにホームページの見つかりにくい部分に潜ませた。