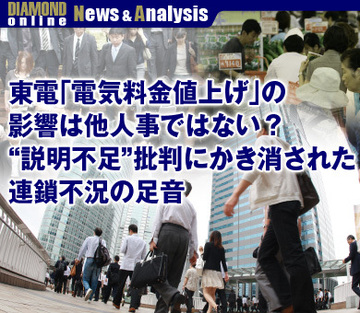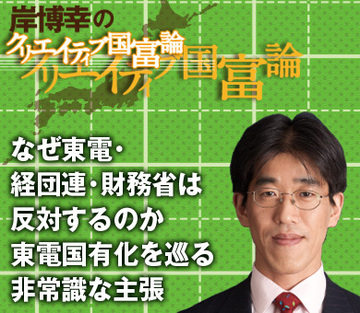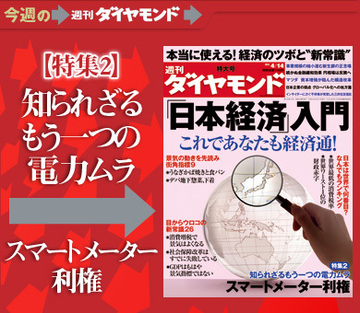東京電力の新社長となる廣瀬直己常務は、まず値上げ問題に対処することになる
東京電力の新社長となる廣瀬直己常務は、まず値上げ問題に対処することになるPhoto:REUTERS/AFLO
東京電力が、家庭用電気料金の平均10.28%値上げを経済産業省に申請した。電気事業法に基づく料金改定申請は1980年以来32年ぶりで、すでに東電が4月から始めた産業用電気料金の値上げに批判が集中したこともあり、その行方に注目が集まっている。
枝野幸男経済産業相は申請を受けて値上げが適正かを審査する専門委員会を設置し、「国民目線」の議論を進めているが、忘れられがちなのは、産業用料金と家庭用料金では、値上げの手続きが全く違っていることだ。
産業用は、経産省の認可なしで自由に値上げできる。燃料費の増大などで財務が圧迫する東電にとっては、自力で取り組める唯一の再建手段ということもあり、今年1月に約17%の値上げをいきなり発表した。結果的に枝野経産相のほか、国民全体から集中砲火を浴び、東電は窮地に陥った。
しかし、電力会社による地域独占が続く家庭用の値上げはプロセスが異なる。電気事業法19条2項は、経産相による「認可」が必要と定めている。政府関係者は「経産相が国会を通さないで認可する最も重たい案件」と指摘する。
つまりは、1月時点では「けしからん」という第三者の姿勢を貫いていればよかった政府が、今回の規制部門では値上げを「認める」という当事者的な作業をしなければならず、政府としての「姿勢」が試されることになる。
枝野経産相は「予断を持たずに丁寧、慎重に審査する」とし、専門委員会にも消費者団体に参加してもらうことで本格議論をすでに始めている。料金原価に含めるコストを絞れば、値上げ幅が圧縮する可能性はある。
ところが、経産省内では「縮小はおそらく誤差の範囲内だろう」(幹部)との声が多い。というのも今回の申請では政府の有識者会議が決めた値上げ幅引き下げを盛り込んでおり、10.28%という数字も東電が政府の「原子力損害賠償支援機構」と決定した。東電次期会長となる、機構の下河辺和彦委員長も「デューデリジェンス(資産査定)を中立的にかなり行った」と説明している。