デジタル・トランスフォーメーション(DX)を、IT化に留めることなく、ビジネスモデルの再構築、ビジネスプロセスの全体最適化、新規事業開発やイノベーションといった、非連続的な変革へと発展させる。また、自前主義や縦割りなど「閉ざされた」経営から抜け出し、さまざまなプレーヤーと共創し、新しい価値や競争優位を創出していく。いま日本企業には、こうした「開かれた」経営が求められている。そのためにはDXが必要十分条件である。「大企業こそDXの牽引役となるべき」と唱える東京大学大学院教授の森川博之氏と、KDDIでDXを推進してきたソリューション事業企画本部長の藤井彰人氏が、日本のDX論について意見を交わす。
大企業こそDXの牽引役
編集部(以下青文字):ピーター・ドラッカーは、「大企業には、国や政府以上に社会を変革する力がある」と考え、会社のあり方、経営者の使命について提言してきました。森川先生も、「大企業こそデジタル・トランスフォーメーション(DX)の牽引役になるべきである」と主張されています。
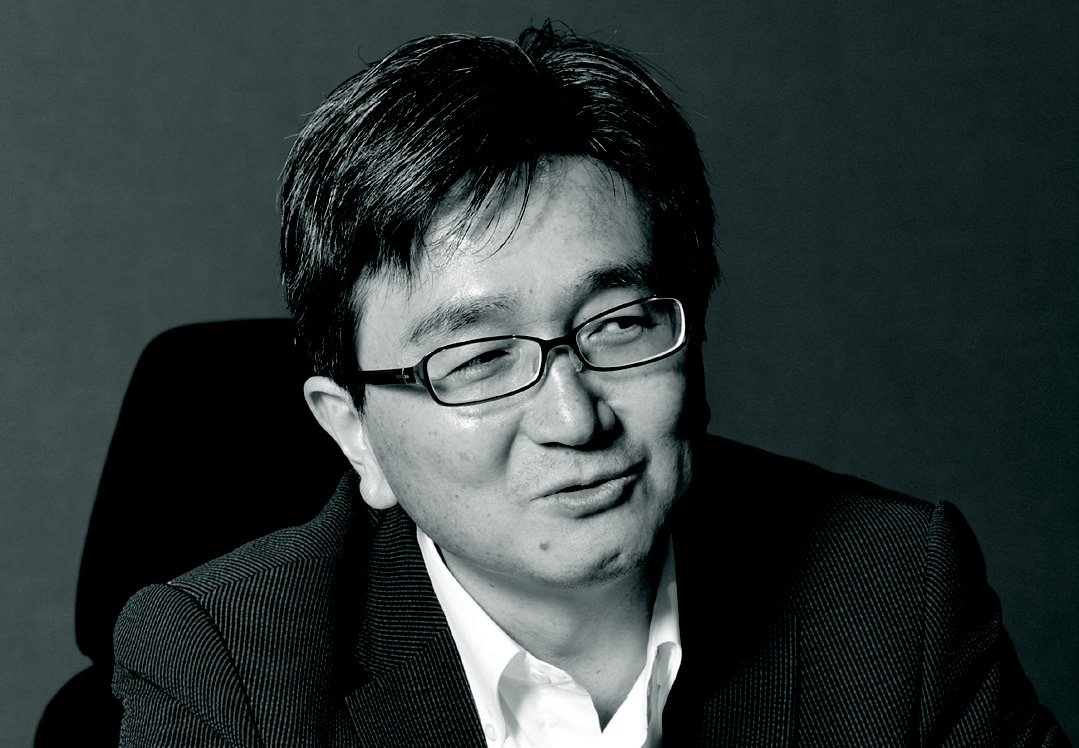
森川 博之 HIROYUKI MORIKAWA
森川:DXを通じて、モノやサービス、社内外のリソース、従業員や顧客といったステークホルダーがつながっていく。そうして新規事業やイノベーションが生まれ、社会にダイナミズムをもたらし、既存事業も変革され、そこからまた新しい何かが萌芽する――。こうした好循環の形成には、大企業の存在が欠かせません。
また、社会を変革・進化させるには、スタートアップの意欲や創造性だけでは足りません。やはり、全国津々浦々に広がる流通網や営業網、通信ネットワーク、多種多様な特許や知財、大規模なR&D、規制対応のノウハウ、幅広い人脈など、大企業ならではの有形無形のリソースが必要なのです。
大企業とスタートアップ、あるいは大企業同士がより広範かつ緊密につながり、フラットに共創していくことがDXの早道であり、大企業のDXに期待しています。
また私は、これから「大企業によるイノベーションの時代」がやってくると考えています。イノベーションの主体は、おおよそ50年単位で変わってきました。1870年代は、トーマス・エジソンやグラハム・ベルといった個人によるイノベーションの時代。1920年代は、デュポンやゼネラルモーターズなど企業主導のイノベーション。1970年代は、主にベンチャーキャピタルによってマイクロソフトを代表とするIT企業が世界中に生まれました。そして2020年代は、大企業が主導になるだろう、と。

藤井 彰人 AKIHITO FUJII
藤井:DXの目的は、単なるデジタル化やIT化を超えて、ビジネスモデルの再構築、ビジネスプロセスの全体最適化、新たな競争優位の確立など、非連続的な変化を推進・実現することにあります。
おっしゃるように、大企業は有形無形のリソースをさまざまに抱えています。その多くはまだ内部に閉ざされていますが、事業提携や協業、オープンイノベーションなどを通じて、次第に解放されつつあります。日本の産業界にDXが広がれば、さらに加速され、共有や結合が進み、その結果として新しいビジネスモデルやイノベーションがそこかしこで生まれてくる――。期待を込めて、こう申し上げたい。
森川:私はいま地方を応援しており、自治体をはじめ、地域の商工会議所や経営者団体からお声がかかると、できる限り足を運ぶようにしています。地方の中小企業の方々とお話しすると、デジタル化やDXに興味があるものの、何をすればいいのかわからないと言うのです。大企業が地方に深く入り込み、隠れたニーズをすくい上げながらDXに取り組めば、地方でもDXが促され、ユニークな共創やイノベーションが生まれてくるのではないでしょうか。
ドイツのインダストリー4・0では、中小企業のDXによって弾みがついたそうです。
藤井:KDDIは長年にわたって、通信プラットフォームを日本の隅々に提供する中で、さまざまな地方の中小企業とお付き合いしてきました。その経験から申し上げると、中小企業がDXに取り組むと、大きな成果が生まれやすい。
これは弊社の営業担当者の提案から始まったのですが、節水装置メーカーと協業して、ビジネスモデルを大きく変革したケースがあります。トイレ内にセンサーを設置し、利用者が着座している時間を計測し、それに応じて水量を流し分けることにより無駄な洗浄水を削減するソリューションを開発し、月額サービスとしたのです。その結果、製品の販売だけで稼ぐ「フロー型ビジネス」から、ユーザーから定期的に対価をいただく「ストック型ビジネス」へと、みごと転換を果たしました。実は、地方には優れた技術や伸び代の大きい事業がたくさんあり、ここにデジタル技術やビジネスパートナーを加えると、一気に花開く可能性があります。




