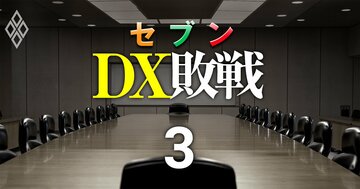Photo by Shintaro Iguchi
Photo by Shintaro Iguchi
日本の製造業の生き残りに不可欠なDX(デジタルトランスフォーメーション)とAI活用だが、その道のりは平坦ではない。特集『製造業DX 破壊と創造 9兆円市場の行方』の#4では、日立製作所とファナックという日本を代表する企業で40年以上製造業に携わり、長くデジタル分野に関わってきた情報処理推進機構(IPA)の齊藤裕理事長に課題を聞いた。インタビューの前半部分では、齊藤氏が民間のビジネスでの経験も踏まえて描く、和製デジタル・エコシステムの構想をお伝えする。(ダイヤモンド編集部 井口慎太郎)
日本のDXは「個別業務のデジタル化」止まり
エコシステム構築で求められる国の関与とは
――IPAがまとめている「DX動向」の2025年版が公表され、日本のデジタル活用はあくまで“個別最適”にとどまっているとの指摘がありました。
欧米のDXは“そこにいる人間”をいなくする。一方、日本では現場の担当者の業務効率化にとどまっています。デジタルを用いたトランスフォーメーションではなく、既に構築されている業務フローにデジタルツールを埋め込んでいるだけで、投資効果は薄いのです。日本のDXが進んでいるのかというと、全く進んでいません。
欧米は大手企業が業界をまたいで課題を解決するためにトップダウン的な発想で進んでいます。まず目的がある。日本はデータ連携から入っている。プロダクトアウトなのです。「データ連携したら何か良いことあるだろう」「やれって言われてるからやってる」。目的じゃなくて手段が先になっています。
――生成AIやDXの導入で、人間が不要になる根本的な恐怖感が導入にブレーキをかけていることはないですか。
日本の製造業は長い間、従来のやり方で良い品質のものができて、給料も良かった。積み上げたものを壊さない方が良いよねとなった。私も良い時代に育ちました。でも、今の日本は全然賃金が上がっていません。安定領域に入ると衰退しかない。他方、欧米では「常に変わり続けたい」という考え方があります。
――日本企業のDX成功例は。
世界で戦いながら成長を続けているのは、製造業や小売業で変化を恐れず挑戦している企業です。例えばニデックはM&Aを駆使して事業を広げており、ニトリホールディングスやアイリスオーヤマも製造を内製化しながらカテゴリー拡大に挑んでいる。ユニクロを展開しているファーストリテイリングも、情報製造小売業としてデジタルを活用し、小売から製造まで自社のテリトリーを広げています。
――古巣の日立製作所はデジタルに注力して久しいです。
日立は電力システムや鉄道事業を通じ、“BtoBtoC型”のサービスを確立しました。顧客との接点があるのが重要です。グローバルでインフラと情報を軸にデジタルを活用したビジネスモデルへ転換し、他社より一歩抜きんでた存在となりました。
生成AIの活用で見えてきたのが、トラブル解析というものは、実は業界を問わずみんな同じだということです。日立であれ他社であれ、電気製品のトラブルって起きること自体は似ている。だったら共通のアーキテクチャーの上でトラブルデータを集約できます。そういう発想は、日立なら持てると思うんです。情報系の部隊もあるし領域も広いですから。
――欧米のプラットフォーマーがトップダウン型のDXを推進する中、日立はボトムアップ型の旗手となり得るのでしょうか。
特定の企業が単独で全てを担う米国や中国のような産業設計型の世界になるのか、それとも別の形となるのか。私は経済産業省の方とも話しています。現状の「データ連携」という言葉の裏には、「システム連携」や「サービス連携」も含まれている。つまり、特定の企業が中心ではなく、国としてある種の「デジタル・エコシステム基盤」を形成し、そこに責任を持って投資していくことが重要です。
次ページでは、40年以上民間で製造業に携わった齊藤氏に、デジタル・エコシステム構築の道筋を語ってもらう。なお、近日公開予定の本特集の#5『ラピダスを念頭に置く「政府出資」のキーマン・IPA齊藤理事長が語る!投資成功のための半導体メーカーとの“距離感”とは?』では、半導体産業の育成に向けた出資という新たな業務を担うことになるIPAと、出資先企業との望ましい関係性についても齊藤氏に尋ねた。