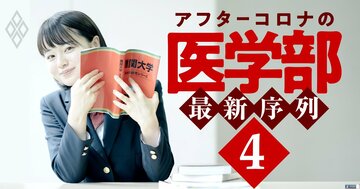支援事業を策定するに当たり演劇や舞台芸術関係者へのヒアリングを行ったところ、業界のガイドラインに定められている、ごく当たり前の感染対策だけでなく「観客の“安心”につながるよう自主的にも対策したいという目的で、コロナの検査を行っており、この費用も助成してほしいという要望が複数あった」(文化庁)。
PCR検査は自費で数万円かかり、検査結果が出るまでにも時間を要する。大手の劇団ならともかく、演劇業界や舞台芸術かいわいのほとんどは小規模な団体で、その費用を負担するのは難しい。
PCR検査の簡易版である抗原検査は、販売会社の富士レビオが供給先を絞っており、無症状者が自費で検査を受けられるところは多くない。
対して抗体検査は費用が数千円で済み、かつ15分程度で結果が出る。しかも広く出回っている。故に、業界は抗体検査で「陰性証明」をしようという行動に走った。
冒頭の劇場クラスターでは、必要な感染対策をことごとく怠っていた実態が徐々に明らかになってきた。客側に安心してもらおうとする善意が一転、一大クラスターを発生させてしまう――。抗体検査の陰性証明とは、かくも罪作りなものなのである。文化庁はこの劇場クラスターを機に、検査に対する誤解を招きかねないとし、助成対象から外した。
抗体検査の誤用は、エンタメ業界だけではなく、飲食などの接客業などでも散見される。彼らを「情弱」とやゆするのはたやすいが、エンタメや飲食は、コロナ禍の影響を最も受けた業界だ。検査に手を出したのも、なんとか客に安心してもらいたい、戻ってもらいたいという一心なのだろう。
現状、抗体検査を含めコロナの検査は原則、医者の下で行われているはずだが、なぜ抗体検査の誤用がこうも多発しているのか。
この問題を探ると、コロナ禍で困窮した医者が検査による「情弱ビジネス」に手を染めているという現実が浮かび上がってきた。