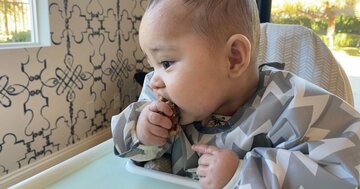夜間専用の赤ちゃんお世話係
「ナイトナース」とは?
産後のアウトソースの選択肢には、料理や掃除の家事代行、助産師やナニー(Nanny/親が不在の間、親に代わって子育てをする人)、ドゥーラ(Doula/産前・産後の家族のお世話係をする人)などがあります。
第2子を迎える際に我が家が最優先したのは「睡眠時間の確保」でした。新生児期間における夫婦の睡眠不足は誰もが知るところです。赤ちゃん用品を開発・販売しているOwlet Baby Care社の調査では、6カ月未満の赤ちゃんがいる夫婦の半数が「1~3時間しか連続で眠れていない」と回答しています。睡眠不足で出勤した結果、職場で居眠りした経験を持つパパは約30%に及んでいるというデータもあります。
睡眠時間確保のための我が家の具体的な手段は、「人間×テクノロジー」のハイブリッドでした。出産直後には夜間専用の赤ちゃんお世話係「ナイトナース」(night nurse)に来てもらい、以降は自動で揺らしてあやすスマートなゆりかご「スヌー(SNOO)」を活用しました。これらによって、どうあがいても睡眠不足をまぬがれることのできない期間を、第1子のときのようなサバイバルモードになることなく、乗り切ることができたのです。
「ナイトナース」は、「新生児ケアスペシャリスト」(NCS/Newborn Care Specialist)や「ベビーナース」とも呼ばれており、夜間限定で赤ちゃんのお世話をしてくれる専門家です。
「ナース」(看護師)というのはあくまで呼び名で、看護師の免許は必須ではありません。CPR(心肺蘇生法)や新生児ケアスペシャリストの資格(講義を3日受講し、乳幼児ケアの現場経験を最低1800時間または1年間行う)を持つ人が多い印象です。
我が家に来てくれたのは、近隣に住む20年以上の経験を持つナイトナースでした。平日の午後8時~午前6時までの間、彼女が赤ちゃんと同室にいてお世話をしてくれました。母乳をあげる場合、授乳や搾乳のためにママは起きる必要がありますが、粉ミルクのみであれば、ママとパパ、共に夜通し寝ることが可能です。
上記を含め、ナイトナースにお願いして良かったなと思う理由は主に5つあります。
1. 睡眠時間と睡眠の質が向上
私は母乳と粉ミルクの混合授乳だったので、夜間も3時間ごとに授乳をしていましたが、特に初期は「triple feeding」(一度に授乳・粉ミルク・搾乳をすべて行うこと)でした。でも、授乳後、ナイトナースが粉ミルクをあげてくれるだけでなく、オムツの交換や「ゲップ出し」も代わりにしてくれます。授乳中もそばにていてくれ、私は授乳だけすればいいので、限られた時間の中でも最長の睡眠時間を確保することが可能に。プロがいる安心感から睡眠の質も上がりました。
2. 睡眠を昼寝に頼らなくなる
「赤ちゃんが寝ている間に寝ればいい」と言う人がいますが、残念ながらそのように便利な「睡眠のオン・オフスイッチ」は存在しません。前述のOwlet Baby Care社の調査では、約40%のママが「赤ちゃんの昼寝中には眠れない」と回答しています。ナイトナースがいてくれることで、身体が自然に眠ろうとする夜間の時間帯に、眠ることができました。昼間に「寝なければ」と焦ることもなくなり、「昼寝ができればラッキー」くらいの心持ちでいられるようになりました。
3. プロの知識と経験
二男は、授乳中に急に泣き出して飲むのをやめてしまうことが頻繁にありました。授乳中また就寝中の様子を観察した結果、「胃食道逆流」であることが判明。対策としてナイトナースが、こまめにゲップをさせる、ベッドに傾斜を設ける、粉ミルクの種類を変える、などのアドバイスをくれました。また、赤ちゃんのおなかにガスをためないための食事指導など、ナイトナースの知識と経験に何度も助けられました。
4. プロが常に見ていてくれる安心感
産後入院中の3日間の間に、二男が3度ほど吐き戻して息を詰まらせる様子を、目の当たりにしました。慌てて縦に抱いて対応したのですが、「このときにもし誰も見ていなかったら?」と以降、不安がつきまとうように。その上、SIDS(乳幼児突然死症候群)の心配もあったので(アメリカでは年間3600人の赤ちゃんがSIDSで亡くなっているというデータがある)、ナイトナースが来てくれてからは、プロがそばで見ていてくれることで心のやすらぎを得られるようになりました。
5. 夜になればママやパパ業に一区切り
新生児期間のお世話は、いつにも増して「24/7」(24時間365日)体制です。昼夜問わず3時間ごとの授乳は続きますが、午後8時になったらナイトナースにバトンタッチして休める。それがわかっていることで、その時間までがんばろうと、つらいときでも乗り切ることができました。第1子のときにはなかった心の余裕が生まれたような気がします。