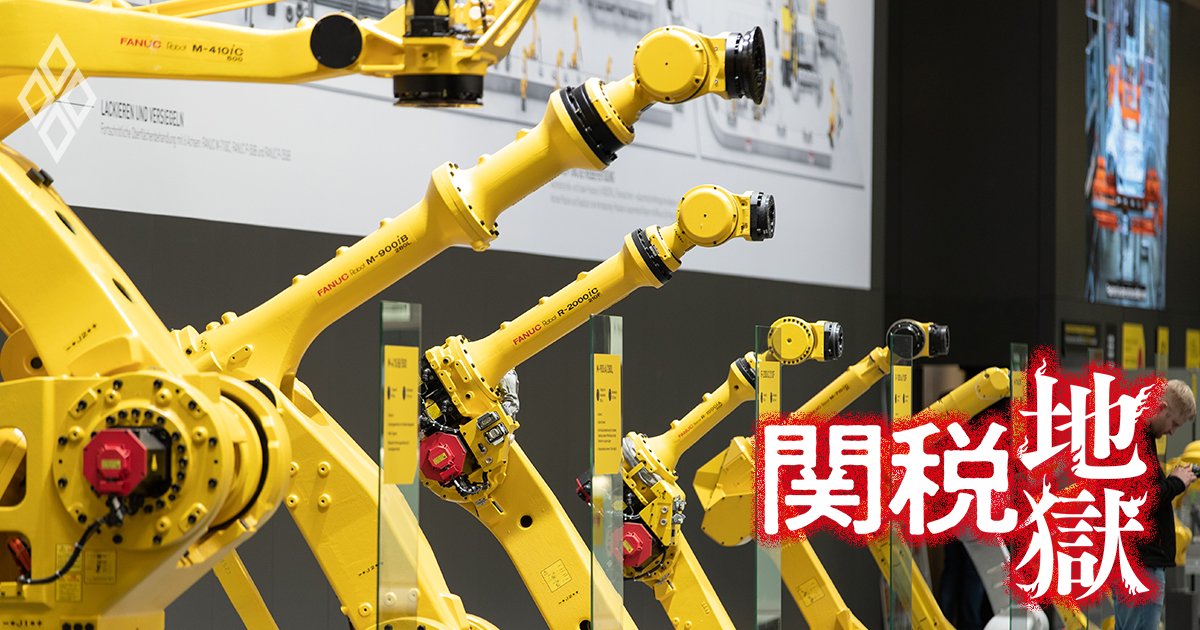企業は、社会問題の解決に取り組むことで社会的価値を創造し、その結果として経済的価値が創造される経営を行うべきとする理論、CSV(共有価値の創造)。ESG投資のバックボーンともいえる同理論は今日、再び脚光を浴びている。中国版CSVを志向する「CCSV」活動の発起人である鄭燕氏(電通公共関係顧問〈北京〉有限公司CEO)と、一橋大学大学院経営管理研究科客員教授の名和高司氏は共同で、東京と北京を結んだオンラインフォーラムを4月17日に開催した。「人と社会のWell-being実現を目指して」と題し、株式会社資生堂代表取締役社長兼CEOの魚谷雅彦氏とパナソニック株式会社副社長(中国・北東アジア社社長)の本間哲朗氏をゲストスピーカーとして迎えた同フォーラムの内容をレポートする。(構成/ジャーナリスト 田原 寛)
中国ではサステナブル消費が日本より速く広がる
フォーラムはまず日本から、名和氏がフォーラムの主旨と経緯を説明した。ハーバード大学教授のマイケル・ポーター氏らが2011年に提唱したCSVに共鳴した名和氏は、2014年からフォーラム形式で、日本でCSVの考えを深める活動を展開してきた。中国での鄭氏による「Co-Creating Shared Value」(CCSV:共有価値の共創)活動と、1年半前から連携するようになり、過去3回の中国主催イベントへの名和氏の参加を経て、今回初めて日中での開催に至ったということである。
次に中国から、企画者の一人である鄭氏が、中国の事業家や消費者の間で、「サステナビリティー」がいかに重要なテーマになりつつあるかについて発表した。