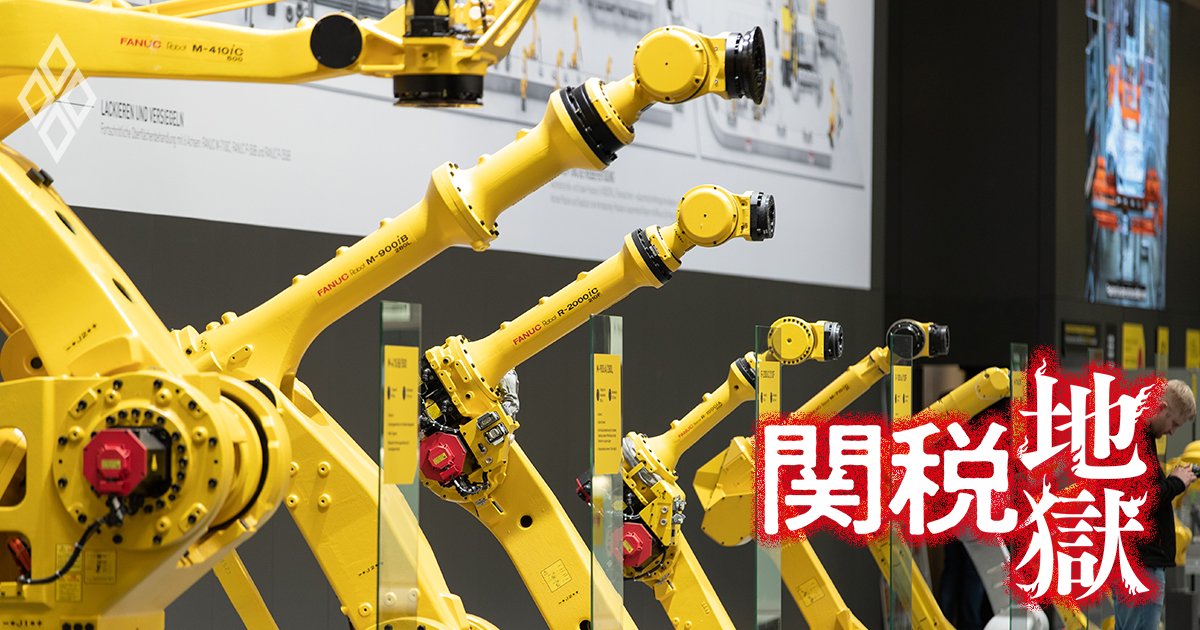「コンプライアンスだの、ハラスメントだの、困ったものだ。それに引き換え昔は良かった……とすら、迂闊には言えない時代になってしまった」と、ある年配の偉い人が嘆いておられた。欧米では法という規範に基づいた契約が絶対視され、個人や企業の権利意識が強いとされる。それに対して、日本は周囲との調和を乱すようなあからさまな権利意識の発露は抑圧されがちで、権利意識が薄く、本音と建前を使い分けながら、事を荒立てず、どちらの顔も立てるように、話し合いで両者の合意点を探るのが日本流だ、となんとなく感じることはあるだろう。
また、昨今のSDGsやカーボンニュートラル推進の急展開に、「ルール遵守とはいえ、そもそも自分たちの有利なようにルールを決めている」という不公平感に釈然としない思いを抱く人も多いに違いない。一体日本人の法に対する意識は変わったのであろうか。それとも、表面的に変わったように見えても、中身はもとのままなのだろうか。この問題を考えるため、今回は『日本人の法意識』(川島武宜著)を採り上げる。
なぜ日本人は
法に関わりたくないのか
 『日本人の法意識』(川島武宜著)
『日本人の法意識』(川島武宜著)岩波新書
ほとんどの日本人にとって、法は身近なものではなく、できれば関わりたくないものだ。それには理由がある。
日本の六法(憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法)の原典は、明治22年から31年の間、わずか10年たらずのうちに完成した。これらは、日本の従来の伝統とは断絶した内容を主にフランスとドイツから学んで(と言えば聞こえはいいが、ほとんどそのまま「拝借」して)起草したものである。先進資本主義国家の法典にならって作られた明治の近代法典と、当時の日本人の実生活とのあいだには、大きなずれがあったのだ。
「明治憲法下の法典編集事業は、まず第一次には、安政の開国条約において日本が列強に対して承認した屈辱的な治外法権の制度を撤廃することを、列強に承認させるための政治上の手段であった」(川島武宜の『日本人の法意識』より)