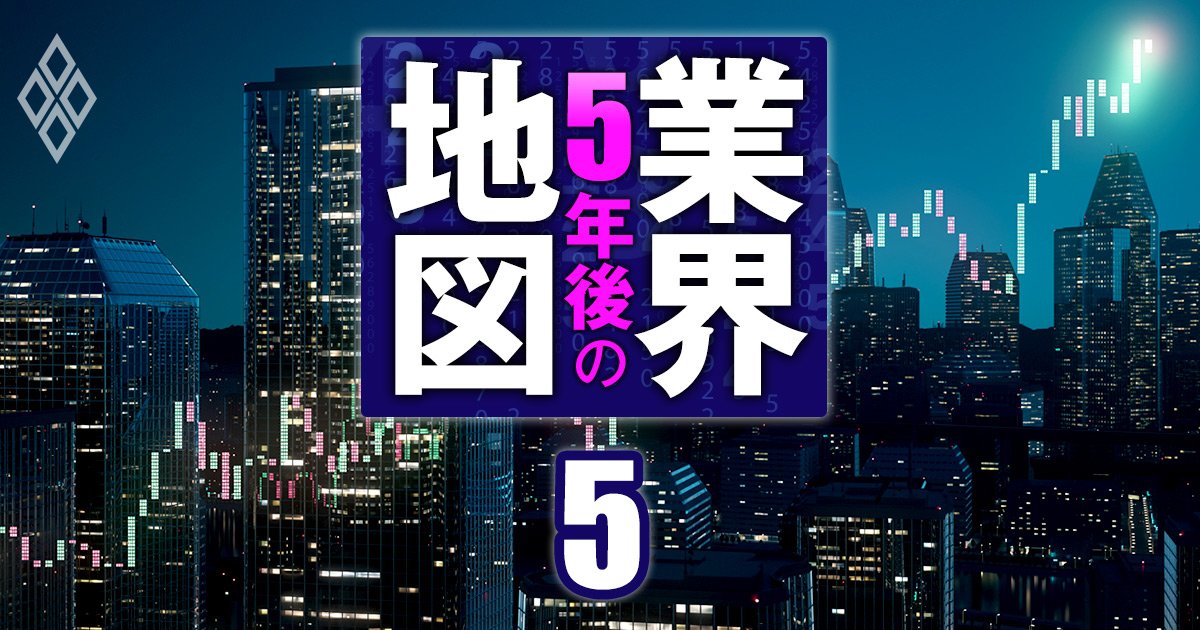不合理が実現する
合理的な理由
筆者が考える、ガソリン価格に関わるあるべき政策の優先順位を大まかに言うと、
(1). ガソリン価格への補助をやめて、困窮者への所得補助を充実させる、
(2). (1)の早急な実現が不可能で激変緩和措置が必要な場合、トリガー条項の凍結解除を補助金よりも優先する、
というものだ。現実的には、まずトリガー条項の凍結解除からということになるだろう。シンプルでかつ合理的ではないだろうか。
しかし、筆者の案が実現しないと信じるに足る、残念で強力な現実が存在する。その根源は一人一票を大原則とする民主主義と個人の経済合理的判断だと言うと穏やかではないが、以下のような事情だ。
まず、困窮者の所得を補助する政策は困窮者とされた国民には直接メリットがあっても、多数のそうではない国民にとってメリットが見えにくい。多数の国民が、ガソリン価格の高騰を眺めつつガソリンの使用を抑制する工夫を考えなくてはならない現実に直面して、不満に思うだろう。
これに対して、補助金による価格抑制は、個々の効果は小さくても直接的なメリットを感じる国民の数が多い。政権支持率に効くのはこちらの方だろう。
また、困窮者の所得補助は一度仕組みを決めるとそれでガソリン価格も電気代もガス代も価格メカニズムに任せることができる効率の良さがあるが、この効率性は、政治家や官僚にとっては、個々の品目と関連する業界に対して政策を「やっている感」を醸し出す上ではむしろ邪魔になる。
ガソリン価格の上昇が生活者の不満と共に報じられて政府が右往左往することは、政府の当事者にとってはまんざら悪いことでもないのだ。
直接的で近視眼的な賛否を超えて合理的な状態を実現するためには、国民が政策の立案・実行を委託する政治家や官僚に良識と能力が必要だが、どうやらわれわれはそのような政治家や官僚の養成に不熱心だった。
「これが日本国民のレベルなのだ」と言われたら返す言葉がないが、目を背けたくなるような現実がそこにはある。