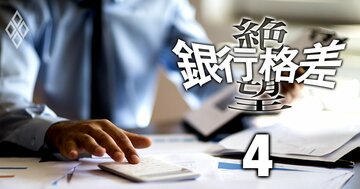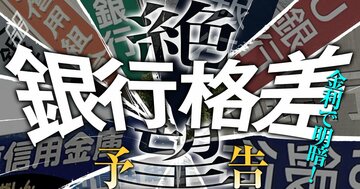『週刊ダイヤモンド』1月27日号の第1特集は「地銀 メガバンク 信金・信組 残酷格差」です。日本銀行がマイナス金利を解除し、金利のある世界が到来したとき、一体何が起きるのか。日銀や地方銀行、メガバンクなど金融機関への取材を通じ、その真相に迫ります。(ダイヤモンド編集部副編集長 重石岳史)
ゼロ金利政策導入から四半世紀
日銀が「2度」敗れた苦闘の歴史
「長きにわたる低インフレ・低成長の流れの転換に向けた動きが見られた1年だった」。
 日本銀行の植田和男総裁はマイナス金利の解除、そして利上げにより「金利のある世界」を復活させることができるか Photo:JIJI
日本銀行の植田和男総裁はマイナス金利の解除、そして利上げにより「金利のある世界」を復活させることができるか Photo:JIJI
2024年1月4日、都内で開かれた全国銀行協会の新年の集いに出席した日本銀行の植田和男総裁は、23年をそう振り返った。
植田総裁は24年について「賃金・物価がバランスよく上昇していくことを期待したい」と述べ、列席した銀行関係者らに対し、企業の前向きな設備投資や研究開発投資を支えるよう呼び掛けた。これに先立つ12月25日の講演では、植田総裁は「賃金・物価が動くようになることは、より大きなプラス効果を経済にもたらす」とも述べている。
「マイナス金利解除への布石として、デフレ脱却を強調しているかのようだ」。年末から年始にかけての一連の植田発言について、メガバンク幹部はそうみる。
だが、植田総裁は23年夏ごろまでは、「基調的インフレは依然として目標の2%を若干下回っている」との見解を持っていた。日銀が目指す消費者物価指数(生鮮食品を除く)の前年比上昇率2%の安定的な実現について、明らかに慎重な姿勢だった。22年に利上げを開始した米国との金利差が拡大し、円安が進んでいたにもかかわらず、である。
その慎重姿勢は理解できなくもない。
1999年にゼロ金利政策が導入されて以来、日銀はゼロ金利解除に2度挑み、いずれも失敗に終わっているからだ。