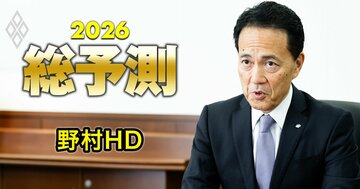重石岳史
インベストメントバンカー M&A請負人の正体#3
世界ナンバーワンの投資銀行で、日本で50年超の活動実績があるゴールドマン・サックス。日本法人を長年率いた持田昌典氏の退任後、名門M&A部隊のかじ取りを任されたのは、投資銀行部門共同部門長に昨年就任した高鍋鉄兵氏だ。日本企業が劇的な変革期を迎える中、新司令塔が描く新たな成長戦略、そして前例のない人員増強の全貌を明らかにする。

インベストメントバンカー M&A請負人の正体#2
2025年のM&Aリーグテーブルで23兆円超という史上最高額をたたき出し首位を奪還した野村證券。トヨタ自動車やNTTなどのメガディールを独占する背景には、歴代のバンカーが紡いできた「歴史的なタスキ」と、国内1000人超体制による圧倒的なネットワーク力がある。外資系がグローバル網を武器に攻勢を強める中、国内最強の「M&A請負人」に死角はあるのか。インベストメント・バンキング グローバル・ヘッドとして投資銀行部隊を率いる武村努副社長が、野村独自のグローバル戦略と人材育成の全貌を明かす。

#1
東レが製造販売する自動車・電子部品向けの主力製品「PBT樹脂」の原料に、製造段階で異物が混入していたことが発覚した。東レの内部調査により、異物の正体は工場のずさんな管理により破損した製造設備で、少なくとも2024年8月から25年3月ごろまで異物混入が継続していた可能性がある。同社が「懸念品」と分類した製品は約1万トンに及び、その大半が既に出荷されていた。だが東レは問題を矮小化し、多くの納入先にこの事実を報告していない。

インベストメントバンカー M&A請負人の正体#1
日本企業が関与するM&Aなどの取引総額(ランクバリュー)が、2025年に50兆円を突破した。24年の20兆円台から倍増した驚異的な膨張の理由は、豊田自動織機の非公開化やNTTによるNTTデータグループの完全子会社化などの大型ディールが相次いだことにある。その裏でシナリオを描き、取引が成立すれば数十億円、時には百億円超という巨額の成功報酬を手にするのが投資銀行だ。野村證券、米ゴールドマン・サックス、三菱UFJモルガン・スタンレー証券――。彼らの最新序列を明らかにし、過熱する人材争奪戦の内幕と市場の行方に迫る。

組織統合の断行により、巨大なワンチームとなったデロイト トーマツ。しかし、真の変革はこれからだ。AI(人工知能)の進化は、従来の「コンサルタントが時間を売る」ビジネスモデルを根底から破壊しようとしている。インタビュー後編では、機能別組織から「産業別(セクター)組織」への大転換、そして「工数報酬」から「成果連動報酬」への移行という、業界の常識を覆す新会社の「青写真」について、木村・長川両氏が赤裸々に語る。

2025年12月1日、デロイト トーマツ グループが、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリーの主要3法人を統合し、合同会社デロイト トーマツを発足させた。なぜ今、専門性を持つ各組織を一つにまとめる必要があったのか。新会社の代表執行役を務める木村研一氏(グループCEO)と長川知太郎氏の両トップが、統合の真の狙いと、競合アクセンチュアと一線を画す「質的転換」への戦略を明かした。

#2
東レの生産拠点における建設・修繕工事を巡り、不適切な取引が行われている疑いが浮上した。ダイヤモンド編集部が入手した内部資料により、東レが1980年代から運用する独自の発注手法「KSK」が、下請け会社に対して著しく低い労務単価を一方的に設定している実態が明らかになった。建設労働者の待遇改善などを目的とした改正建設業法に抵触する可能性がある。品質不祥事を招いた「原価低減」のゆがみが、協力会社への不当な対価設定という形で露呈している。

#16
みずほフィナンシャルグループの木原正裕社長が、就任5年目に入る2月1日を前にダイヤモンド編集部の独占インタビューに応じた。システム障害の対応から始まった木原体制は、2025年度に1兆円超の過去最高益を見込む。メガバンク3位という規模の評価に対し、木原氏は「単純な金額だけで比較しても意味がない」と断じ、ROE(自己資本利益率)など「クオリティー」を競う姿勢を鮮明にした。木原氏が初めて詳細に語った次世代リーダーに求める五つの資質、そして最高益の先に見据える「志」を明らかにする。
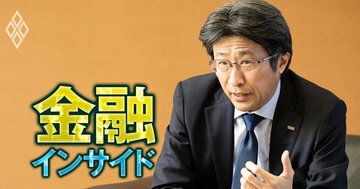
#1
東レが製造販売する自動車・電子部品向けの主力製品「PBT樹脂」の原料に、製造段階で異物が混入していたことが発覚した。東レの内部調査により、異物の正体は工場のずさんな管理により破損した製造設備で、少なくとも2024年8月から25年3月ごろまで異物混入が継続していた可能性がある。同社が「懸念品」と分類した製品は約1万トンに及び、その大半が既に出荷されていた。だが東レは問題を矮小化し、多くの納入先にこの事実を報告していない。

年末繁忙期を迎え、宅配便大手の佐川急便が創業来初めて、災害以外の理由で集荷停止に追い込まれた。同社は「予測を大きく上回る荷物増加」が背景にあると説明するが、実際には別の理由があった。東京・江東区の巨大物流拠点「Xフロンティア」だ。関係者への取材から浮かび上がったのは、大型施設への集約戦略の失敗、協力運送会社の離反、そして急拡大する越境EC事業への対応のほころびだった。12月中旬を過ぎた今も配達遅延は続き、年末年始の繁忙期を前に出口は見えない。物流業界を震撼させた「佐川ショック」の真相に迫る。

生成AIが爆発的に普及した2025年を経て、26年は一体どのような年になるのか。GMOインターネットグループの熊谷正寿会長兼社長は「ヒューマノイド元年になる」と断言する。AIとロボットがもたらす「人類史上最大級の産業革命」の展望と、米中に後れを取る日本の課題、そしてGMOの戦略について熊谷氏に聞いた。

2026年10月、東京証券取引所によるTOPIX(東証株価指数)の改革が実行段階に入る。市場区分とのひも付けを廃止し、流動性と時価総額で構成銘柄を厳選するこの改革により、現在より約600社少ない約1100社体制へとスリム化される見通しだ。基準未達企業には「段階的除外」という過酷な措置が待ち受け、同時に進むコーポレートガバナンス・コードの改訂も経営への圧力を高める。市場の新陳代謝を促す大改革の全貌と、企業が直面する生存競争の行方を解説する。

集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染した人への国家賠償金の支払いが、今年に入り著しく滞っていることが分かった。ダイヤモンド編集部が国に情報開示請求を行ったところ、賠償金の支払件数は前年比6割程度に落ち込んでいた。法務省における事務手続きの遅れが原因で、デジタル庁主導で導入された新システムに不具合が生じた可能性がある。政府がひた隠す「DX失敗」が、B型肝炎患者に悪影響を及ぼしている。

組織統合の断行により、巨大なワンチームとなったデロイト トーマツ。しかし、真の変革はこれからだ。AI(人工知能)の進化は、従来の「コンサルタントが時間を売る」ビジネスモデルを根底から破壊しようとしている。インタビュー後編では、機能別組織から「産業別(セクター)組織」への大転換、そして「工数報酬」から「成果連動報酬」への移行という、業界の常識を覆す新会社の「青写真」について、木村・長川両氏が赤裸々に語る。

2025年12月1日、デロイト トーマツ グループが、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリーの主要3法人を統合し、合同会社デロイト トーマツを発足させた。なぜ今、専門性を持つ各組織を一つにまとめる必要があったのか。新会社の代表執行役を務める木村研一氏(グループCEO)と長川知太郎氏の両トップが、統合の真の狙いと、競合アクセンチュアと一線を画す「質的転換」への戦略を明かした。

2026年も続くとみられる株高基調を追い風に、証券業界が活況に沸いている。最大手の野村ホールディングスは、前期に19年ぶりの過去最高益を記録し、今期もその勢いは止まらない。その数字は、かつてトヨタ自動車を抜き去り「利益日本一」に輝いた1987年のバブル経済期をほうふつとさせる。だが同じ「黄金期」でも、その中身は似て非なるものだ。収益構造が激変した野村の現在地と死角を追う。
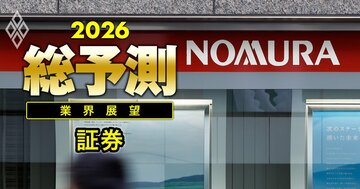
年末繁忙期を迎え、宅配便大手の佐川急便が創業来初めて、災害以外の理由で集荷停止に追い込まれた。同社は「予測を大きく上回る荷物増加」が背景にあると説明するが、実際には別の理由があった。東京・江東区の巨大物流拠点「Xフロンティア」だ。関係者への取材から浮かび上がったのは、大型施設への集約戦略の失敗、協力運送会社の離反、そして急拡大する越境EC事業への対応のほころびだった。12月中旬を過ぎた今も配達遅延は続き、年末年始の繁忙期を前に出口は見えない。物流業界を震撼させた「佐川ショック」の真相に迫る。

#11
三菱UFJフィナンシャル・グループが、2026年の新体制移行へ動きだそうとしている。亀澤宏規社長の後任には、三菱UFJ銀行の半沢淳一頭取が就く公算が大きい。焦点は空席となる銀行頭取ポストだ。その最有力候補に加え、さらにその先の「次々期」頭取候補も浮上。国内最大の金融グループのトップに上り詰める王道出世に「新条件」が加わりつつあることが明らかになった。

国の集団予防接種でB型肝炎に感染した被害者への賠償が、法務省における事務処理の遅滞により大幅に減少している。その原因を法務省はひた隠しにしている。B型肝炎訴訟を日本で最も多く手掛けるベリーベスト法律事務所の酒井将代表がダイヤモンド編集部のインタビューに応じ、国の対応への憤りを語った。

2期連続の最高益更新に向けて視界良好な野村ホールディングス。2025年に5万円を超えた日経平均株価は、26年も高値5万9000円と強気の見通しを示す。ビジネスモデル変革の成果が表れ、全てが順調に見える中、奥田健太郎社長の口から出たのは「死角はたくさんある」という意外な言葉だった。奥田社長が26年の市場予想、そして直面する「真の課題」を明らかにした。