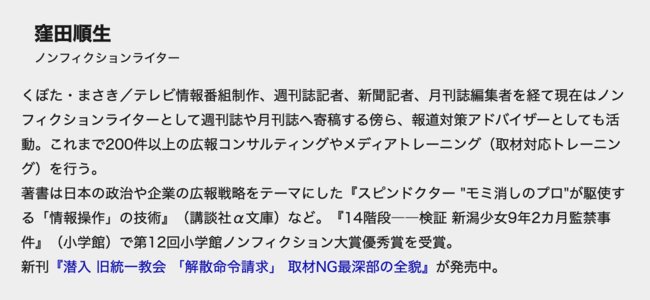SDGsに含まれた意味、日本の未来の若者たちはどう思うか
日本ではSDGsといえば、レジ袋をやめてエコバッグを使ったり、プラスチックストローをやめたり、太陽光パネルをいたるところに敷き詰めたりという「エコ」の言い換えだと思われがちだ。しかし、それはあくまで表面的な話であって、国連に影響力のある西側諸国が競争を有利に進めていくため、「敵」を名指しで叩いている部分もあるのだ。
わかりやすいのは、SDGsの目標7「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」と、目標13「気候変動に具体的な対策を」に基づくカーボンニュートラルだ。
これを持ち出されると、世界最大のCO2排出国である中国や、天然資源大国のロシアは黙るしかない。電動化が欧米よりも進んでいない日本の自動車産業も同じだ。つまり、SDGsは誰もが逆らいにくい理想的なスローガンの中に、西側諸国が自分たちにとって有利にゲームを進めるための「不公平なルール」が巧妙に織り込まれているという側面もあるのだ。
そんなSDGsの中に、「すべての人に健康と福祉を」という目標がある。ご想像通り、WHOの活動に密接に関係している。そして、この目標の中での具体的な取り組みとして含まれているのが、「薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する」である。
ここまで言えば、もうおわかりだろう。これもWHOが飲酒規制を各国に広げていくための「世界戦略」の一環なのだ。
そして、日本はまんまとこの術中にハマっている。世界では認知や理解にかなり温度差のあるSDGsだが、日本はこの手のスローガンが昔から大好きということもあって、かなり普及している。
政府から大企業まで何かにつけて「SDGs」を連呼して、最近ではテレビ局もSDGsをテーマにした番組をよく放送している。今後も、こうした動きはさらに加速していくだろう。
さて、そんな「SDGs信者」の日本が、WHOや国連から「SDGsの観点からアルコールの有害な摂取を防止するため、居酒屋の飲み放題などを禁止すべきでは」とプレッシャーをかけられたらどうか。
「いや、我々はレジ袋とかだったら喜んで廃止しますけれど、飲み放題は文化なので」と毅然とした態度でノーと言えるのか。
「あなたたちは、日本中どこででも“SDGsを推進します”って宣言してるじゃない、あれはうそなの?」と詰められたらかなり苦しいはずだ。SDGsを推進します、と国内外に宣言をしている大手酒類メーカーは、「持続可能な社会に背を向けている」と、海外投資家から嫌われるかもしれない。
最近、バラエティ番組では「飛行機の座席でタバコが吸えた」などの昭和のVTRを流して、スタジオにいる若者たちが「信じられない」と驚くようなやりとりをよく見かけるが、「酒」もこのパターンになるのではないか。
「え?令和の居酒屋って2時間飲み放題だったの?すぐ酔っちゃうし自分のペースで飲めないから楽しくなさそう。もしかして罰ゲーム?」なんて感じで、若者たちがドン引きする時代がくるかもしれない。
(ノンフィクションライター 窪田順生)