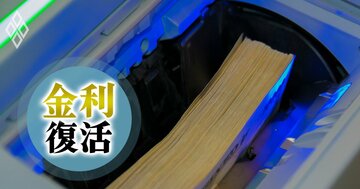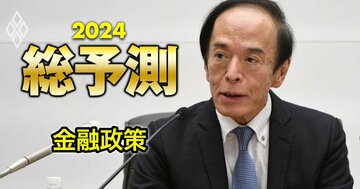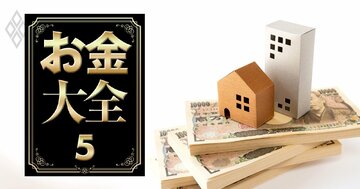Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
金利、中長期的には2~3%へ
利上げ効果、変動型ローン増加で強まる
金利が上昇する機運が高まっている。長期金利は、日本銀行が2023年7月にイールドカーブコントロール(YCC)の運用を柔軟化して以降、海外金利や国債市場の動きを反映しやすくなっており、10年国債利回りは一時1%近くまで上昇した。
短期金利も、今後の政策金利の予想値が反映された「オーバーナイト・インデックス・スワップレート(OIS)」は1年先1カ月物で0.2~0.3%で推移しており、市場参加者の間では今後1年間でマイナス金利の解除と0.25%ポイント程度の利上げが見込まれている。エコノミストの間でも24年春先に日銀が短期金利の引き上げを始めるとの予想が大勢だ。
こうした見方の背後には、賃金と物価が共に上昇する兆しが見られていることがある。企業の賃上げ意欲は強く、24年の春闘では前年以上の賃上げが予想され、こうした賃金の上昇を物価に転嫁する動きも続くとみられる。
すでに消費者物価の上昇率は日銀の2%物価目標を21カ月連続で超えているが、今後も日本のインフレ率が政策目標の2%で定着することになれば、景気を過熱も冷却もしない「中立金利」は2~3%と予想され、将来的には金利水準はそこまで上がる可能性がある。
日本では本格的な利上げが30年以上実施されていないが、企業や家計への利上げの波及では「変動金利チャネル」が主な波及経路に変わっている。
金利上昇への耐性を見る上では、とりわけ急増する変動金利型住宅ローンを通じた影響が大きくなっていることに要注意だ。