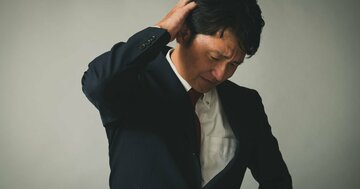写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
日本人の長寿化は、遺産相続争いの状況をも変えてきている。かつてそれは親の死後に起こるものだったが、今や親の生存中から争いやだまし合いが始まるのだ。もしあなたが一人っ子ではなくて親が健在であれば、あるいはあなた自身に子どもが2人以上いるのならば、「遺言があれば大丈夫」とは絶対に考えないでほしい。どんなに仲が良い兄弟姉妹でも、親の財産を巡って悲惨な争いが起こる確率が非常に高いからだ。(NPO法人二十四の瞳、社会福祉士 山崎 宏)
「争続」の背景にあるのは
終末期療養の長期化と家族の負担増
社会福祉士として財産まわりの相談を受けていて、最近、実感していることがあります。コロナ禍の前後で、明らかに「争族」の質が変わってきている、ということです。
もともと「争族」とは、親の死後に展開される遺産相続争いのことを指していました。しかし、ここ数年の「争族」は、親が生きているうちから勃発します。老い衰えた親を管理下に置いて、自分に都合がいいようにコントロールする……これが現在の「争族」の実態といえます。
平均寿命と健康寿命の差を、終末療養期間と呼びます。要するに、エンディングを迎える直前の療養期間のことです。ちなみに健康寿命とは、医療や介護などの制約を一切受けずに自立した生活を送ることができる状態のことを言います。昭和40年代半ば、終末療養期間は約5年でした。私の祖父母は4人とも、65歳までに亡くなっています。ところが2022(令和4)年の終末療養期間は、男性が平均9年、女性が12年となっています。
最近の状況では終末療養期間は平均10年というところです。志村けんさんのように、発症から2週間もたたずに他界されるケースは珍しく、読売巨人軍の終身名誉監督の長嶋茂雄さんなどは、脳梗塞発症から20年以上も療養期間が続いています。また、私の経験則では、認知症の場合は7年~8年と、平均よりやや短い傾向にあります。
「争族」の観点から言えば、志村けんさんのようなケースでは従来型の遺産争いになりますが、これからは現代型の「争族」、つまり認知症の兆候が見られたり要介護状態になったりした老親を早期に取り込み、財産を手中に収めようとする兄弟姉妹間の争いが増加すると予想されます。