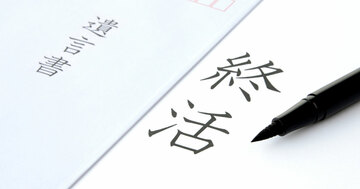山崎 宏
年収800万円、部長職、妻と大学生の娘――順風満帆だった56歳の人生が、わずか1年で崩壊したきっかけは「介護」だった。妻と娘は家を出て離婚寸前、職場復帰の目処は立たず、退職が現実味を帯びてくる……認知症の父を支えるために「よかれ」と信じた選択は、何が間違っていたのだろうか?

「介護と仕事の両立、もう限界…」50歳人事部長が選んだ、母と自分を救う“意外な決断”とは
仕事をしながら、親や配偶者など家族の介護・ケアを行う、ビジネスケアラー(ワーキングケアラーとも)が増えています。企業に雇用されている社員、さらには管理職や専門職として働く人が親の介護問題に直面した場合のインパクトは甚大です。親の介護の負担が増せば増すほど子の生活は一変し、「天国から地獄」といってもいいほどです。本記事で紹介するのは、離れて暮らす母の介護に直面した会社員の事例です。実際にあったケースをもとに、起死回生の介護離職対策について考えます。災い転じて福となす。多くの現役世代が抱える老親問題や介護離職問題のヒントになるはずです。

「遺言で遺産相続だけはやめておけ」と社会福祉士が警告、醜さを増した“争族”の実態
日本人の長寿化は、遺産相続争いの状況をも変えてきている。かつてそれは親の死後に起こるものだったが、今や親の生存中から争いやだまし合いが始まるのだ。もしあなたが一人っ子ではなくて親が健在であれば、あるいはあなた自身に子どもが2人以上いるのならば、「遺言があれば大丈夫」とは絶対に考えないでほしい。どんなに仲が良い兄弟姉妹でも、親の財産を巡って悲惨な争いが起こる確率が非常に高いからだ。

毎年10万人が介護離職…「介護しながら会社員」300万人超を救う“知られざる存在”とは?
仕事(ビジネス)をしながら親などの介護(ケア)をする、いわゆる「ビジネスケアラー」は、現在約300万人以上いるといわれます。その多くは、老親のケアに悩みながらフルタイムで働く中高年、現役世代のビジネスパーソンです。第二次安倍政権が“介護離職ゼロ社会”の実現をブチ上げたのは2016年の秋でした。企業への介護休業制度の法定義務化が話題になったものの機能不全に陥っており、毎年10万人もの介護離職者が増え続け、360万人もの人々が介護のために会社を辞めているのです。今回の記事では、老親に何かが起こったとしても、従業員が職場を離れなくても済むためには会社はどうしたらいいのか、具体的な方法論をお届けします。
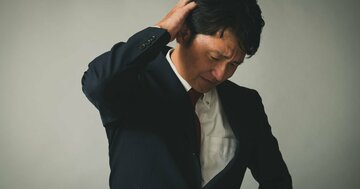
東大卒エリートが泣きじゃくった日…アルツハイマーの母を介護、NGワードだった「生活保護」
日本では年々、働きながら在宅介護を行う「ビジネスケアラー」が増えています。しかし、子育てと違い、何年で終わるか分からない上にだんだん負担が重くなっていく介護を自宅で行うのは本当に大変です。仕事との両立に悩んだり、妻に離婚されてしまったりと、さらなる不幸に襲われることも珍しくありません。筆者のところにも、たくさんのビジネスケアラーから相談が持ちかけられます。今回は、ある東大卒エリートのケースを紹介します。

年末年始に親に会ったら伝えるべき「老後のNG」10項目
メリークリスマス!年末年始は久しぶりに、普段離れて暮らす親に会う、という方も多いのではないでしょうか。この記事は、クリスマス、または年末年始に、あなたから親御さんに伝えてほしいクリスマスプレゼントのつもりで書きました。最後に読者プレゼントを用意しましたので、ぜひ最後まで読んでほしいと思います。

「子どもに迷惑かけない終活」75歳以上の9割超ができていない!お盆に親子で話すべき10のこと
今年のお盆は実家に帰省する、という予定の人も多いのではないでしょうか。離れて暮らす家族が集まるお盆は、終活を始める絶好のチャンスです。久しぶりに高齢の親に会ったのであれば、じっくりと腰を据えて「これからどうしたい?」という話しあいをしてみませんか。終活サポートやシニアの人生相談を数多くこなす筆者は「正しい終活ができているシニアは1割もいない。確認すべきことをしなかったために苦労するのは、残された遺族、ほとんどの場合は現役世代の子どもです」と指摘します。本記事では終活の第一歩として、親と何を話し合うべきなのか。10のポイントを解説します。

認知症の症状にはさまざまなタイプがあり、タイプによっては人格が豹変して周りの人へ攻撃的に当たるようになり、状況次第では精神科病院への入院も必要になる。ある日、老父の暴力や暴言に悩まされる息子からSOSの電話がかかってきた。

長寿命化、超高齢化が進む日本では、40代以上のビジネスパーソンの多くが「親の介護問題」に直面することになります。国は介護休業制度を定めていますが、筆者は「行政の意図が周知されておらず、休みを使い果たした結果追い込まれ、どうにもならなくなる人が多い」と指摘します。「親の介護問題に直面した社員に対して、企業がやるべきサポートがある。しかもそれは簡単だ」という筆者の提案とは?

介護休業における取得可能日数を増やす企業が増えているが、介護休業を取ったところで、会社を休まなくてはならないことには変わりない。しかし、「たとえ親の介護が必要になったとしても、職場を離れなくていいように会社がサポートする」という企業が現れた。この新しい介護離職対策を打ち出したのは、東京都港区三田に本社を構えるエイブリックである。同社の取締役執行役員兼CAO(Chief Administrative Officer)である長野典史氏に、なぜこうした取り組みを始めたのかを取材した。

家族が要介護になったときに、労働者が介護のために3回まで、通算93日まで休業できる「介護休業制度」。労働者に認められた権利だが、いざ実際に利用するとなると一筋縄ではいかないことも多い。介護の問題は、実際に携わった経験がない者には実感がわかず、自分事として考えらない上司もいるためだ。しかしこれは誰の身にも高い確率で起こることであり、少子高齢化が進む日本では今後どんどん介護休業制度の申請者が増えてくるはずだ。都銀で総合職を務める田代さん(男性42歳、仮名)のケースを通して、現在の介護休業制度の落とし穴について考える。
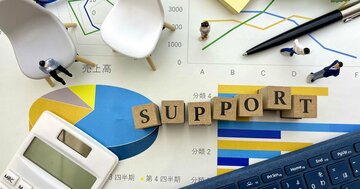
終活サポートやシニアの人生相談を数多くこなす筆者のところには、親のケアに悩む現役世代からの相談もやってきます。40代の会社役員からの相談は壮絶でした。尊敬する父がおかしくなってしまった、銀座のクラブからの高額請求、コンビニに立てこもり警察からの呼び出し、さらには妻に性暴力を振るったというのです……。

お盆に故郷へ帰省して、久しぶりに顔を合わせた親や兄弟と相続の話になり、「何かあってからでは遅いから、遺言を書いておいたほうがいいんじゃないか」といった話になった方もいるのでは。しかし、終活サポートやシニアの人生相談を数多くこなす筆者は「遺言こそが残された家族に遺恨を起こす原因。絶対にやめたほうがいい」と言います。遺言から遺恨が生じるとは、どういうことなのでしょうか。

多くの老親世代(70~80代)が「PPK(ピンピンコロリ)」を望むが、現実には誰かの介助を受けながら最期に至るケースがほとんどだ。現役世代は、老親の死後に「争族」が起きないよう、「まさか」の事態に備えなくてはならない。どう備えれば良いのか、考察する。

高齢者に「終活」や「シニアライフ」をアドバイスする民間資格が雨後の筍のように増えている。新規事業や副業に役立てようと期待して、こうした資格を積極的に取得する人もいるようだ。ただし、資格を取得するだけではうまくいくはずがない。

日本全国、終活セミナーが花盛りである。しかしながら、その実態は、成年後見制度や家族信託や葬儀の生前予約ありきで、さながら、認知症1000万人時代に乗じた「販売促進の場」と化している。