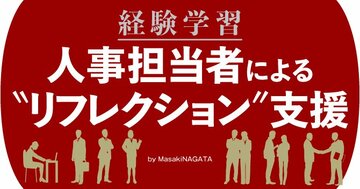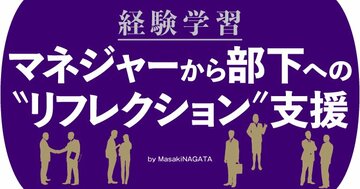“エルダー制度”を導入した3つの目的とは?
永田 経験学習の利点や魅力はどのようなところにあると思われますか?
茂木 「教える」レベルを一定にできるという部分はもちろんですが、教える側も、教えることによって成長できるという点も大きいと感じています。新入社員とエルダーだけではなく、そこに関わる人たち全員の成長にもつながるのが経験学習ではないか、と。一定の場所でグルグル回るのではなく、回しながら上がっていくようなイメージ、といえばよいでしょうか。
永田 螺旋(らせん)ですね。
茂木 まさにそうです。経験したことがナレッジとして共有でき、財産がどんどん増えていくと感じています。
永田 教える側も経験学習を回していける。
茂木 はい。将来的にはチームマネージメントを担う人もいますし、OJTリーダーから所長になって営業所をまとめていく立場になる人もいます。ここで経験したことは、役割が変わっても、きっと活かせるはずです。その点も大きな魅力といえますね。
永田 お話をうかがって、御社の人財育成で経験学習がしっかりと根付いていることがよくわかりました。そもそも、経験学習は、どのようなきっかけで取り入れられたのでしょうか?
髙木 2017年から始めたのですが、当時は新入社員を6人1組のチームにして課題を設け、グループワークを行っていました。その中で、振り返りの質を上げるために、私たち教育部門が個人面談を入れて、振り返りの方法を教えるようになっていったのです。振り返りをしっかり行うことによって、現場に出た後も新入社員それぞれが経験学習を回せるようになったらよいと思ったのがきっかけの一つです。

永田 振り返りの方法は、具体的にはどのようなことを教えられたのですか?
髙木 たとえば、名刺交換をするときに目上の相手よりも高く持ってしまったら、「目上の人に対しては下に持つものだよ」と教えます。ここで1つの経験と振り返りができますよね。この経験を活かせば、懇親会などの席で乾杯するとき、同じ要領でコップを少し下に下げれば、「目上の人を立てられる人だな」と、周囲の信頼度が上がります。「研修でやっていることは、現場と同じではないかもしれないけれど、そのように概念化することによって、仕事でも、その経験が活きるよ」と、新入社員には話していました。いまはそのような振り返り面談は行っていませんが、研修時から経験学習を回せるようなシートを使ったり、チームで振り返りをしたりすることは行(おこな)っています。
永田 そのような経緯もあって、エルダー制度につながっていった、と。改めて、エルダー制度の概要について教えてください。
髙木 弊社がエルダー制度を導入する目的は、「新人の成長促進と職場への定着」「エルダーの育成指導力の向上・強化」「各職場における育成風土の醸成」の3つです。
エルダー制度自体は、かなり以前からあったのですが、2017年に経験学習を取り入れたタイミングで、エルダーカリキュラムも変えていこうと大きく修正しました。結果、エルダーに対する教育も進み、私たちが振り返り面談を行わなくてもエルダーや係長が把握できているようになり、振り返りの質も上がってきていると感じています。
永田 エルダーカリキュラムは、シートを使って行っていらっしゃるということでしたね。
髙木 はい。「エルダーカリキュラムシート」という名称のものです。シートには、新入社員、エルダー、上司の3人が関わるのですが、新入社員は、最初に所属されたら、目標設定から始めます。所属部門としての目標、そして、上司からの「3〜5年後の期待する姿」と、本人の「3〜5年後に目指す姿」を決めます。そこからさらに面談を通しながら、「1年後のありたい姿」を上司が設定し、その中で短期と長期の2つの目標を定めるのです。ここまでは上司と新入社員のやりとりです。
その後、先ほどお話しした育成導入期、育成前期、育成後期の時期ごとにマイルストーンを置いていくところからエルダーが入ってきます。具体的な仕事の内容を書き込み、新入社員は、それに対して、自分で目標を立て、実践した後に振り返りをするような流れになっています。実践したことはどういうことで、実践してわかったことは何か、次はどうするか、などを書き込んでいくのです。
永田 まさに、経験学習ですね。それぞれの仕事ごとに経験学習を回させることによって、振り返りの習慣ができてくる。
髙木 そうです。さらに、新入社員が記入し終わった後に、エルダーと上司と面談をして、エルダー、上司それぞれがコメントを書くという流れになっています。