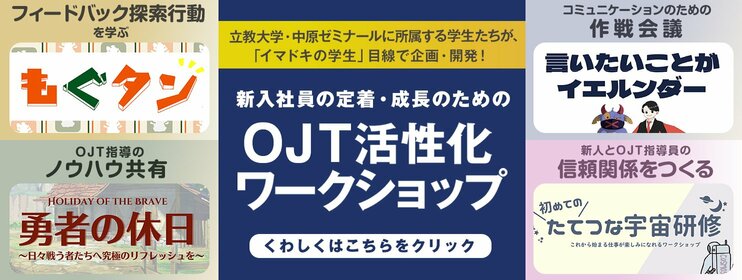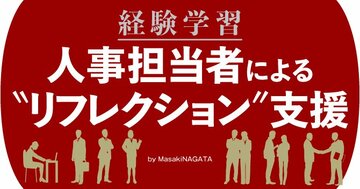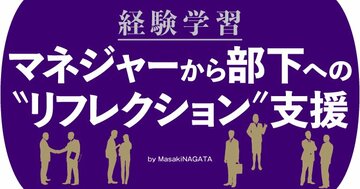教育部門と現場の橋渡しとなるOJTリーダー
永田 エルダーカリキュラムを始めてから、現場での成果はいかがですか?
髙木 私たちは毎日毎年やっているので、できている実感があまりなかったのですが、エルダー向けハンドブックで永田さんがインタビューされたものを読んだら、「現場の社員にこんなに根付いていたんだ!」と思えました。茂木さんも、階層別の課長や部長の雰囲気が変わってきたとおっしゃっていましたよね?
茂木 はい。いままでは、所属長たちも、やらなくてはいけないとわかっていてもそこまで手をかけられないというところがあったのではないかと思います。それが、新入社員とエルダーがしっかり振り返りをしていて、目標を立てるときに自分も関わっているとなると、コメントもきちんと書かなくては、となります。人を育成すること、育成に関わることを楽しいと感じる人が増えていると感じています。ツールに沿っていけば、新入社員の成長を応援できるというノウハウを上司側も学べたことによって、育成の後押しをしやすくなったという面もあるのではないでしょうか。
永田 同じように回していても、経験学習が身に付く人とそうでない人の個人差も出てくると思うのですが、そのようなときはどうされていますか?
髙木 たしかに、振り返りの質も新入社員によって違いますし、フィードバックも上司の質で変わってきます。新入社員自身が振り返りをできていないときは、新人フォロー研修などで直接本人にフィードバックしたり、エルダーや上司の関わりが足りないと感じたときは、OJTリーダーと連携して現場の情報を聞いたりしています。

永田 OJTリーダーはどのような役割でしょうか?
髙木 エルダー制度内では、エルダー、OJTリーダー、上司、新人の4つの役割があり、OJTリーダーは「支社支店内の育成リーダー」という位置づけになります。たとえば、A営業所の新人はうまく育っているけれど、B営業所ではうまくいっていない、というような育成のばらつきがあったとき、これまでは、その新入社員の素養だと理解してしまっていました。ですが、エルダーや所属長による部分もありますよね。そこの横の連携をつなげるのが、OJTリーダーです。支社支店の育成リーダーとして、横軸を通して育成ナレッジをまとめるような役割です。
OJTリーダーは、育成オリエンテーションにも参加しますし、エルダーを集めての振り返りを行うなど、私たち教育部門と現場の橋渡しのような役割も担っています。
永田 経験学習をうまく回していると、新入社員の成長が早いという実感はありますか?
髙木 早咲きの社員と遅咲きの社員はいるのですが、遅咲きの人に対しても根気強く関わっていると、2年後、3年後に必ず花開く瞬間があると感じています。その点では、経験学習をきちんと回すことは効果があると思っています。
永田 今後、人財育成を、さらにどのようにしていきたいと思われますか? 茂木さんと髙木さん、それぞれの考えをお聞かせください。
茂木 人財育成に、「魔法の杖」はないと思っています。自分が経験したことを活かせるところもあれば、活かせないところもあります。何より、相手がいることなので、自分の思いどおりにはなかなかいきません。それでも、いろいろな人がいること、相手と自分が違うことを前提とし、自分と一緒に仕事をしている人は必ず成長すると信じて支援をしていきたいですね。そのような姿勢を当たり前のものとして考えられる組織にしていきたいと思っています。
髙木 OJT制度を始めたとき、たとえ、OJTリーダーがいなくても、横の連携がしっかりとできていて、組織全体で人を育てられるような風土にしたいという思いがありました。将来的には、OJTリーダーのような存在がなくても、「いろいろな人が声をかけてくれて、自分を成長させようとしてくれる。だから私も頑張ろう!」と社員が思えるようになったらよいと思います。育成方法の改革を重ねて、振り返り面談をなくすことができたことを考えると、それも実現できるのではないでしょうか。それから、まだ、OJT制度を実施できていない技術職の分野でもこのようなOJT文化を進めていきたいですね。
永田 御社の人財育成の取り組みと仕組みがよくわかりました。今日はありがとうございました。

聞き手●永田正樹 Masaki Nagata
ダイヤモンド社HRソリューション事業室顧問
ビジネス・ブレークスルー大学大学院助教
立教大学大学院経営学研究科リーダーシップ開発コース兼任講師
博士(経営学)、中小企業診断士、ワークショップデザイナーマスタークラス。「アカデミックな知見と現場を繋ぎ、人と組織の活性化を支援する」をコンセプトとし、研究者の知見をベースに、採用・育成・定着のスパイラルをうまく機能させるためのツールやプログラムの開発に携わる。また、企業のOJTプログラムや経験学習の浸透のためのコンサルテーションも行っている。著書に『管理職コーチング論 上司と部下の幸せな関係づくりのために』(東京大学出版会)がある。