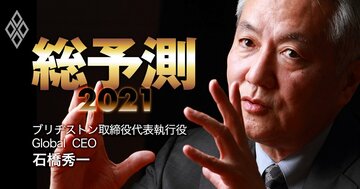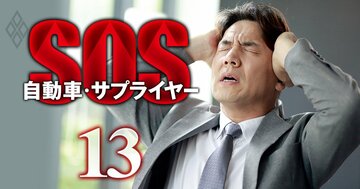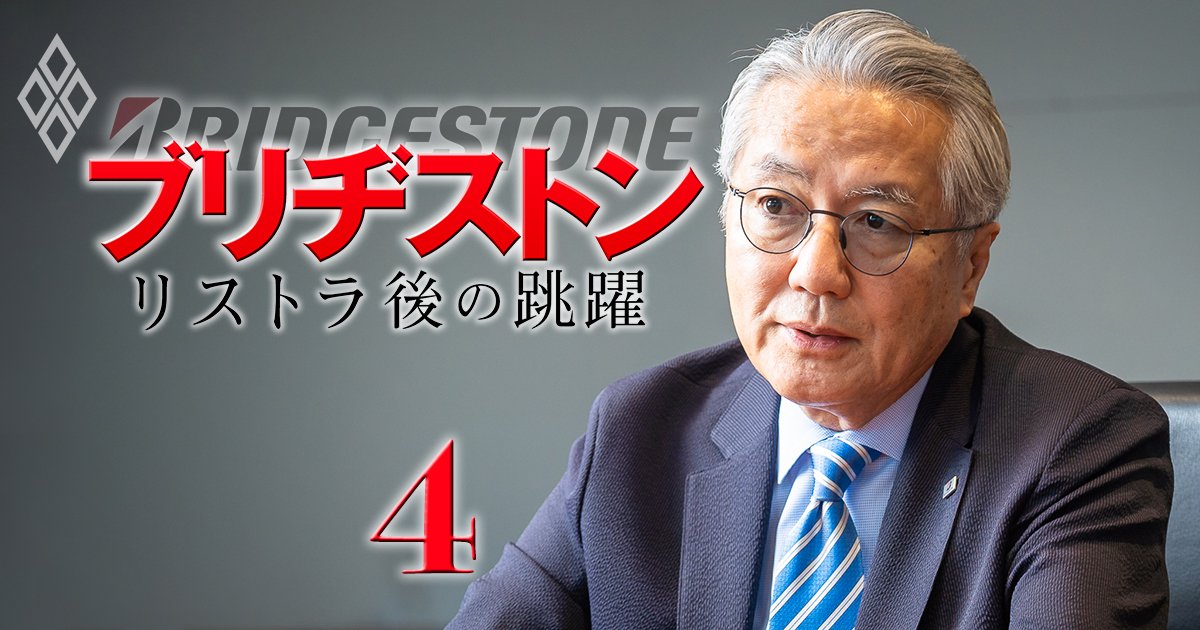 Photo by Masato Kato
Photo by Masato Kato
2020年3月からブリヂストンを率いる石橋秀一CEO。就任から5年超かけて、事業売却や工場閉鎖を進めてきた。こうした再編は、今年度でほぼ終了するものの、残されたリストラ候補があることも事実だ。同時に、25年度下期からは「質を伴った成長」に突入するという。跳躍に向けた「成長事業の実名」とは。特集『ブリヂストン リストラ後の跳躍』の#4では、残された“リストラ候補”と、跳躍に向けた「成長事業」について石橋CEOに余すところなく語ってもらった。(ダイヤモンド編集部 山本興陽)
2035年以降に、逆風が吹くが
新素材含め「新しい価値」をつくり乗り切る!
――「過去の課題に正面から向き合い、先送りしない」というメッセージを対外的に常々発信しています。この言葉の真意は。
(2020年3月の最高経営責任者(CEO)就任前後で)私の前任時代の業績を分析しました。前任時代に売上高はあまり変わりませんでしたが、営業利益率が15年度から継続して落ちていました。これは事実です。
ブリヂストンは創業者の時代から「営業利益率10%」を目安としていましたが、19年度には調整後営業利益率が10%を切りました。私は、これを非常に重たい課題だと捉えました。
経営の課題には、大きく分けて、オペレーションの課題と、事業ポートフォリオ構築といった構造的な課題の二つがあります。(コスト削減や効率化など)オペレーションの改善で、構造的な課題は解決しない。
事業ポートフォリオの決定は、まさに構造的な課題です。かねてブリヂストンは事業ポートフォリオへの発想が少し弱かった。やはり、事業の見直しが必要だと考えました。昔は良い事業だったかもしれないけど、時が流れる中で、価値創造ができているかどうかを見極める必要がありました。
そうした観点から言えば、営業利益率が悪化し続けてきた要因の一つが、防振ゴムや化工品などといった「非タイヤ事業」でした。ずっと赤字で、赤字額も膨らんできていたのです。とにかく、ここを構造改革しなければなりませんでした。
――CEO就任から5年半、過剰生産能力の削減や、不採算事業の売却、撤退を行ってきました。残された再編・再構築の事業は何でしょうか。
石橋CEOの就任から5年半で、従業員数は15%減、生産ゴム量は20%減となった。だが、「残されたリストラ候補」はまだあるという。そして、リストラフェーズから跳躍フェーズへの移行に当たり、成長事業に位置付けるものは何か。さらに、石橋CEOが、「2035年以降が課題だ」とみる理由とは。次ページ以降では、「残されたリストラ候補」と「成長事業の実名」を明かした。