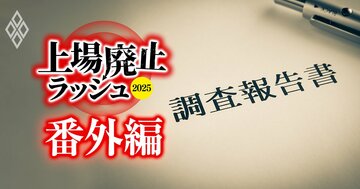『週刊ダイヤモンド』3月1・8日合併号の第1特集は『上場廃止ラッシュ』です。コーポレートガバナンス・コード導入から10年を迎える2025年、資本市場が激変期を迎えています。企業改革に対応できない上場企業が資本市場から退場を迫られる、淘汰の時代が到来したのです。その「ゲームチェンジ」の実態に迫ります。(ダイヤモンド編集部副編集長 重石岳史)
セブン&アイ、牧野フライス…
「同意なき買収」から何を守る?
「かつては敵対的買収を受けた企業は守らなければならない、という空気があった。今はそんな空気はない。経営陣に追随する安定株主は、ほぼ存在しないと思った方がいい」
 企業改革に対応できない上場企業が資本市場から退場を迫られる、淘汰の時代が到来した Photo:PIXTA
企業改革に対応できない上場企業が資本市場から退場を迫られる、淘汰の時代が到来した Photo:PIXTA
長年投資銀行業務に携わる証券会社幹部はそう語る。この幹部の念頭にあるのは、王子製紙が北越製紙に対して06年に仕掛けた敵対的買収だ。
事業会社の老舗同士による国内初の経営権争奪戦は、日本製紙グループ本社(現日本製紙)や三菱商事がTOB阻止に動いたことで破談した。日本製紙は北越株取得の理由について「北越製紙の経営体制、従業員の生活および地域社会のみならず、製紙業界の秩序を乱す恐れがある」と説明していた。
敵対的買収を「秩序を乱す」と忌避し、被買収者を守るべしとの世論が、当時は確かにあった。だが、「守る」とは一体誰を守るのか。
買収される企業の経営者は守れるかもしれないが、買収提案を受けるほどに企業価値を上げられなかった責任の所在は誰にあるのか。株主とっては株価が上がる買収は、むしろ歓迎されることなのかもしれない。