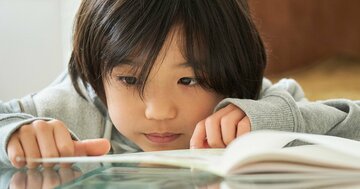女性の負担が大きい限り
少子化は止まらない?
どれだけ支援を充実させても「子育て」を選択する人が増えないのであれば、日本の少子化は今後どうすれば改善されるのか。輸入会社の経営者として女性社員を多く雇用している芳子ビューエル氏は「国の政策も重要だが、会社単位でのサポート体制も必要」だと言う。
「日本でも昨今やっと男性が育休を取るようになってきましたが、まだその割合は低く、依然として女性にかかる負担が圧倒的に大きいのが現状です。弊社には子どもを持つ女性社員が複数人いますが、子どもがいると家庭内感染で病気になったり、都度病院へ連れて行ったり、保育園に呼び出されたりという事態は避けられません。その負担や責任を母親だけが背負うのではなく、夫も会社も協力してサポートしなければ、出産や育児を前向きに捉えることは難しいでしょう」
女性が育児と仕事を両立させるためには、周囲の協力や手助けが重要だ。そして女性の働きやすさを社内で整えることが、経営者としてできる少子化対策ではないかとビューエル氏は語る。
「弊社は1時間から有給が取れて、育児の都合などで出社が遅れる場合は、LINEで連絡をすれば良いことになっています。また子どもが病気の際はリモートワークをすることも可能です。なにより誰がどんな事情で休んでも社内から責めるような言葉が出ないよう、職場全体の意識には気を配っています。休みにくい雰囲気を作らず、『小さいうちは大変だね』と励ますのがトップの仕事。社内制度を整えることはもちろん、一緒に働く社員の心ない言葉を無くす努力が企業側にも必要ですし、そういったサポートの積み重ねで社会全体の少子化を少しずつ変えていければと願っています」
先日、「たまひよ」が発表した「今、何があったらもうひとり産もうと思えますか?」というアンケートでは、1位が「お金」、2位が「いろいろな意味での母への負担解消」という回答だった。また4位、5位には「子育てに関する社会の理解」「職場・会社の理解」が挙がった。もはや少子化改善のためには、子育て支援の充実だけでは追いつかない。社会全体の意識改革が必要だ。